アスベストを含む建物解体の基本と注意点
- 最終更新日:
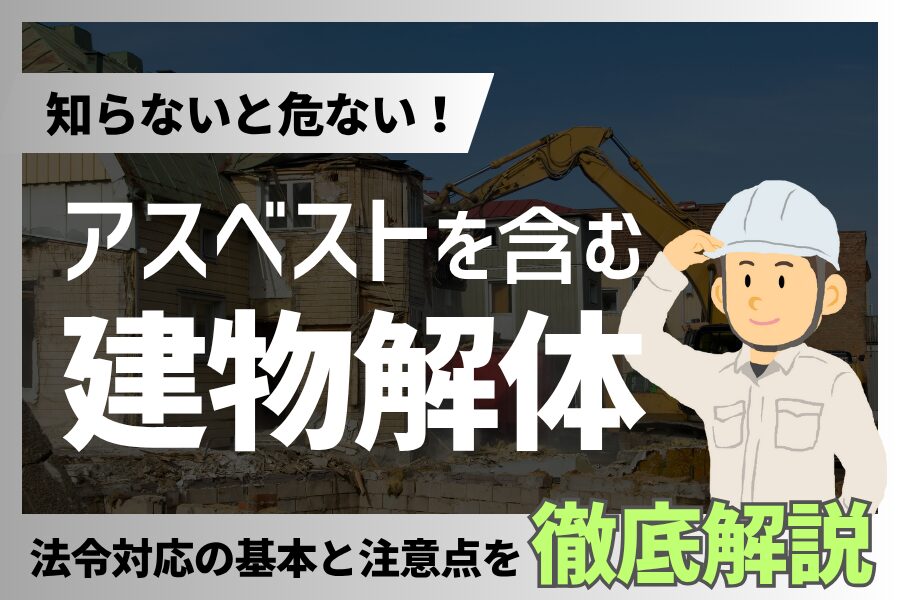
アスベスト(石綿)は、その優れた耐熱性や絶縁性から、かつて多くの建築物に使用されていました。
しかし、アスベストの繊維を吸入することで深刻な健康被害を引き起こすことが明らかとなり、現在では使用が禁止されています。
そのため、アスベストを含む建物の解体に際しては、特別な注意と対応が求められます。
本記事では、企業向けにアスベスト建物解体の基本と注意点をご紹介いたします。
アスベスト建物解体とは?基本的な概要
アスベスト建物解体とは、アスベストを含む建材が使用されている建物を、安全かつ適切に解体・撤去する作業を指します。
アスベストは微細な繊維状の鉱物であり、吸入すると肺がんや中皮腫などの重大な健康被害を引き起こす可能性があります。
そのため、解体作業中のアスベストの飛散防止と作業員の安全確保が極めて重要となります。
アスベストの危険性
アスベストを吸い込むと、肺がんや中皮腫、アスベスト肺などの重篤な病気を引き起こす可能性があります。
発症までに長い潜伏期間があるため、問題が発覚するのは数十年後になることもあります。
解体作業での注意点
解体中はアスベストの飛散を防ぐことが最重要です。
作業員には保護衣や防塵マスクの着用が義務付けられ、作業エリアは隔離されるなど、厳格な安全対策が求められます。
また、法律に基づいた適切な処理と廃棄も不可欠です。
解体前に知っておきたいアスベスト関連法規・規制
アスベストに関する法規制は年々強化されており、解体工事を行う際には最新の法令を遵守する必要があります。
2020年に「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」が改正され、以下の点が強化されました。
法改正で強化されたポイント
- 有資格者によるアスベスト事前調査の義務化
解体や改修工事を始める前に、有資格者によるアスベスト含有建材の仕様状況の調査が原則として義務付けられました。 - 調査結果の報告義務
一定規模*以上の改修・解体工事では、事前調査結果を都道府県などの行政機関に報告する必要があります。
*解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円
作業の安全管理と記録
- 作業計画の作成
石綿使用建築物等の解体作業をする場合は、安全対策を含めた作業計画を事前に作成することが求められます。 - 作業記録の保存
作業計画に基づいた作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存するとともに、
従事労働者の氏名、従事期間等を記録し、40年間保存することが義務付けられています。
アスベストを含む建材の確認方法と調査手順
アスベストを含む建材の有無を確認するには、複数のステップを踏んで慎重に調査を行う必要があります。
これらの手順を確実に実施することで、安全な解体作業につなげることができます。
書面による予備調査
まず、建物の設計図書や施工記録を確認する書面調査を行います。
これにより、アスベストが使われている可能性があるかをあらかじめ推定するとともに、
現地での調査の流れの想定や重点的に調査すべきポイントの絞り込みを行います。
現地での目視調査
その後、現地で目視調査を実施し、劣化状況や過去にアスベストが使用されていたとされる建材の特徴、型番や製造業者などの情報をもとに、
アスベスト含有建材か否かを判断します。
専門機関による分析調査
目視だけでは判断が難しい場合、建材のサンプルを採取し、専門の分析機関にて顕微鏡などを用いた分析調査を行います。
特にアスベスト使用が禁止される前の、2006年9月以前に建てられた建物はアスベスト使用の可能性が高く、こうした詳細な分析が不可欠です。
専門家による正確な調査と判断が、作業員や周囲の人々の健康を守る鍵となります。
解体工事の流れと安全対策
アスベストを含む建物の解体工事は、作業員や周囲の安全を確保するために、厳密な手順と法令に基づいて進められます。
各段階での対応を正しく行うことが、安全かつ適切な工事に欠かせません。
解体前の準備と手続き
最初にアスベスト(石綿)事前調査を実施し、アスベスト(石綿)の有無や使用状況を確認します。
その結果をもとに、解体工事の全体方針が決定され、具体的な作業計画が立案されます。
計画には、使用機材・作業手順・保護措置などが盛り込まれ、関係法令を遵守することが求められます。
そして、実際の作業前には、作業エリアをシートなどで囲い、飛散防止のための養生・隔離を徹底します。
除去作業と廃棄処理の流れ
養生が完了したら、湿潤化を行いながらアスベストの除去作業を実施します。
乾いた状態では繊維が空気中に飛散しやすくなるため、湿潤化することで粉じんの発生を防ぎます。
可能な限り手ばらしにより、慎重に作業を進めることが重要です。
除去後は作業エリアを丁寧に清掃し、作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります。
空気中のアスベスト濃度も専用機器で測定し、安全が確保されたことを確認します。
最後に、除去した建材が飛散しないように梱包、シート掛け等を行い、石綿含有産業廃棄物として処理します。
石綿含有産業廃棄物の処理は、石綿含有産業廃棄物の処理業許可を有する産業廃棄物収集運搬業者に回収を委託する、元請業者が自ら運搬して埋め立て施設等の石綿含有産業廃棄物の処理ができる施設に搬入する等、法令に従って適切に処理します。
このような一連の流れを確実に実施することが、作業員や周辺住民の健康と環境保護の両面から非常に重要です。
アスベスト解体における費用相場と見積もりのポイント
アスベストを含む建物の解体工事は、一般的な解体工事と比べて高度な専門性が求められるため、費用も高額になりやすい傾向があります。
費用を適切に見積もるには、さまざまな条件を正確に把握することが大切です。
見積もり時のチェックポイント
見積もりを依頼する際は、以下の点に注意することが重要です。
- 詳細情報の提供
アスベストの種類、建材の位置、施工環境など、できる限り詳しい情報を業者に伝えることで、正確な見積もりが可能になります。 - 業者の信頼性の確認
過去の実績や保有資格(特別管理産業廃棄物管理責任者など)を確認し、信頼できる業者を選ぶことが必要です。 - 費用項目の内訳確認
仮設工事費、除去費、廃棄物処理費など、見積もりに含まれる項目を確認し、追加費用が発生する可能性がないかを事前に把握しておくことが大切です。
アスベスト解体は、法令順守と徹底した安全対策のもとで行う必要があります。
費用だけでなく、技術力や安全意識を含めて、総合的に信頼できる業者を選ぶことが、安心・安全な工事の第一歩です。
法人向けのアスベストサポートサービスのご紹介
2006年9月1日以前に着工された建物では、アスベスト(石綿)含有建材が使用されている可能性があり、
解体・改修工事に際して、元請業者は法令に沿った対応を求められます。
クラウド型システム「アスベストONE」では、事前調査結果報告書・作業計画書・現場掲示用看板などを自動作成でき、法令対応の抜け漏れを防ぎつつ作業を効率化。
アスベスト分析依頼にも対応し、進捗確認や履歴管理もスマートに行えます。
「まず何をすべきか分からない」という場合でも、経験豊富な専門スタッフが一からご案内します。
👇お問い合わせはこちらから👇
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)


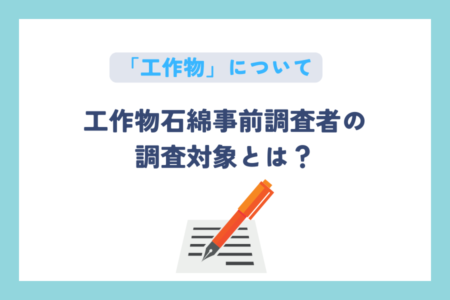












_20250214.png)
