アスベスト解体の正しい進め方|元請業者が押さえるべき事前準備と作業手順
- 最終更新日:

アスベストを含む建築物の解体工事では、適切な手順と厳格な管理が求められます。
微細なアスベスト繊維は空気中に浮遊しやすく、吸引することで深刻な健康被害を引き起こすため、作業者のみならず、周辺環境への影響も考慮した対策が不可欠です。
元請業者には、事前調査の実施をはじめ、 法令に基づく届出、作業計画の策定、安全管理体制の構築など、多岐にわたる責任が課されています。
本記事では、アスベスト解体工事を安全かつ適正に進めるための基本知識と、具体的な作業フローについて解説します。
アスベスト解体時に発生する石綿粉じんの飛散リスクと健康被害
アスベスト(石綿)を含む建築物の解体作業では、建材の破砕や除去に伴って、微細な石綿粉じんが空気中に飛散するリスクが非常に高くなります。
アスベスト繊維は肉眼では確認できないほど細かく、一度吸引すると体内に長期間蓄積されやすい性質を持ちます。
これにより、作業者だけでなく周辺住民にも健康被害を及ぼす可能性があるため、適切な飛散防止対策が不可欠です。
アスベスト繊維を吸引することで発症する代表的な疾患には、石綿肺(じん肺の一種)、中皮腫、肺がんなどがあります。
いずれも発症までに一般的には10年以上の潜伏期間を経るため、ばく露時の記録や作業環境の管理が将来的な労災補償や医療支援の根拠となります。
このような背景から、アスベスト解体工事では、調査結果の保存(3年間)や工事計画の届出、作業状況の記録保存(最大40年間)などが法令で定められています 。
アスベストの危険性は広く知られるようになりましたが、解体現場では依然としてリスクが高く、特に適切な隔離措置や湿潤化措置が不十分な場合、目に見えない粉じんが広範囲に飛散するおそれがあります。
そのため、元請業者や現場管理者は、作業区域を明確に区分けし、第三者の立ち入りを厳格に制限する必要があります。
また、作業員には国家検定に合格した防じんマスク(RS2以上やRL2以上)や保護衣・作業衣等の着用が求められ、定期的な健康診断の実施や作業記録の保管も重要な義務となります。
さらに、周囲への影響を最小限に抑えるため、必要に応じて現場ごとに大気汚染防止法、石綿障害予防規則および自治体条例に基づく届出を行い、自治体や周辺住民への事前周知も含めたリスクコミュニケーションが不可欠です。
アスベスト対策は単なる現場管理にとどまらず、長期的な健康被害を未然に防ぐ社会的責任の一環であることを、すべての関係者が理解する必要があります。
アスベスト解体工事前に必要な調査・分析と書類準備
アスベストを含む建材の有無を確認するためには、建物の改修・解体工事前に「事前調査」を実施することが法令で義務付けられています。
この調査は、建物内外の建材について目視確認や資料調査を行い、必要に応じてサンプリングし、専門機関による定性分析を経て石綿含有の有無を判定します。
調査結果に基づき、作業計画を策定する必要があります。
また、一定規模以上の工事においては、石綿事前調査の結果を電子システムにより報告する義務があります(2022年4月以降)。
報告には、調査方法、対象建材、使用箇所、石綿含有の有無などの詳細な情報が求められ、報告漏れや虚偽記載には罰則が科されるため、正確な記録と確認作業が必要です。
このほかにも、作業計画書、労働者名簿等の各種書類の作成・保存等についても対応しなければなりません。
調査および書類作成は、元請業者が中心となって進め、下請業者や専門調査機関との連携が必要不可欠です。
不備がある場合には、工事の停止命令や行政指導の対象となるため、慎重かつ確実な手続きが求められます。
さらに、事前調査を実施する際には、調査を担当する者が「石綿含有建材調査者講習」を修了していることが条件とされており、調査の信頼性と精度を担保する仕組みが整えられています。
建築図面や過去の工事履歴が残っている場合は、それらの資料も活用し、調査対象建材の特定と優先順位の判断に役立てます。
実際の現場では、設計図に記載されていない建材や施工変更部分が存在することも少なくないため、現地での目視確認による照合が不可欠です。
目視調査を実施しても、メーカーや型番による製品の特定ができない場合には、分析調査の併用も有効です。
この一連のプロセスは、工事の円滑な進行だけでなく、作業員や地域住民の安全確保、法令遵守の徹底にも直結しており、元請業者にとっては非常に重要な責務といえるでしょう。
アスベスト解体に関連する法令と必要な届出とは
アスベスト解体工事には、複数の関連法令が適用されます。
主な法令には「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」「大気汚染防止法」などがあり、それぞれに対応した届出や措置が求められます。
労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則では、石綿作業主任者の配置、作業計画の策定、作業員への特別教育の実施などが義務付けられています。
また、大気汚染防止法においては、飛散防止措置の実施が定められるほか、レベル1(吹付け材)やレベル2(耐火被覆材・断熱材・保温材)の建材を取り扱う作業に際しては、
都道府県知事に対して「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。これらの届出は、作業開始の14日前までに行うことが原則です。
さらに、地方自治体によっては、独自の条例や報告義務が定められていることもあり、現場所在地の法令確認が重要です。
全体として、アスベスト解体工事は厳格な法的管理のもとで行われるべき業務であるため、届出の遅延や不備があると法令違反となり、元請業者に重大な責任が生じます。
アスベスト解体手順(隔離・湿潤化・撤去・清掃)の具体的ステップ
アスベスト解体作業は、石綿粉じんの飛散を最小限に抑えるために、厳格な作業手順を踏んで行う必要があります。
一般的な手順は以下の通りです。
- 作業区域の隔離:解体を行う区域は、外部と遮断されるよう養生し、出入口には警告標識やエアロック等を設置します。(補足)レベル3の建材を取り扱う作業においては負圧隔離養生は原則不要です。
- 湿潤化:解体対象のアスベスト含有建材には、作業前・作業中に水分を含ませる処理を施し、粉じんの発生を抑えます。(補足)湿潤化が困難な場合は、除じん性能付き電動工具の使用や隔離養生などの代替措置が必要です 。
- 除去作業:手作業または低振動工具を用いて建材を撤去し、飛散が最小限になるよう慎重に扱います。使用済みの保護具や工具も現場内で管理されます。
- 清掃・廃棄物処理:撤去後は区域内をHEPAフィルター付き真空掃除機や湿式清掃で洗浄し、石綿含有廃棄物は密閉梱包のうえ、法定の処分場で処理します。
以上の各工程には、専門知識を持つ作業者と監督者の配置が求められます。
安全管理体制の不備は、健康被害や近隣からの苦情に直結するため、段取りと教育の徹底が不可欠です。
アスベスト解体工事費用の構成と見積り取得時の注意点
アスベスト解体にかかる費用は、通常の解体工事と比較して高額になる傾向があります。
主な費用項目には、事前調査費用、届出・報告関連の書類作成費、作業員の人件費(特別教育や作業主任者の配置費用を含む)、
保護具や資機材の調達費、養生や隔離措置の施工費、廃棄物の収集・運搬・処分費用などがあります。
※工事にかかる費用や必要な措置は、石綿のレベル(レベル1:吹付材、レベル2:保温材・断熱材・耐火被覆材、レベル3:成形板等)によって大きく異なります。
見積を取得する際には、これらの項目が明確に記載されているかを確認するとともに、調査結果や工事規模に応じた適正価格が反映されているかを精査することが重要です。
過度に安価な見積を出す業者の場合、安全管理を十分に行っていないケースもあるため、実績や資格保持者の有無も含めて慎重に業者を選定する必要があります。
また、工事の規模によっては行政への補助制度や自治体の助成金が利用できる場合もあるため、事前に情報収集を行うことで、費用負担を抑える工夫も可能です。
アスベスト対応を分析から書類作成・電子報告まで、クラウドで効率化
従来のアスベスト対応業務は、FAXやメールによる分析依頼、煩雑な書類作成、進捗の確認や管理、報告手続きと、手間もミスも起きやすい作業の連続でした。
「効率化を図りたいが、法令対応のために結局アナログ作業が多い」──そんな悩みを抱える現場担当者も少なくありません。
「アスベストONE」は、こうした業務をまとめてクラウド上で効率化するサービスです。
フォームに沿って情報を入力するだけで、分析依頼が完了し、受け入れ状況や進捗もリアルタイムで確認可能。
書類作成も自動化され、作業計画書・報告書・現場掲示用の看板までワンクリックで出力できます。
出力される書類はすべて法令に準拠したフォーマットのため、記載内容の整合性や記入漏れにも安心。
GビズIDを連携した電子報告にも対応しており、従来のような手入力作業を省くことで、時間と手間を大幅に削減できます。
スマホやタブレットからも利用できるので、現場や出張先からもスムーズに操作が可能。
現場・事務所・協力会社間で常に最新の情報を共有できるため、手戻りや重複作業を減らし、スピード感のある業務体制を実現します。
まずは無料の個別相談で、現場の課題やお悩みをお聞かせください。




_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
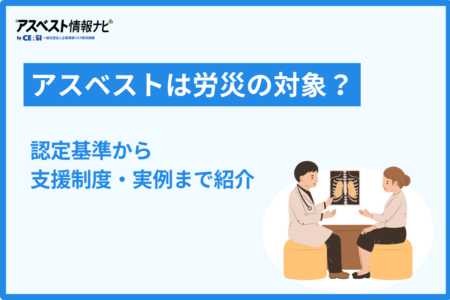
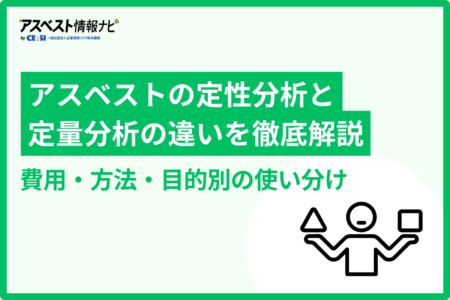
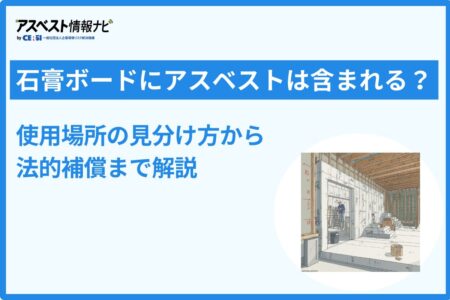











_20250214.png)
