壁面の見た目だけでは判断できない?アスベスト判定のポイントと分析の重要性
- 最終更新日:

アスベストを含む建材は、外観だけで判別することが極めて難しいという特徴があります。
たとえ壁や天井の仕上げが新しく見えても、内部や下地にアスベスト含有建材が使われている可能性は否定できません。
特に、1970年代から1990年代にかけて建てられた建物では、そのリスクが高まります。
目視での自己判断は誤認につながり、解体や改修時のアスベスト飛散リスクを高め、法令違反や健康被害に直結する恐れもあります。
本記事では、科学的根拠に基づいた、製品ラベル・建物の築年(着工年代)・分析結果などをもとに正しく判定するためのポイントを解説します。
正確な判断のためには、専門機関による分析の重要性を理解することが求められます。
見た目からアスベストを見分けることができるのか?建材の特徴と限界
建材にアスベストが使用されているか否かに関して、外観だけでは判別が極めて困難です。
たとえば、Pタイルやケイ酸カルシウム板、スレート、成形板などは、アスベストの有無にかかわらず見た目が類似しており、
素人はもちろん、建築の専門家であっても視覚的に区別することは非常に困難です。
また、経年劣化やリフォームによる表面改修が行われている場合、建材の外観が当初の状態とは大きく変化していることがあり、判別はさらに困難になります。
そのため、壁面や天井、床を「見た目」だけで判断することは極めて危険な行為です。
さらに、建材には複数の素材が層状に重なっているものも多く、表層のみでは判別できない場合があります。
たとえば、天井ボードの表面が新建材であっても、内部に古いアスベスト含有層が残っていることがあります。
また、塗装やクロス仕上げが施されている場合、基材の構造が隠れてしまい表層だけではアスベストの含有を見抜くことが難しく、誤認につながる結果となります。
平成18年(2006年)以降、重量比で0.1%を超えてアスベストを含有する建材・資材の輸入、製造、利用等が禁止されました。
しかしながら、その規制は段階的に実施されたものであり、2004年以前は重量比1%未満であれば「アスベストなし」と判断されていました。
一部の建材には「アスベスト非含有」「無石綿」と明示されている場合がありますが、これは製造時点での基準による記載であるため、
現在の基準(0.1重量%)では「アスベスト含有」と判断しなければならないケースもあります。
したがって、現場での目視調査において、設計図書や外観のみでアスベストの含有有無を判断することはできません。
アスベストの含有がないことの正確な判定には、製品の特定およびメーカーによるアスベスト非含有の証明、もしくは専門機関による分析調査が不可欠です。
見た目に頼った判断は、誤認による飛散リスクや法令違反、作業員や居住者の健康被害を脅かすリスクをはらんでおり、根拠ある対応と安全性の確保が求められます。
アスベスト判別が難しい理由と分析機関による分析の重要性
アスベスト含有建材の判定が難しい理由のひとつは、アスベストが非常に微細な繊維で、建材中の含有量が多くの場合1%未満であるためです。
加えて、同じ形状・色・質感の建材でも製造時期や工場、メーカーによってアスベストの使用の有無が異なることも珍しくありません。
このような状況下では、見た目や感触だけでなく、製造年や建築年の情報を照合した上で、専門の分析機関による定性・定量分析を行うことが唯一確実な判定方法です。
分析には主に偏光顕微鏡(PLM)やX線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)などの手法が用いられ、これらによりアスベストの有無や種類、含有率を明確に判定することができます。
分析結果は、建材除去や改修工事の計画だけでなく、アスベスト事前調査結果報告(電子報告)においても必要不可欠です。
アスベストがよく使われていた建材の種類と施工年代
アスベストが多く使用されていた建材には、吹付け材、耐火被覆材・保温材・断熱材、Pタイル、スレート、ケイ酸カルシウム板、ロックウール吸音板、石膏ボードなどがあります。
これらは1970年代から1990年代にかけて多用されており、特に1980年代前半まで建設現場で広く採用されていました。
2004年にはアスベスト含有率1%超の建材の製造・使用が禁止され、2006年9月以降には0.1%超の製品が原則禁止となったため、それ以前の建物にはアスベスト含有建材が存在する可能性が高いと考えられます。
そのため、1980〜2000年代初頭に施工された建物を中心として、既存の建物に対して解体・改修等工事を実施する場合には、事前調査による確認が必須です。
製造ラベル・刻印の有無によるアスベスト判定のポイント
一部の建材には、製造メーカーや製品名、JIS番号などのラベルや刻印が残されていることがあります。
これらの情報が確認できれば、国土交通省や建材メーカーが公開しているアスベスト含有建材のリストと照合することで、ある程度のリスク評価が可能です。
たとえば、ケイ酸カルシウム板に「チヨダウーテ」や「ニチアス」といったメーカー名や、特定の製品記号がある場合には、該当製品の仕様を調査することによって、アスベストの有無を推定する材料になります。
しかし、すべての建材にラベルが残っているわけではなく、また製品名が判明してもロットや製造年の違いにより含有状況が異なる可能性があるため、あくまでも補足的な確認手段として捉えるべきです。
最終的な判断は、あくまでも専門機関による分析結果に基づく必要があります。
安易な自己判断によって生じるリスクと分析の必要性
見た目や印象による安易な自己判断は、アスベストの見落としを招く重大なリスクがあります。
石綿事前調査を行わず、適切な飛散防止対策を実施せずにアスベスト含有建材を解体・破砕した場合、周囲にアスベストを含む粉じんが飛散し、作業者や居住者、近隣住民に深刻な健康被害を及ぼす可能性があります。
また、現在は一定規模以上*の工事においてアスベスト事前調査結果の報告が義務化されており、調査を行わずに解体や改修を行うことは、法令違反として行政指導や罰則の対象となります。
元請業者や建物管理者にとっては、事前に適切な書面調査・目視調査および分析調査を実施し、アスベストの有無を把握することが、リスクマネジメントの観点からも非常に重要です。
*延べ床面積80㎡以上の解体工事や請負金額100万円以上の改修工事
アスベストの含有判定には、知識や経験に基づく判断だけでなく、確実な分析データが求められます。
見た目に惑わされず、専門機関の力を借りて正確な状況を把握することが、法令順守や安全確保の観点で必要不可欠といえるでしょう。
書類作成のミス防止・業務負担の軽減に。アスベストONEがワンストップでサポート
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)対応業務をクラウドでワンストップで支援するサービスです。
煩雑な書類作成や進捗管理を効率化し、法令遵守の負担も軽減します。
項目に沿って情報を入力するだけで、事前調査報告書や作業計画書、現場掲示用看板PDF、作業方法説明書、作業記録、作業報告書まで、自動で作成できます。
法令準拠のフォーマットで出力されるため、記載漏れや誤記のリスクを抑え、書類作成にかかる時間も削減できます。
また、GビズIDに対応しており、CSV形式でデータを出力してアップロードするだけで電子報告が可能。
従来のように工事情報を手入力する必要がなく、負担やミスを防げます。
工事情報はクラウド上で一元管理され、社内・下請け業者・協力会社とスムーズに情報を共有します。
進捗状況もリアルタイムで見える化されるので、手戻りの少ないスピーディーな業務が可能です。
EMSでは、初めての方にもわかりやすく、現場の実情にあった運用方法を無料相談でご提案しています。
業務の正確性と効率化を両立したい方に、アスベストONEは最適です。ぜひご活用ください。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
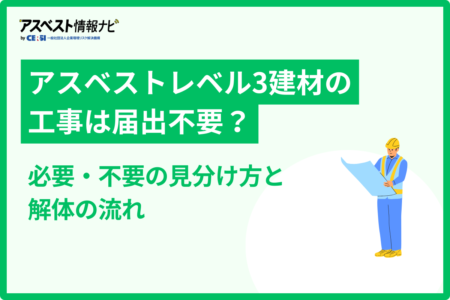

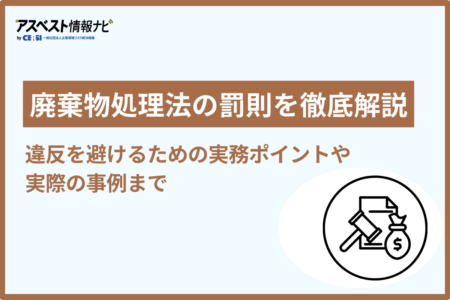











_20250214.png)
