アスベスト含有天井材の危険性と見分け方とは?使用建材の種類から安全な除去方法まで解説
- 最終更新日:

発注者(施主/工事の注文者)が建物のリフォームや解体工事を検討する際に、特に注意しなければならないのが天井部分に使用されたアスベストの存在です。
アスベストはかつて、優れた耐火性・断熱性・遮音性を持つ素材として、オフィスビルや学校、工場、集合住宅の天井材等に幅広く使用されてきました。
しかし、アスベスト繊維を吸い込むことで、肺がんや中皮腫、石綿肺といった深刻な健康被害を引き起こすことが分かり、2006年以降は使用が全面禁止されています。
特に2006年9月1日以前に着工された建物については、天井にアスベスト含有建材が使用されている可能性が高く、事前調査を行う際には天井仕上げ材・下地材・吹付け材などの部位に注意が必要です。
発注者として正しい知識を持ち、使用建材の種類や判別の難しさ、そして除去方法を理解することが、適切かつ安全な対応につながります。
本記事では、アスベスト含有天井材の危険性や具体的な建材の種類、判別方法、安全な除去手順までを体系的に解説します。
天井に存在するアスベストの危険について
発注者が最も注意すべき点は、天井に使われたアスベスト含有建材が、劣化や改修工事によって飛散しやすい状態になっているかどうかです。
天井のアスベストは、建物利用中には目に見えない形で存在していることが多く、落下や破損、穿孔(せんこう)といった外力が加わることで、空気中に微細なアスベスト繊維が放出されるリスクがあります。
特に、吹付けアスベストや保温材が使用されている場合は、飛散性が高く、吸引による健康被害のリスクが非常に大きくなります。
これらの被害は長期潜伏性があり、吸引から数十年後に症状が現れることも少なくありません。
しかも、アスベスト関連疾患には治療法が限られており、発症すると回復が困難であるという現実があります。
発注者が天井の改修や解体を検討する段階で、事前調査を怠ると、作業従事者だけでなく建物内にいるすべての人々の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
アスベストが見つかった場合は、放置せず速やかに専門家による対応を行うことが必要です。
天井に使われるアスベスト建材の種類
発注者が確認すべき天井のアスベスト含有建材には、いくつか代表的な種類があります。
最も広く知られているのが、吹付けアスベスト(吹付け石綿)です。
これは鉄骨や天井裏に直接吹き付けられていたもので、特に1970年代から1980年代前半にかけて頻繁に使用されていました。
この吹付け材は非常に飛散性が高く、現在では除去が最優先とされる建材の一つです。
次に多く見られるのが、ロックウール吸音板や化粧石膏ボードなどの天井仕上げ材です。
これらの建材にはアスベストが1〜3%程度含有されているものがあり、外観だけでの判別は困難です。
また、天井の断熱材や保温材、下地材に混入しているケースもあります。
特に目視できない部分に使用されている場合は、事前調査においてサンプルを採取し、分析調査を行う必要があります。
天井裏に設置されたダクトや配管に巻かれていた保温材にもアスベストが含まれていた例があり、そうした場合は天井を解体することで初めて露出するため、見落としがちです。
施工年代や建材名だけでは判断できないため、過去の施工図面や仕様書の確認も有効です。
アスベストの判別方法とよく間違える建材
発注者がアスベスト含有建材を判断する際、外観や施工時期だけで推測するのは危険です。
実際には、アスベスト非含有のロックウールやパーライト板、無石綿の石膏ボードと非常によく似た見た目の建材も存在しており、経験の浅い調査者では区別がつかないことが多くあります。
建材表面の凹凸や色、模様などの外見的特徴のみで判断することはできません。
現在では、建材の破片や粉じんを採取し、JIS(日本産業規格)に準拠したX線回折法(XRD)や偏光顕微鏡法(PLM)などの技術を用いて行われます。
定性分析によってアスベストの含有有無が、定量分析によって0.1重量%以上のアスベストを含むかどうかが判定されます。
分析依頼は、分析機関または専門事業者を通じて行う必要があり、発注者自身での目視確認およびアスベスト含有の判断は行うことができません。
また2022年4月以降、元請け業者に対し、石綿事前調査結果報告義務に対応した正確な書類の提出が求められるようになりました。
発注者としては、分析結果に基づいた正しい判断と対応が欠かせません。
天井に使われるアスベストは見極めが重要な理由
天井のアスベストは、目に見えない危険であるため、誤った判断や放置が重大な問題を引き起こすおそれがあります。
発注者が「問題ないだろう」と判断して工事を進めた場合、作業従事者が飛散したアスベストを吸引し、数十年後に健康被害が発覚するという事態が起こり得ます。
実際に、吹付けアスベストが残存したままの状態で天井を撤去し、飛散事故につながった例も報告されています。
また、アスベストの有無を曖昧にしたまま工事を発注した場合、元請業者や下請業者との間でトラブルになるケースもあります。
大前提として、工事着工前に事前調査を実施し、アスベスト含有有無を判断することが必要不可欠ですが、万が一、着工後にアスベストが発見された場合には、工事を一時中断して届出や計画書の提出が必要となり、工程や予算に大きな影響を及ぼします。
発注者が初動で正確な事前調査が可能な状態を確保し、情報を開示することが、工事全体の安全と信頼性を確保するうえで重要です。
また、適切な分析結果をもとにアスベスト除去の必要性が明らかになった場合には、法令に準拠した手続きと対応が求められます。
アスベストが飛散する前に、的確な判断を下すことが、発注者のリスクを最小限に抑える鍵となります。
天井に使われるアスベストを除去する方法
発注者がアスベスト含有天井材の除去を検討する場合、最も重要なのは、法令に準拠した方法で、資格を持つ専門業者に作業を依頼することです。
除去方法には「除去工法」「封じ込め工法」「囲い込み工法」があり、天井材に使われているアスベストの種類や状態に応じて適切な工法が選択されます。
最も確実に再発リスクを低減できるのは除去工法で、アスベストを完全に撤去し、飛散の危険性を根本から排除します。
吹付けアスベストの除去作業の際には、着工14日前までに労働基準監督署への届出が必要です。
現場では集じん・排気装置の設置や養生による飛散防止措置を講じたうえで、アスベストを湿潤化しながら除去を行います。
除去後には廃棄物の適正処理も必須であり、吹付けアスベストは「特別管理産業廃棄物」として、許可を有する処理業者に回収・処分を委託することが義務づけられています。
発注者としては、専門業者の実績や対応範囲、届出・書類作成の支援体制などを総合的に判断し、信頼できる業者を選定することが重要です。
なお、補助金や助成制度を活用すれば、一定の条件下で除去費用の一部を軽減できるケースもあるため、工事前に各自治体の制度を確認することをおすすめします。
アスベスト対応を分析から書類作成・電子報告まで、クラウドで効率化
従来のアスベスト対応業務は、FAXやメールによる分析依頼、煩雑な書類作成、進捗の確認や管理、報告手続きと、手間もミスも起きやすい作業の連続でした。
「効率化を図りたいが、法令対応のために結局アナログ作業が多い」──そんな悩みを抱える現場担当者も少なくありません。
「アスベストONE」は、こうした業務をまとめてクラウド上で効率化するサービスです。
フォームに沿って情報を入力するだけで、分析依頼が完了し、受け入れ状況や進捗もリアルタイムで確認可能。
書類作成も自動化され、作業計画書・報告書・現場掲示用の看板までワンクリックで出力できます。
出力される書類はすべて法令に準拠したフォーマットのため、記載内容の整合性や記入漏れにも安心。
GビズIDを連携した電子報告にも対応しており、従来のような手入力作業を省くことで、時間と手間を大幅に削減できます。
スマホやタブレットからも利用できるので、現場や出張先からもスムーズに操作が可能。
現場・事務所・協力会社間で常に最新の情報を共有できるため、手戻りや重複作業を減らし、スピード感のある業務体制を実現します。
まずは無料の個別相談で、現場の課題やお悩みをお聞かせください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)


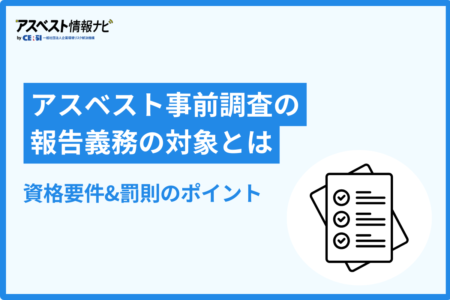












_20250214.png)
