アスベストの年代別の判定ガイド|規制の歴史から含有製品一覧と判定方法まで解説
- 最終更新日:

発注者(施主/工事の注文者)が解体や改修工事を行う際、最初に確認しなければならないのがアスベストの使用有無です。
アスベスト(石綿)は、1970年代から1990年代にかけて建築資材として幅広く使用されてきましたが、人体への深刻な健康影響が判明し、2006年以降は全面的に使用が禁止されました。
特に2006年9月1日以前に建てられた建築物では、アスベスト含有建材が使用されている可能性が高く、より注意が必要です。
アスベストが含まれている可能性を判定するうえで、建築物の着工年代は非常に重要な判断材料となります。
どの年代にどのような規制が行われてきたのかを正しく理解することで、含有の可能性や調査の必要性を見極めることが可能になります。
本記事では、アスベスト規制の歴史、含有建材の種類、年代別の判定目安などを発注者の視点から整理し、工事前に知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
アスベスト規制までの歴史や背景
アスベストが広く建築資材として使用されたのは、1950代から1980年代後半にかけてです。
安価で耐火性・断熱性に優れていたため、天井材、内装材、外装材、保温材、床材などさまざまな用途に用いられてきました。
しかし、1970年代以降、海外でアスベストによる健康被害が報告され、日本国内でも規制の必要性が認識され始めました。
最初の本格的な規制は1975年で、特定化学物質等障害予防規則により、アスベストを5重量%を超えて含有する吹付けアスベストの使用が原則禁止されました。
さらに1995年には、この基準が1重量%超に引き下げられ、同時にアモサイト(茶石綿)およびクロシドライト(青石綿)といった特に有害性の高い種類のアスベストの輸入・製造・使用が禁止されました。
2004年にはアスベストを含む摩擦材や接着剤、建材などの製品が禁止対象に追加され、2006年にはついに0.1重量%超のアスベストを含むすべての製品の製造・輸入・使用が全面禁止されました。
これらの規制は段階的に強化されてきたため、建材の種類や製造時期によっては、法的には使用可能だった期間が存在します。
そのため、建物の施工年代だけでアスベストの有無を断定することはできず、あくまで調査の要否を見極める一つの判断材料として活用する必要があります。
2006年より前に建てられた建物はアスベスト含有の可能性がある
厚生労働省のガイドラインでは、2006年9月1日より前に着工された建物については、アスベスト含有建材が使用されている可能性があるとしています。
これは、労働安全衛生法施行令の改正により、同日以降、0.1重量%超のアスベストを含む建材が完全に製造・使用禁止となったことが根拠です。
つまり、それ以前に流通していた建材にはアスベストが含まれている可能性が否定できず、解体・改修時には事前調査が義務づけられています。
たとえ建物の完成が2006年9月以降であっても、着工がそれ以前であれば、使用された建材が規制前の在庫品である可能性があります。
発注者は、設計図書や建築確認申請などの工事記録をもとに着工日を確認し、石綿有無の可能性を判断する必要があります。
こうした規制の変遷も、発注者が正確に把握しておくべき重要な情報です。
アスベストが使用されている可能性がある場所とは?
アスベストは建物内外のさまざまな部位に使用されていたため、事前調査を行う際には、特定の場所に限定せず、建物全体を対象として網羅的に確認する必要があります。
とくに使用例が多かったのは、天井仕上げ材、内外装材、床材、間仕切り、柱の耐火被覆材、ボード類、保温材、電気絶縁材、配管の巻付け材などです。
製品としては、吹付けアスベスト、石綿含有ロックウール、化粧石膏ボード、スレート板、石綿セメント板、バーミキュライトパネル、ビニル床タイル、塗料や接着剤などに使用されていました。
外壁材としてよく見られるスレート波板や、倉庫や工場の天井に用いられていたロックウール吸音板なども、アスベスト含有製品として代表的です。
また、直接目に見えない天井裏や壁内の保温材や断熱材に混入している場合もあり、建物を部分的に解体した際に初めて発見されることもあります。
事前調査の際は、「見えている場所だけ」を確認して安心せず、可能性のある部位をあらかじめ洗い出すことが求められます。
アスベスト含有製品の年代別一覧
アスベスト含有建材の代表的な製品を、施工年代ごとに分類した一覧を以下に示します(※製品によっては製造時期と施工時期にずれがあるため、あくまで目安です)。
1970年代以前
吹付けアスベスト(ロックウール、バーミキュライト)、アスベスト含有モルタル、保温材(配管・ダクト)
1980年代
石綿含有セメント板、スレート波板、ロックウール吸音板、化粧石膏ボード、バーミキュライトパネル
1990年代
ビニル床タイル、Pタイル、塗料、接着剤など、内装仕上げ材としての使用
2000年代(2004年以前)
アスベスト含有の粘着材、接着剤、耐火パテ、配管カバーなど
2004年以降
石綿の使用制限が大幅に拡大され、含有製品は激減。ただし、一部の在庫品や既存建材が残存していたケースもあり、調査が必要。
この一覧をもとに、発注者は建物の建設時期と照らし合わせながら、どの建材が使用されている可能性があるのかを把握しておくことが重要です。
年代でアスベスト含有を判定する方法
発注者が年代を手がかりにアスベスト含有の有無を判断する場合、まず確認すべきは建物の着工日です。
着工日が2006年9月1日より前である場合は、建材にアスベストが含まれている可能性が高く、とくに注意が必要です。
設計図面や施工報告書、建築確認申請書などを確認することで、着工日や建材の使用時期を推定することが可能です。
ただし、前述のとおり施工年代と建材の製造・出荷時期にはずれが生じるため、「2007年完成=安全」とは限りません。
とくに在庫建材や転用建材が使用された場合をはじめ、アスベストが含まれていた事例も報告されています。
したがって、年代情報は「判断の手がかり」として活用するものであり、最終的にはJIS規格に基づく分析結果による確認が唯一確実なアスベスト含有判断手順と言えます。
2023年度には全国で76万4145件の事前調査結果報告が提出されており、東京都だけでも12万4782件にのぼりました。
こうしたデータからも、年代による判定だけでは対応できない現場が依然として多いことが分かります。
発注者としても、建物の新築着工日を確認したうえで、必要に応じて分析機関に検体を提出し、定性・定量分析による裏付けを取ることが望まれます。
アスベストONEで書類作成と進捗管理をワンストップで効率化
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)に関する書類作成と進捗管理をワンストップで支援するクラウドサービスです。
必要な情報を項目に沿って入力すれば、事前調査報告書・作業計画書・現場掲示用の看板PDFなどを自動生成。
同じ内容を何度も入力する必要がないため、書類作成の手間を大幅に削減できます。
また、GビズIDによる電子報告にも対応しており、CSV形式で出力したデータをアップロードするだけで、煩雑な手入力作業を省き、スムーズな報告が可能です。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく、下請け業者や協力会社との情報共有もスムーズに行えます。
全体の工程を明確に把握しながら、法令に沿った対応を効率的に進めることができます。
初めての方でも安心して運用いただけるよう、アスベスト対応に関するご相談も随時承っております。
EMSでは、現場に即した実務の視点から、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内し、皆さまの業務負担の軽減と、確実な法令対応をしっかりとサポートいたします。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
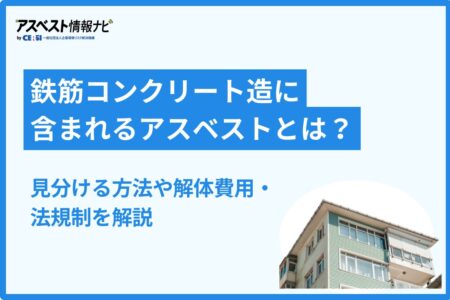
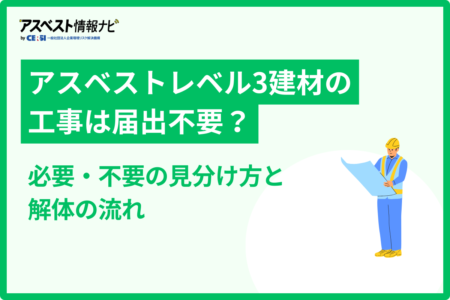
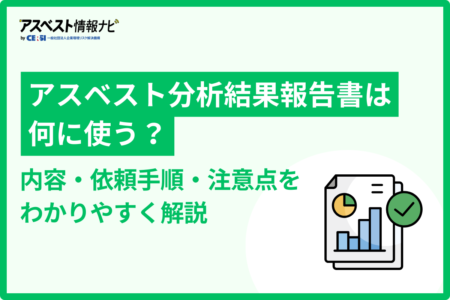











_20250214.png)
