アスベスト分析の必要性・費用相場&調査手順を分かりやすくご紹介
- 最終更新日:

本コラムでは、アスベスト分析調査の基本から実務で押さえるべき判断ポイントまでを整理します。
・アスベスト分析調査の全体像と、書面調査・現地調査・分析調査の役割
・定性分析と定量分析の違い、使い分けの考え方
・分析費用の相場と、依頼時に確認すべき実務上の注意点
「調査は必要なのか」「どこまで分析すべきか」「費用は妥当か」といった現場で迷いやすいポイントを、実務目線で解説します。
アスベスト分析調査の概要
アスベスト分析調査とは、建築物の内外装材や配管などにアスベストが含まれているかどうかを調べるための専門的な調査です。
アスベストはかつて耐火性や断熱性に優れていることから、ビルや住宅、工場などさまざまな建築物に建材として使用されてきました。
しかし、アスベストの繊維を吸い込むことで肺がんや中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こす可能性があることが明らかになり、現在では使用が原則禁止されています。
そのため、解体やリフォームの際には、事前に建材にアスベストが含まれているかどうかを調査することが法令で義務づけられています。
アスベスト調査には大きく分けて「書面調査」「現地(目視)調査」「試料採取・分析調査」の3段階があります。
まず、建物の設計図や建材の仕様書などを確認する「書面調査」を行い、使用の可能性がある部位を推定します。
次に現地で建材の状態や材質を目視で確認し、アスベスト含有が疑われる箇所から試料を採取します。
採取した試料を専門機関で分析し、アスベストの有無や含有率を科学的に判定します。
この事前調査は建築物の安全性確保や労働者・居住者の健康を守るうえで非常に重要です。
特に解体・改修工事を予定している場合には、事前調査を怠ると法令違反となり、工事の中断や罰則を受けるリスクがあります。
アスベスト調査は単なる義務ではなく、安全で適正な建築環境を維持するための第一歩といえるでしょう。
アスベスト分析が必要な理由
アスベスト分析が必要とされる最大の理由は、人体への深刻な健康被害を未然に防ぐためです。
アスベストは一度吸い込むと肺に蓄積され、20〜50年という長い潜伏期間を経て中皮腫や肺がん、石綿肺といった重篤な病気を引き起こすことがあります。
そのため、過去にアスベストが使用された建築物を解体・改修する際には、作業者や周辺住民の安全を確保するために事前調査が欠かせません。
また、日本では2006年にアスベストの使用が原則全面禁止となったものの、それ以前に建てられた多くの建物にはアスベスト含有建材が使用されている可能性があります。
特に1970〜1990年代に建設されたビルや工場、学校、病院などでは、吹付け材や断熱材、仕上げ材として広く使われていました。
これらの建材は外見からはアスベスト含有の有無を判断することができず、専門機関による分析調査が必要になります。
さらに、リフォームや解体工事を行う際には、「事前調査義務」が法令で定められており、これに違反すると罰則の対象となります。
石綿障害予防規則や労働安全衛生法などにより、既存の建材に損傷を及ぼす工事では事前にアスベストの有無を確認し、必要に応じて飛散防止措置を講じなければなりません。
このように、アスベスト事前調査は法的な義務であると同時に、建物の利用者や工事関係者の健康を守るための重要なステップです。
安全な環境づくりの第一歩として、適切なタイミングで確実に実施することが求められます。
定性分析と定量分析の違い
アスベストの分析には「定性分析」と「定量分析」の2種類があり、それぞれ目的や手法が異なります。
まず「定性分析」とは、建材などの試料にアスベストが含まれているかどうか、つまり有無を判断するための分析調査です。
主に偏光顕微鏡や位相差顕微鏡などを用いて、繊維の形状や光の反射性、屈折率などからアスベストの種類を識別します。
一般的に、建材から採取したサンプルを分析し、「アスベストが含まれているか否か」を判断する場面では、この定性分析が行われます。
一方、「定量分析」は、試料中に含まれるアスベストの量を測定するための分析です。
具体的には、「その建材にアスベストが全体重量の何%含まれているか」といった数値を出します。
定量分析では主にX線回折装置や走査型電子顕微鏡などが使用され、より高精度かつ詳細な分析が求められます。
アスベスト含有率が重量比で0.1%を超えるかどうかは、法令上の規制対象か否かを判断する基準となるため、定量分析の結果が非常に重要となります。
定性分析は主に初期調査やスクリーニングに使われ、迅速かつ比較的低コストで実施できますが、法的判断が必要な場面や、飛散防止対策の計画を立てる際には、より正確な定量分析が求められることがあります。
そのため、調査の目的や必要な精度に応じて、どちらの分析を実施すべきかを慎重に判断する必要があります。
アスベスト分析の費用相場
アスベスト分析にかかる費用は、調査の内容や対象建物の規模、採取する試料数、分析方法などによって異なりますが、一般的な相場を知っておくことで、適正な見積もりを判断しやすくなります。
基本的に、アスベスト分析は「現地調査」と「分析作業」の2つの工程に分かれており、それぞれに費用が発生します。
まず、現地調査も委託する場合、その費用は、1回あたり3万円〜10万円程度が相場です。
この中には、建材の目視調査やサンプル採取、交通費などが含まれる場合が多く、建物が広かったり、試料の採取箇所が多い場合は、それに応じて追加費用が発生することがあります。
次に、採取したサンプルを分析する費用ですが、「定性分析」の場合は1検体あたり1万円〜2万円程度が一般的です。
これに対し、より詳細な「定量分析」を行う場合は、1検体あたり3万円〜5万円程度かかることがあります。
たとえば、2箇所からサンプルを採取して定性分析を行う場合、全体で5万円前後が目安になります。
また、緊急対応などを依頼する場合は、追加費用が発生することもあります。
たとえば、即日分析を希望する場合には、オプション料金として1万〜3万円程度が加算されることがあります。
このように、アスベスト分析の総費用は、内容によって大きく変動しますが、簡易な調査であれば5万〜10万円程度、より厳密な定量分析や複数検体の調査になると10万〜20万円以上になることもあります。
正確な見積もりを取る際には、調査会社に具体的な範囲や目的を伝えることが重要です。
アスベスト分析の具体的な依頼方法
アスベスト分析を依頼する際は、いくつかの手順と注意点を押さえておくことが大切です。
まず最初に行うべきなのは、信頼できる分析機関や調査会社を選ぶことです。
厚生労働省や各自治体のホームページには、石綿分析が可能な登録機関や認定業者のリストが掲載されている場合があるので、それらを参考に選ぶと安心です。
依頼の第一歩は、見積もりの取得です。
多くの業者は電話やウェブサイト、メールフォームから問い合わせが可能で、建物の所在地・築年数・工事の内容(解体・改修など)・調査したい範囲を伝えると、概算の見積もりを出してくれます。
この段階で、調査方法(定性・定量分析のどちらか)や必要な検体数、報告書の形式なども確認しておくとスムーズです。
見積もりに納得したら、正式に調査の依頼を行い、現地調査の日程を調整します。
現地調査では、専門スタッフが建材の種類や状態を目視で確認し、必要な箇所からサンプルを採取します。
この作業は、飛散を防ぐための安全対策を取りながら慎重に行われます。
採取された試料は、検査機関に送られて分析され、数日〜1週間程度で結果が報告されます。
報告書には、アスベストの有無や含有率、使用されていたアスベストの種類などが記載されており、工事計画や法的手続きに必要な資料として活用できます。
また、アスベスト分析の結果によっては、除去工事や飛散防止措置が必要になる場合もあります。
そのため、工事を協力会社に委託する場合には分析だけでなく、必要に応じて除去や対策工事も一貫して対応できる業者に依頼するのもひとつの方法です。
このように、アスベスト分析は事前準備から報告書の受領まで複数のステップがありますが、信頼できる業者と綿密に連携することで、安全かつ円滑に進めることができます。
アスベスト分析から書類作成・電子報告まで、クラウドで完結。現場の業務効率化を今すぐ実感
建設現場のアスベスト対応業務は、分析の手配、進捗確認、法令に沿った書類作成、行政への報告など、煩雑で時間のかかる業務が多く、担当者の大きな負担となっています。
こうした業務に追われて、「本来の作業に集中できない」「毎回の対応が手探りで大変」…そんなお悩みはありませんか?
アスベストONEは、分析依頼から書類作成、電子報告までをクラウド上で一元管理できるサービスです。
必要な情報をクラウド上のフォームに入力するだけで、分析依頼が完了し、進捗もリアルタイムで確認可能。
作業計画書や報告書、現場掲示用の看板PDFなども自動生成され、書類作成にかかる工数を大幅に削減できます。
出力される書類は法令に準拠したフォーマットなので、記載漏れや誤記のリスクも軽減。
さらに、GビズIDに対応した電子報告も可能で、手入力による煩雑な作業から解放されます。
また、クラウド上でのデータ共有により、現場・事務所・協力会社の間で常に最新の情報が確認できるので、手戻りや無駄な確認作業も減り、スピーディーで確実な業務連携が実現します。
アスベスト対応における事務負担の軽減、コスト削減、法令対応の徹底を、ぜひアスベストONEでご体感ください。
まずは無料の個別相談で、貴社の現場に合わせた最適な活用方法をご提案いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)


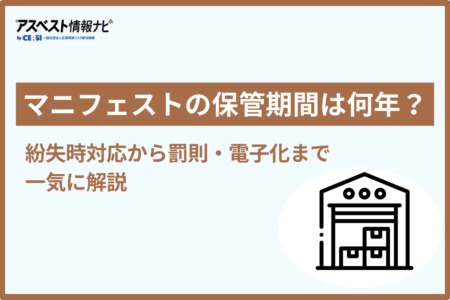
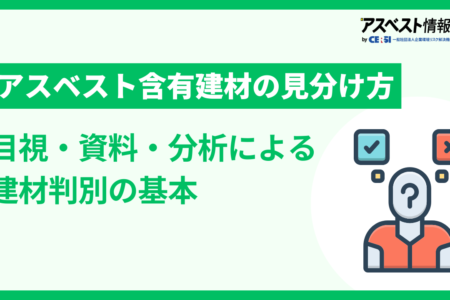











_20250214.png)
