【2025年版】アスベストに関する法令と法改正の歴史|リスク対応と留意点を解説
- 最終更新日:

発注者(施主/工事の注文者)が建物の解体や改修を計画する際、必ず考慮すべき項目の一つが「アスベストに関する法令対応」です。
アスベスト(石綿)は、過去に断熱性・耐火性・防音性に優れた建材として重宝されましたが、
その後、吸引によって重篤な健康被害を引き起こすことが明らかとなり、社会的・法的な規制が強化されてきました。
2006年の全面禁止をはじめ、法改正は段階的かつ継続的に実施され、現在では調査・報告・施工・廃棄まで、厳格なルールが定められています。
特に、2022年の法改正以降は、解体や改修工事に先立つアスベスト事前調査および結果の電子報告が義務化されるなど、発注者にも明確な対応責任が求められるようになりました。
制度は年々見直されており、2025年現在も関係省庁の通達・告示に基づいて最新の運用が続いています。
本記事では、アスベストによるリスクの概要から、関連法令の体系、法改正の流れ、よくある疑問、そして今後の留意点までを、発注者の視点から丁寧に解説します。
アスベストによるリスクの増加
アスベストは、極めて細かい繊維状の鉱物であり、吸入によって肺の中に蓄積される性質を持ちます。
その結果、発症までに数十年を要する中皮腫や肺がん、石綿肺などの重大な健康被害を引き起こすとされています。
発注者が着目すべきは、工事による建材の破損や穿孔(せんこう)などを通じて、目に見えないアスベスト繊維が空気中に飛散する可能性がある点です。
とくに1970年代から1990年代にかけて建築された物件には、吹付け材、保温材、天井材、外壁材などとしてアスベストが多用されていたため、解体・改修の際には十分な注意が求められます。
こうしたリスクの存在が、現在のアスベスト規制の根拠となっており、調査の実施から報告、除去工事、廃棄物処理に至るまで、多段階での法令対応が義務づけられています。
近年は、既存建物の老朽化に伴い改修・解体工事の需要が増していることから、アスベスト飛散事故のリスクも相対的に増加しており、施工業者のみならず、発注者にも一層の法令遵守が求められています。
アスベストに関する法令
アスベストに関連する法令は複数存在し、主に次の4本柱で構成されています。
1つ目は「労働安全衛生法」であり、事前遵調査や作業計画の策定、作業基準、報告義務、使用制限などの基準が定められています。
とくに石綿障害予防規則(通称:石綿則)は、作業従事者の保護を目的とした技術的・組織的対策を義務づける法令で、発注者としても間接的に遵守責任を負う場面が多くあります。
2つ目は「大気汚染防止法」です。
アスベストは飛散性の有害物質として規定されており、解体・改修工事時の作業基準、周辺環境への配慮、工事前の届出義務などが定められています。
3つ目は「廃棄物処理法」です。
アスベスト除去後の建材は「石綿含有産業廃棄物」や「廃石綿等(特別管理産業廃棄物)」に該当し、専門の運搬・処分業者によって適正に処理されなければなりません。
4つ目は「建築基準法」等の関連法令で、建材の使用制限や告示などが反映されています。
発注者は、これらの法令群を横断的に理解し、元請業者や調査会社との連携の中で、適切な対応をとることが求められます。
アスベストに関わる法改正の流れ
アスベスト規制の強化は段階的に行われてきました。
代表的な法改正の経緯は次のとおりです。
1975年、特定化学物質等障害予防規則により、アスベストを5重量%超含有する吹付けアスベストの使用が原則禁止されました。
1995年にはこの基準が1重量%超に引き下げられ、さらにアモサイト(茶石綿)およびクロシドライト(青石綿)の輸入・製造・使用が禁止されました。
2004年にはアスベスト含有建材や摩擦材、接着剤などの輸入・使用が原則禁止となり、2006年にはついに0.1重量%超の石綿を含むすべての製品が全面的に禁止されました。
これにより、2006年9月1日以前に着工された建物は、現在でもアスベスト含有建材を含む可能性があるとして事前調査を進める必要があります。
そして2022年4月には、労働安全衛生法の改正により、解体・改修工事を行う際の事前調査結果の電子報告が義務づけられ、報告対象の拡大や有資格者による調査の明文化が行われました。
さらに2026年1月には、資格要件の追加など、実務レベルでの管理体制の充実が求められています。
アスベストの法改正に関するよくある質問
Q:2007年に建てられた建物にもアスベスト調査が必要か?
A:2006年9月1日以降に着工された建物でも事前調査は必要です。
しかし、2006年9月1日以降はアスベスト含有建材の使用が禁止されているため、基本的に「新築着工日が2006年9月1日以降であること」を設計図書等から確認する書面調査でアスベスト無の判断を行います。
ただし、在庫品や転用建材が使われていた可能性もあるため、場合によっては現地調査を行うことが推奨されます。
Q:報告義務の対象となる工事は何ですか?
A:原則として、解体工事(解体する床面積80㎡以上)、改修工事(請負金額100万円(税込)以上)、一定規模以上の保守工事が対象です。
それ以下の工事であっても、規模の要件のみをもって調査義務が免除されることはありません。
Q:無資格者による調査は認められますか?
A:2006年9月1日以降に着工した物件で、かつ書面調査を行う場合に限り、資格を有していない方でも調査は可能です。
ただし、2023年10月以降は、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの資格を有する者によって実施しなければならず、無資格者による調査は無効とみなされ、再調査が必要となります。
Q:調査結果は誰が報告するのですか?
A:原則として工事を実施する元請業者が電子報告を行います。
調査結果の確認や分析報告の手配を含め、発注者も適正な工事管理のために協力体制をとる必要があります。
今後必要となるアスベスト対応と留意点
発注者が今後アスベスト対応を進めるうえで重要となるのは、各種対応への理解と、全面的な協力です。
調査・報告・施工・廃棄までを一貫して管理できる体制を持つ業者を選定し、発注者も必要なアスベスト対応がなされているか把握できる状況が望ましいといえます。
調査への協力として、設計図面や仕様書の提供、アスベスト分析調査の費用負担、最新制度の把握が欠かせません。
近年では、工事の元請業者向けのクラウド型のアスベスト対応支援サービスも整備されており、
こうしたシステムを利用すれば、報告書作成、電子報告、現場掲示物の出力、進捗管理などが一元化され、法令対応がより確実かつ効率的に進められます。
このようなシステムを導入している点も、信頼性の高い業者を見極める判断材料となるでしょう。
今後、報告制度のさらなる厳格化、罰則の明確化、電子化の義務拡大が予想されており、早期からの情報収集と体制整備が肝要です。
法改正の方向性を見据え、適切な措置を講じることで、発注者自身のリスクを低減し、工事の安全性・信頼性を確保することが可能になります。
アスベストONEで分析依頼から書類作成・電子報告までを効率化
「アスベストONE」は、クラウド上での分析依頼から進捗状況の確認、書類作成までをワンストップでサポートするクラウドサービスです。
システムに沿って入力するだけで、法令に準拠した作業計画書や報告書を自動で生成できるため、これまで手間のかかっていた書類作成業務を大幅に効率化できます。
さらに、CSV形式で一括出力したデータはGビズIDと連携して電子報告が可能なため、複雑な行政手続きもスムーズに対応できます。
また、書類の作成状況や進捗がクラウド上で“見える化”されており、現場・事務所・協力会社の間で常に最新情報を共有・確認できます。
これにより、手戻りや確認作業を最小限に抑えた、無駄のない連携が可能になります。
EMSでは、アスベスト対応に関する無料の個別相談も承っております。
専門スタッフが現場の状況を丁寧にヒアリングし、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内いたします。
まずは分析からはじめて、手間とコストを削減できる実感をぜひお確かめください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)



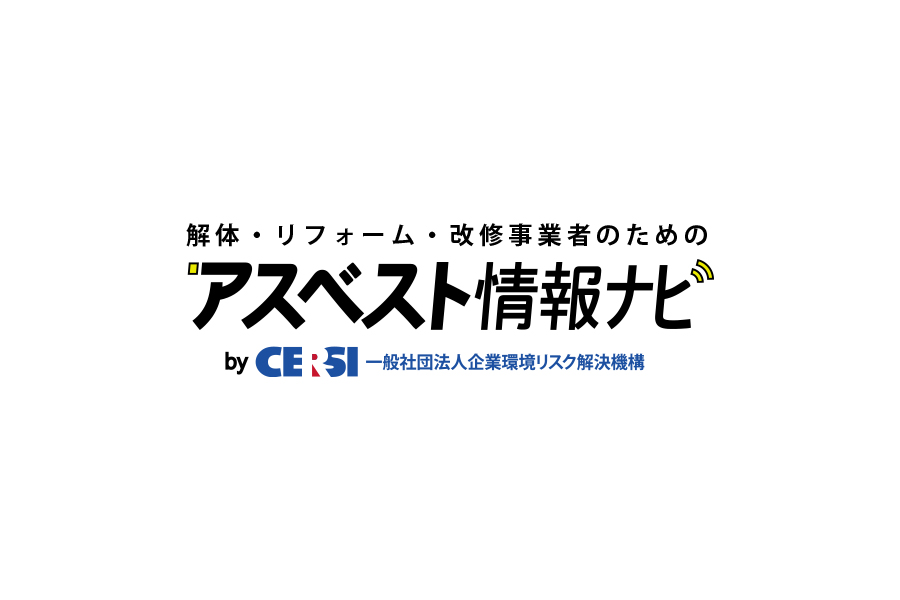











_20250214.png)
