壁紙にアスベストは含まれている?見分け方と健康リスク・処分法を完全ガイド
- 最終更新日:

壁紙に使用される建材にアスベストが含まれている可能性は、過去の建築物において現実的な懸念事項となっています。
特に1970年代から1990年代初頭までの日本においては、建築物全体にわたってアスベスト含有建材が多用されていました。
アスベストは耐熱性や断音性に優れており、接着剤や下地材の成分として壁紙にも用いられていた可能性があります。
2006年9月以降は法令でアスベストの使用が全面的に禁止されているため、それ以降に新築着工された建物に関してはリスクは低いとされますが、
2006年8月までに新築着工された建物については小規模な建築物であってもアスベスト含有の壁紙を使用している可能性を否定できません。
そのため、古い建物のリフォームや解体時には、壁紙にアスベストが含まれていないかを慎重に確認する必要があります。
この記事では、壁紙にアスベストが含まれるケースや健康リスク、その見分け方、安全な処分手順、さらに法令で定められた対応までを正確に解説していきます。
壁紙に含まれるアスベストとは?
アスベストとは、天然に産出される非常に細い繊維状の鉱物で、耐熱性・断熱性・耐薬品性等に優れていることから、かつては建築資材や工業製品に広く使用されていました。
とりわけ、1970年代から1990年代前半にかけては、建築現場においてアスベストが含まれるさまざまな材料が頻繁に使用されていたため、現在でも古い建物では注意が必要です。
アスベストを含有する壁紙は、主に不燃クロス、アスベスト壁紙、無機質壁紙等と呼ばれ、建築基準法の内装制限により「不燃材料」を要求される避難階段、通路、エレベータホール等の壁面、天井などに使用されており、
住宅では、台所やユーティリティ等の火気使用室に使用されている頻度が高いとされています。
さらに、壁紙を貼り付ける際に用いられた接着剤や、下地を調整するために使用されたパテ、さらには壁そのものの下地材にアスベストが含まれている場合があります。
建築物の新築着工時期やリフォーム歴の把握は、アスベスト含有の可能性を判断する重要な手がかりになります。
2006年9月以降、アスベストを全面的に禁止する改正労働安全衛生法が施行されたため、それ以前に新築着工された建物については、アスベスト含有建材が使用されている可能性が否定できません。
こうした背景から、壁紙を含む内装工事や解体工事を行う場合は、2006年9月以前に建てられた建物であれば、たとえ小規模な作業であっても、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査が必須となります。
なお、2006年9月以降に新築着工された建物であっても、書面等により着工時期を確認する事前調査は必須となるので注意が必要です。
安全なリフォームや除去作業を進めるためにも、壁紙にまつわるアスベストリスクの理解と、的確な判断が求められます。
アスベスト含有壁紙の危険性と健康リスク
アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物であり、空気中に浮遊しやすい性質を持っています。
そのため、一度建材から飛散してしまうと、人間が呼吸することで肺に取り込まれやすくなります。
特にアスベスト繊維は、人体の排出機能では自然に体外に除去されにくく、長期間にわたって体内にとどまり続けるという特徴があります。
これが健康リスクの大きな要因となっており、注意が必要とされています。
アスベストに関連する代表的な健康被害としては、中皮腫、肺がん、そしてアスベスト肺(じん肺の一種)などが挙げられます。
これらの疾患はすぐに発症するものではなく、10年から40年という非常に長い潜伏期間を経て症状が現れることが多いため、気付いたときにはすでに進行しているケースが少なくありません。
したがって、アスベストへの曝露がたとえ一時的であったとしても、将来的な健康への影響が否定できないことから、初期段階での対応が極めて重要となります。
壁紙に関しては、その表面が劣化していたり、物理的に破損していたりすることで、繊維が飛散するリスクが高まります。
また、リフォームや改修に伴って壁紙を剥がす作業を行う際にも、アスベスト含有の壁紙や、接着剤、下地材が損傷することで微細なアスベスト繊維が空中に舞い上がる危険性があります。
これらの飛散した繊維は非常に軽く、目に見えるほどの大きさではないため、知らないうちに作業者や住人が吸い込んでしまう可能性があります。
さらに、アスベストを含んでいるかどうかは、壁紙や下地の見た目だけでは完全に判断はできません。
表面に凹凸がある、裏面が灰色であるなどの特徴があると言われていますが、必ずしもすべてに共通するものではなく、当てはまったからアスベストを含有している、あるいは当てはまらなかったから含有していない、ということは断定できません。
実際、外観上はまったく異常がないように見える場合であっても、調査を行った結果、アスベストが含有されていたという例も珍しくありません。
このような背景からも、建築年や使用された建材に不安がある場合には、むやみに壁紙を剥がしたり、穴を開けたりすることは避けた方が賢明です。
安全な作業を行うためには、事前に有資格者による現地調査を実施することが必要不可欠です。
具体的には、「建築物石綿含有建材調査者」といった専門資格を有する者による調査が義務付けられており、製品情報からのアスベスト含有の判断や、サンプル採取から分析機関での検査までを通じて、アスベストの有無や含有量を確認することができます。
調査結果に基づいて適切な除去や対策を講じることで、作業者や居住者の健康リスクを最小限に抑えることが可能となります。
壁紙のアスベストを見分ける方法とポイント
壁紙自体の外観だけでは、アスベストの含有有無を判断することはできません。
見分けるにはまず、建築年や使用された建材の種類、施工時期の情報を基に、専門家によるヒアリングと現地調査を行います。
型番等による製品情報との照合などでアスベスト含有の有無が明確にならない場合には、石綿含有があるとみなして工事を行うか、検体を採取し分析機関での分析調査を行う必要があります。
なお、建築物の所有者等が自分で剥がして確認するのはアスベスト含有の危険を伴うため、必ず建築物石綿含有建材調査者のような有資格者に依頼しましょう。
アスベスト含有壁紙の安全な処分手順
アスベストが含まれていることが確認された場合、法令に基づいた適切な手順で処分する必要があります。
まず、作業前に「石綿作業主任者」を配置し、作業員に対して石綿特別教育を実施します。
次に、周囲への飛散を防ぐために養生を行い、防じんマスクを着用の上、湿潤化処理を施しながら壁紙と下地材を慎重に除去します。
除去後は、アスベストを含む廃棄物として専用袋に密閉し、石綿含有産業廃棄物として指定処分場へ運搬・処理します。
作業前後の看板掲示や作業記録の作成・保存も法的に求められています。
これらの対応を怠ると、元請業者や所有者が行政指導や罰則の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
アスベストを含む建物の解体・リフォームに関する法規制
2020年の大幅な法改正により、アスベストに関する解体・改修工事の規制は強化され、元請業者や関係業者に対する義務が格段に広がりました。
特に2022年4月からは、大気汚染防止法および労働安全衛生法に基づいて、すべての建築物(非鉄骨造・木造含む)に対して解体面積80㎡以上の解体工事、または請負金額100万円(税込)以上のリフォーム工事を行う場合には、
アスベスト事前調査の調査結果報告を電子システム(石綿事前調査結果報告システム)を通じて行うことが法律で定められています。
さらに、事前調査結果報告の対象とならない請負金額100万円未満の小規模な住宅リフォームや一戸建ての部分改修であっても、事前調査結果記録をはじめとする各種帳票を作成・保存しなければなりません。
例えば、クロス(壁紙)や床材、天井仕上げなどの仕上げ材にアスベスト含有がある、またはあるとみなして工事する場合、撤去作業は「レベル3石綿作業」に該当し、
石綿作業主任者の選任や防じんマスクの着用、飛散防止のための湿潤化や養生措置、作業計画書の作成、作業記録の作成と保存など様々な対応が求められます。
元請業者は、建築物石綿含有建材調査者など有資格者による調査の実施を確認したうえで、報告・届出の正確な実行を担う責任があります。
また、作業時には現場に法定様式の看板を掲示し、施工後も事前調査結果記録・作業記録・作業完了報告書などの帳票類を3年間(一部は40年間)保存することが義務付けられています。
これらの対応を怠った場合には、労働基準監督署や地方自治体からの行政指導や罰則の対象となることがあります。
このように、建物の解体に伴うアスベスト対応は、もはや一部の専門業者だけの問題ではなく、一般住宅や小規模工事を請け負うすべての施工業者・元請業者にとって重要な法的責任となっているのです。
現場ごとの建材構成や築年数に応じて、的確に調査・報告・養生を行うことが、トラブル回避と安全確保の両立につながります。
アスベストONEで書類作成・進捗管理を効率化し、法令遵守も安心サポート
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)対応業務に必要な書類作成と進捗管理を、クラウド上でワンストップで支援するサービスです。
これまで手間と時間のかかっていた作業を効率化し、現場との情報共有までを一括でカバーします。
入力項目に沿って進めるだけで、事前調査報告書や作業計画書、現場掲示用の看板PDFなどを自動で生成。
法令に準拠したフォーマットで出力されるため、記載漏れやミスを防ぎます。
さらに、GビズIDに対応した電子報告にも対応しており、出力したCSVデータを一括アップロードするだけで行政への報告が完了するため、手入力による負担やミスを軽減できます。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく下請け業者や協力会社とも最新情報を簡単に共有可能です。
進捗状況や全体工程も見える化され、手戻りの少ないスムーズな業務連携を実現します。
EMSでは、現場の状況や課題をヒアリングしたうえで、最適な運用方法を無料相談でご案内しています。
業務負担を軽減し、確実に法令対応できる体制をぜひアスベストONEで実現してください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)


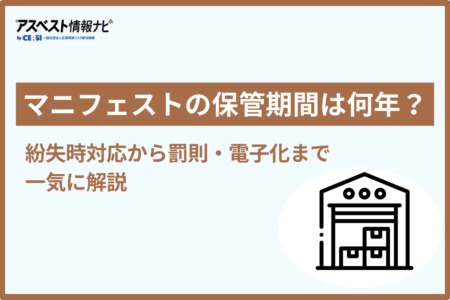
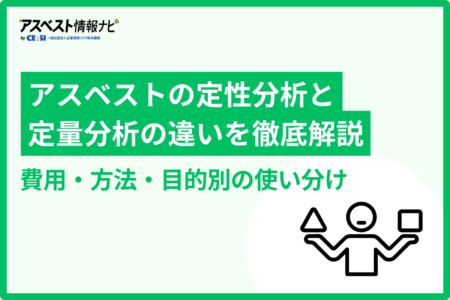











_20250214.png)
