ロックウールの危険性とは?アスベストとの違い&含有リスクと見分け方を解説
- 最終更新日:

建築物の断熱や防音に使用される素材にはさまざまな種類があり、その中でもロックウールは広く流通している無機繊維の一種です。
しかし、発注者(施主/工事の注文者)がリフォームや解体工事を計画する際、「ロックウールはアスベストなのか?」「取り扱いに危険はないのか?」といった不安を感じることも少なくありません。
これは、ロックウールの見た目や用途がアスベストとよく似ており、特に築年数の経過した建物においては、混同されやすいためです。
ロックウールとアスベストは全く異なる性質を持つ素材であり、その危険性のレベルにも大きな違いがあります。
ただし、過去には一部のロックウール製品にアスベストが混入していたケースも報告されており、建築年代や使用状況によっては、注意が必要となる場面も存在します。
本記事では、ロックウールの基本情報から、アスベストとの違い、危険性の有無、見分け方、含有リスクの有無まで、正確な情報に基づいて詳しく解説します。
ロックウールとは
ロックウールとは、玄武岩等の天然岩石や鉄炉スラグなどを高温で溶解し、人工的に繊維状に加工した無機鉱物繊維です。
日本産業規格では、一例として「人造鉱物繊維断熱材(JIS A 9504)」に分類されており、主に断熱性・防音性・耐火性を目的として建物の壁・天井・床などに使用されています。
ロックウールの繊維径は数ミクロン程度で、毛羽立ちが少なく、軽量で扱いやすいことが特徴です。
吸音材や空調ダクト周囲の断熱材、ALCパネルの裏打ち材などにも使用されており、住宅だけでなくビルや公共施設でも幅広く採用されています。
1990年代以降に製造されたロックウール製品は、製品の安全性が確保されています。
したがって、ロックウール=危険という認識は誤解に基づくものであり、事実とは異なります。
ロックウールとアスベストとの違い
ロックウールとアスベストは、いずれも細かな繊維状の素材であり、外観や施工目的が似ているため混同されることがありますが、成分構成や性質には明確な違いがあります。
アスベストは天然の鉱物繊維で、繊維が非常に細く、空気中に浮遊しやすいという特徴があります。
そのため、吸入による健康被害が問題視され、肺線維症(石綿肺)、中皮腫、肺がんなどの原因となることが科学的に明らかにされています。
この危険性から、日本国内では、アスベストの製造・使用は2006年をもって全面的に禁止されました。
一方、ロックウールは人工的に製造された鉱物繊維であり、生体溶解性が高く、人体内に吸入された場合でも比較的速やかに排出されるとされています。
日本国内では、ロックウールは「石綿」に該当せず、アスベストによる法規制の対象外となっています。
また、ロックウールの構造は不均一であり、アスベストに比べて耐久性が低く、施工中に発じんする量も抑えられているため、使用時における粉じんばく露のリスクは限定的です。
ロックウールの危険性・安全性は?
発注者が懸念する「ロックウールの危険性」については、現在流通している製品においては、基本的に安全性が確保されているとされています。
ロックウールは、国際がん研究機関(IARC)により「ヒトに対する発がん性が分類されない(グループ3)」とされており、適切に取り扱えば健康被害の懸念は極めて低いと考えられています。
ただし、施工時や撤去時に繊維が飛散することはあり得るため、作業従事者が適切な保護具(防じんマスク、手袋、保護衣)を装着することは望ましいとされます。
また、施工現場における粉じんの発生を抑えるためには、湿潤化や局所排気装置の活用が推奨されています。
過去には、ロックウールやグラスウールといった無機繊維が皮膚刺激を起こすことも報告されていましたが、現在では製品表面のコーティング技術や繊維径の調整により、こうした問題も大幅に低減されています。
したがって、発注者がロックウールの使用を理由に過度な不安を抱える必要はありません。
ロックウールとアスベストの見分け方とは
外観が似ているロックウールとアスベストを見た目だけで判断することは困難です。
発注者が施工現場でこれらを見分けるには、以下のような点に注目する必要があります。
製品ラベルや記録図書の確認
製造元、製品名、施工時期などが記載されていれば、該当製品がアスベスト含有か否かを判断する手がかりになります。
繊維の太さと色味
アスベストは繊維が非常に細く、均一で、白・灰色・青色などの色調があるのに対し、ロックウールは繊維が太く、見た目がバサバサしており、灰白色や黄褐色に近いことが多いです。
使用部位
ロックウールは断熱や吸音を目的として壁・床・天井に使用されることが多く、吹付けアスベストとは使用範囲が異なる傾向にあります。
最終的な判定には、やはり建材調査者による成分分析が必要です。
JIS A 1481に準拠した分析法(偏光顕微鏡法、X線回折法など)を通じて、アスベストの含有の有無が科学的に明らかになります。
発注者としては、疑いがある時点で専門調査を依頼することが、安全かつ確実な対処法です。
ロックウールにアスベストが含有されている可能性はある?
原則として、ロックウール製品自体にアスベストが意図的に混入されていることはありません。
アスベスト含有建材データベース(国土交通省・経済産業省)では、以下の建材が「アスベスト非含有建材」として記載があります。
- ロックウール(吹込み用繊維質断熱材)JIS A 9523
- ロックウール(人造鉱物繊維保温材)JIS A9504
- 住宅用ロックウール断熱材[マット](住宅用人造鉱物繊維断熱材)JIS A 9521
- 浮き床用ロックウール緩衝材(ロックウールボード)
- 屋上緑化植物栽培用ロックウール(ロックウールベッドポット等)
ただし、1970〜1980年代に製造された一部の断熱材・吸音材の中には、アスベストとロックウールを併用していた製品も存在したとされており、古い建築物においては注意が必要です。
特に以下のような条件に該当する場合は、含有の可能性を否定しきれません。
- 1980年代以前に建築された建物
- 屋根裏や壁内部に古い断熱材が残っている
- 記録図書や施工記録が残っておらず、使用建材が不明
このような場合、発注者が自主判断で「ロックウール=安全」と決めつけてしまうのではなく、専門家の調査を経て対応方針を検討することが求められます。
特に解体や大規模改修を予定している場合、アスベスト含有の有無を事前に確認し、必要であれば法令に基づく報告や適切な除去作業を行う必要があります。
アスベストONEで分析依頼から書類作成・電子報告までを効率化
「アスベストONE」は、クラウド上での分析依頼から進捗状況の確認、書類作成までをワンストップでサポートするクラウドサービスです。
システムに沿って入力するだけで、法令に準拠した作業計画書や報告書を自動で生成できるため、これまで手間のかかっていた書類作成業務を大幅に効率化できます。
さらに、CSV形式で一括出力したデータはGビズIDと連携して電子報告が可能なため、複雑な行政手続きもスムーズに対応できます。
また、書類の作成状況や進捗がクラウド上で“見える化”されており、現場・事務所・協力会社の間で常に最新情報を共有・確認できます。
これにより、手戻りや確認作業を最小限に抑えた、無駄のない連携が可能になります。
EMSでは、アスベスト対応に関する無料の個別相談も承っております。
専門スタッフが現場の状況を丁寧にヒアリングし、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内いたします。
まずは分析からはじめて、手間とコストを削減できる実感をぜひお確かめください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)



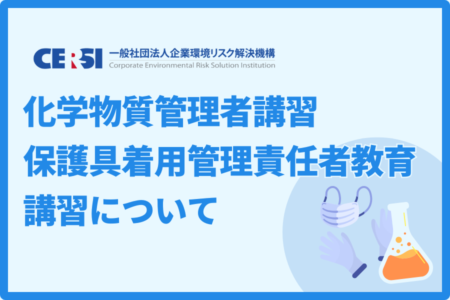











_20250214.png)
