天井材のアスベストの見分け方とは?対処法や除去対策費用までわかりやすく解説
- 最終更新日:

本コラムでは、天井材に含まれるアスベストのリスクと、見分け・対応の実務ポイントを整理します。 ・天井材にアスベストが使用されてきた背景と、年代・建材別の注意点 ・目視確認や書面調査で判断できる範囲と、分析調査が必要になるケース ・アスベストが判明した場合の法令対応、工法選定、費用の考え方 天井という飛散リスクが高まりやすい部位だからこそ押さえるべき実務を、
元請・発注者視点で解説します。
天井材に含まれるアスベストとは?
天井に使われる建材にアスベストが含まれている可能性は、健康リスクを考えるうえで非常に重要です。
アスベストとは高い耐熱性や強度を持つ鉱物繊維であり、かつては天井材としても多く使用されていました。
しかし、建材の経年劣化によりアスベスト繊維が飛散し人体に吸引されると、中皮腫や肺がんなど深刻な疾患を引き起こす可能性があるため、慎重な確認が欠かせません。
さらに、天井材にアスベストが含まれているか判断するためには「視覚的な識別ポイント」に注目することが有効です。
例えば、白っぽく繊維質な質感を持ち、ひび割れや表面の毛羽立ち等が確認できる場合には、アスベスト含有の可能性が高まります。
建材の色や繊維の見た目は非常に特徴的であるため、初期判断の手がかりとして役立ちます。
加えて、「年代別の使用状況」を把握することも重要です。
1970年代から1980年代にかけてはアスベスト含有建材の使用が一般的であり、1990年代以降には徐々に禁止が進みました。
2006年に日本で石綿の使用が全面禁止となったため、それ以前に建てられた建物については、アスベストを含んでいる可能性を考慮する必要があります。
実際、目視調査や築年数等の情報だけでは石綿含有を確定できない場合が多いため、誤判断によるリスクを避けるには「専門機関や専門業者による調査・分析」が不可欠です。
例えば、サンプルを採取して顕微鏡で分析するなど、科学的な検証によって初めてアスベストの有無を正確に把握できます。
天井に使用されるアスベストの見分け方を解説
天井に使用されているアスベストの見分け方は、健康被害を未然に防ぐためにも非常に重要な知識です。
まず、建物の着工年代を確認することが肝心です。
2006年9月以前に新築着工された建物には、アスベスト含有建材が使用されている可能性があるため、特に注意が必要です。
天井材には、吹付けアスベストが使用されている場合があります。
経年劣化により、天井から石綿の繊維が垂れ下がっている状態が見受けられます。
これは、アスベスト含有の兆候であり、除去等の作業を行うと飛散のリスクも高まります。
また、設計図書や仕様書から建材名を確認する方法も有効です。
建材名やメーカーの型番をもとに、国土交通省などが運営する「石綿含有建材データベース」で照合することで、アスベスト含有の有無を推測できます。
しかしながら、これらの方法はあくまで推定にとどまる点に留意が必要です。
最も確実な判断方法は、天井材等のアスベスト含有の可能性がある建材の試料を採取し、専門機関による分析調査を行うことです。
偏光顕微鏡法(PLM)や電子顕微鏡法(TEM)などの分析手法を用いることでアスベストの含有有無が明確になります。
アスベストと似ている素材
アスベスト含有の吹付け材と外見が酷似している建材として、ロックウールやグラスウールなどが挙げられます。
ロックウールは玄武岩や高炉スラグなどを1500度~1600度の高温で溶かし繊維状に加工した素材であり、断熱性・吸音性に優れているため建築現場で広く使用されてきました。
グラスウールはガラスを素材とし、同様に繊維状に加工された建材で、こちらも断熱や吸音用途に多用されています。
両者とも人工素材であり、人体への有害性は低いとされています。
それに対して、アスベスト(石綿)は天然由来の鉱物繊維で、耐熱性・断熱性に優れていたことから、かつては多用されたものの、
微細な繊維が肺に入り込むことで中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を引き起こすことが明らかになっています。
これらの建材を外見だけで区別するのは極めて困難ですが、次のようなポイントを参考にすると判断の手がかりになります。
指で触って確認する方法
ロックウールやグラスウールは指でこすると細かな粉状に崩れやすい性質がある一方で、アスベストは繊維状のまま残りやすい性質があり粉状にはなりにくい、という違いがあります。
ただし、この方法は飛散リスクを伴います。
お酢(酸)に浸して確認する方法
ロックウールは酸に弱くお酢をかけると溶ける性質がありますが、アスベストは酸に強くお酢をかけても溶けない、という違いがあります。
ただし、これはあくまで簡易的な確認方法に過ぎません。
現在のアスベスト含有の判断基準は「0.1重量%超」というシビアな数値が設定されており、仮にお酢で溶けることが確認できたとしても、実際にはアスベストを基準値以上含有している可能性が否定できないためです。
顕微鏡による繊維観察
アスベストは非常に細かい繊維(直径0.02〜0.35 μm)であり、ロックウール(直径3〜10 μm)、グラスウール(直径4〜9 μm)とは肉眼では見分けられない程度の大きさの違いがあります。
よって、分析調査により繊維の太さから専門的に判断するのが最も確実な手法です。
建材のサンプリングを行い、顕微鏡や偏光顕微鏡(PLM)、電子顕微鏡(TEM)を用いた分析調査を行うことで、繊維がアスベストであるか否かを判断できます。
天井にアスベストが見つかった場合の対処法
天井材などにアスベストが使用されているかどうかは、建築物石綿含有建材調査者の資格保有者が事前調査を実施し判断することが義務づけられています。
また、その調査結果に応じて、適切な施工方法を選択する必要があります。
飛散の恐れが高い吹付け材(レベル1建材)や断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2建材)が判明した場合には、原則として「除去工法(リムーバル工法)」の選択が求められます。
条件に応じて「封じ込め工法」や「囲い込み工法」が許容されるケースもありますが、これらはいずれも一時的な対策に過ぎず、最終的にはアスベスト含有建材を除去しなければなりません。
さらに、作業自体にも厳格な法規制が存在します。
大気汚染防止法および石綿障害予防規則(労働安全衛生法)により、作業時には飛散防止措置として隔離養生、湿潤化、呼吸用保護具の着用、負圧除じん装置の使用(レベル1・2建材の場合)等が義務付けられているほか、作業の記録や報告が必要です。
加えて、アスベストを含む廃材は、廃棄物処理法に基づいて、適切な梱包・表示・処理ルートの確保といった手続きが不可欠です。
アスベスト対策にかかる費用
天井材へのアスベスト含有が確認された場合には、その後の対策にかかる費用も重要です。
ここでは、アスベスト対策にかかる費用の目安とその内訳についてわかりやすく解説します。
まず、アスベスト対策にかかる費用の大部分は「調査費用」「除去工事費用」「廃棄処理費用」の3つに分けられます。
調査費用は、建物の規模や調査範囲によって異なりますが、数万円から十数万円程度が一般的です。
特に天井材のように広範囲にアスベストが使われている場合は、精密な分析が必要になるため調査費が高くなる傾向があります。
最もコストがかかるのは除去工事です。
アスベスト除去工事は特殊な装備や厳重な飛散防止対策が求められるため、アスベストの除去を伴わない解体工事よりも高額になります。
たとえば、アスベスト含有吹付け材の除去を行う場合は、除去にかかる費用は1平方メートルあたり1万円から3万円が目安ですが、建物の状況によってはさらに高くなることもあります。
また、除去後の廃棄物処理費用も無視できません。
アスベスト含有廃棄物は「廃石綿等(特別管理産業廃棄物)」「石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)」に区分されます。
取り扱うことができる許可業者が限定されていること、処理段階での飛散防止対策が必要となることから、収集運搬や処分にも高額な費用がかかります。
これらの費用は除去工事費と合わせて、総額の30〜40%を占めるケースも少なくありません。
費用を抑えるためには、自治体の助成制度の活用も併せて検討いただくと良いでしょう。
補助金だけで全額を賄うことができるわけではありませんが、申請条件や手続きの流れを確認しておくことをお勧めします。
分析依頼から書類作成・電子報告までアスベスト対応を見える化
アスベスト対応業務では、いまだにFAXやメールでの分析依頼、手書きでの書類作成、煩雑な報告準備といったアナログ業務が根強く残っています。
こうした手作業が時間を奪い、本来の現場作業に支障をきたすことも珍しくありません。
「アスベストONE」は、分析から書類作成・報告までをクラウドで完結させ、現場の業務効率化を支援するサービスです。
スマホやタブレットからでも簡単に分析依頼ができ、進捗状況もログインするだけでリアルタイムに確認可能。
受け入れから分析結果までの流れが“見える化”されるので、現場・事務所・協力会社の間で常に最新情報を共有できます。
書類作成は必要な情報をシステムに入力するだけで自動で生成され、作業計画書、報告書、掲示用の看板PDFまで一括で出力可能。
記載ミスのリスクを減らし、工数も削減できます。
さらに、出力したCSVデータをアップロードするだけで、GビズID対応の電子報告がスムーズに完了。
これまで何度も工事情報を入力していた手間やヒューマンエラーを大幅に削減できます 。
クラウド上で進捗管理や情報共有ができるため、確認作業や手戻りも最小限に抑えられ、スピーディーで無駄のない業務が実現します。
まずは無料の個別相談をご利用ください。
現場の状況や業務フローをヒアリングし、最適な活用方法をご提案します。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)

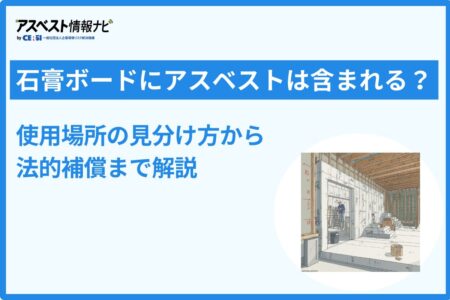
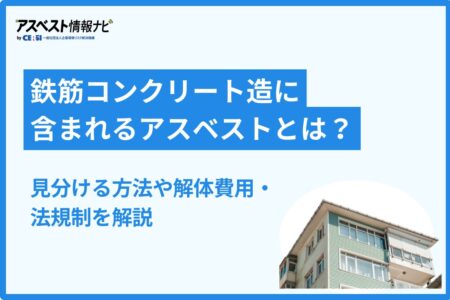












_20250214.png)
