なぜアスベストは危険?健康影響・吸入経路・法規制のポイントまとめ
- 最終更新日:

本コラムでは、アスベストがなぜ危険とされているのかを起点に、
健康被害・使用場所・法規制までを整理します。 ・アスベストが人体に与える影響と、潜伏期間の長い健康被害の特徴 ・解体や改修時にばく露リスクが高まる代表的な使用場所 ・現在の法規制と、元請・発注者に求められる責任と対応 過去の経緯を踏まえ、今なぜ厳格な調査と管理が必要なのかを実務視点で解説します。
アスベストの危険性
アスベストは天然に産出する鉱物繊維であり、非常に細い繊維で構成されているため加工性に優れ、強度が高く、耐火性や断熱性に優れており、さらには摩擦や酸にも強いなど、建築材料として理想的な性質を数多く併せ持っています。
しかも天然鉱物であるため調達が容易でコストも低く、大量生産が必要とされた高度経済成長期の建築現場においては欠かせない存在でした。
住宅の屋根材や外壁材、公共施設の天井材や床材、さらには工場や倉庫の耐火材など、数多くの場面で使用されたのです。
しかし、その利便性の裏で重大な問題が潜んでいました。
後になって明らかになったのは、アスベストが人の健康に深刻な被害をもたらすという事実です。
アスベストの繊維は髪の毛よりもはるかに細く、肉眼で確認することはできません。
一度肺に入り込んだ繊維は排出されにくく長期間にわたって体内に残存し、時間の経過とともに炎症や線維化を引き起こします。
建築物の解体や改修を行う際には必ず建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行い、発注者(施主/工事の注文者)に結果を報告することが義務付けられています。
調査によってアスベストの有無や含有率が確認された結果、含有されているあるいは含有していると「みなす」場合は、厳格な飛散防止措置を施す必要があります。
養生や湿潤化、負圧集じん装置の使用などを徹底しなければ、作業現場から繊維が漏れ出し、想定外の粉じんばく露を招くことになります。
さらに、アスベストはばく露してから健康被害が具体的な症状として現れるまでに数十年の潜伏期間があります。
若い頃に工場や建設現場で働き、粉じんを吸い込んだ人が、定年を迎え高齢になった頃に石綿肺や悪性中皮腫を発症するケースが多く見られます。
症状が現れるまでに時間がかかるため、原因の特定が難しく、被害の拡大を防ぐのが困難だった歴史があります。
現在では法令が整備され、アスベスト含有建材の新たな使用は禁止されていますが、2006年以前に建てられた建物には依然として多くのアスベストが残されています。
したがって、危険性を正しく理解し、適切に管理・除去していくことが、今後も数十年の間、社会全体の課題として残り続けます。
アスベストが健康に与える影響
アスベストが健康に及ぼす影響は深刻であり、かつ潜伏期間が数十年に及ぶため被害が長期的に表面化します。
吸入された繊維は肺の奥深くに沈着し、慢性的な炎症や線維化を引き起こすことがあります。
その代表的な疾患が「石綿肺」で、長期間のばく露によって肺組織が硬化し、呼吸機能が低下します。
また、「悪性中皮腫」はアスベストばく露との因果関係が強く指摘されているがんで、胸膜や腹膜などを覆う薄い膜(中皮)に腫瘍が発生します。
発症すると治療が難しく、予後が厳しい病気として知られています。
さらに肺がんもアスベストばく露によってリスクが高まるとされ、特に喫煙との相乗効果で危険性が増すことが報告されています。
その他にも良性胸膜疾患やびまん性胸膜肥厚など、生活の質を著しく損なう病気が発症することがあります。
これらはいずれもばく露から20年から40年後に症状が現れることが多く、過去にばく露した人が高齢になってから発症するケースが目立ちます。
アスベストを吸い込む可能性のある場所とは
アスベストを吸入するリスクが高まるのは、建築物の解体や改修、修繕等の現場です。
特に2006年9月1日以前に着工された建物ではアスベスト含有建材が使用されている可能性が高く、その使用箇所は外壁材や屋根材、天井材、床材など多岐にわたります。
代表的なものには、スレート屋根、窯業系サイディング、ビニル床タイル、吹付け材、配管の保温材などが挙げられます。
これらが老朽化や破損によって崩れると、繊維の飛散しやすさが飛躍的に高まります。
また、工事現場だけでなく、アスベストを取り扱った工場周辺でもばく露の可能性がありました。
高度経済成長期には製造工程で繊維が飛散し、周辺の住民が無自覚のうちに吸い込んでいた事例も報告されています。
さらに、作業従事者が自宅に作業服を持ち帰ることで家族が二次的にばく露したケースも社会問題となりました。
こうしたリスクを踏まえ、現在では解体や改修に先立って必ず事前調査を実施し、アスベストが含まれている場合には適切な養生や湿潤化といった飛散防止措置を行うことが義務付けられています。
安全な生活環境を守るためには、建物所有者や発注者、元請業者が責任を持って調査を実施または依頼し、メーカー証明や分析結果等の明確な根拠を踏まえた上で対応することが不可欠です。
アスベストに関連する法律
アスベストの危険性が明らかになったことで、日本国内でもさまざまな法律が整備されてきました。
その中心となるのが大気汚染防止法と石綿障害予防規則(労働安全衛生法)です。
これらの法律では、解体や改修工事における事前調査の実施、結果の報告、作業計画の策定、飛散防止措置の実施、作業従事者への保護具の着用などが規定されています。
違反した場合の罰則が定められているだけでなく、労働基準監督署の職員等による送検・摘発にも繋がり得る厳格な法令です。
また、建築基準法もアスベスト使用建材に関する規制を定めています。
増築や改築を行う場合には原則として既存部分のレベル1建材(吹付け材)、レベル2建材(断熱材、保温材、耐火被覆材)の除去が義務付けられるほか、
増改築部分の合計床面積が増改築前の延床面積の2分の1を超えない場合であっても、封じ込めや囲い込み等による飛散対策が求められます。
こうした法制度は、作業従事者や住民を保護するだけでなく、建物所有者や発注者(施主/工事の発注者)、元請業者の責任を明確にし、社会全体でアスベスト被害を減らすために機能しています。
アスベストにおける法規制の歴史
日本におけるアスベスト規制は、段階的に強化されてきました。
1975年には特定化学物質等障害予防規則によって、重量比5%を超える吹付け材の使用が原則禁止されました。
その後、1995年には規制が拡大され、重量比1%を超える吹付け材が禁止されると同時に、労働安全衛生法施行令の改正によりアモサイト(茶石綿)やクロシドライト(青石綿)といった一部のアスベストの輸入・製造が禁じられました。
2004年にはさらに規制が進み、建材や摩擦材、接着剤などへの使用が禁止され、2006年には労働安全衛生法の改正によって重量比0.1%を超える製品の製造・輸入・使用が全面的に禁止されました。
このように規制は徐々に厳格化されていき、現在では新たにアスベスト含有建材を使用することはできません。
ただし、規制が始まる前に建てられた建物には依然として多くのアスベストが残っており、解体や改修の現場でリスクが発生する状況が続いています。
したがって、法規制の歴史を理解することは、現在直面している問題の背景を知る上で欠かせません。
規制の強化は、被害が顕在化してからようやく進められた経緯があります。
潜伏期間の長さゆえに健康被害の因果関係が分かりにくく、対策が遅れたことが被害拡大の一因となりました。
現在は法令のもとで厳格な管理が行われていますが、今後も建物解体のピークを迎えるにあたり、より一層、関係事業者の抜け漏れのない法令遵守が求められます。
分析依頼から書類作成・電子報告までアスベスト対応を見える化
アスベスト対応業務では、いまだにFAXやメールでの分析依頼、手書きでの書類作成、煩雑な報告準備といったアナログ業務が根強く残っています。
こうした手作業が時間を奪い、本来の現場作業に支障をきたすことも珍しくありません。
「アスベストONE」は、分析から書類作成・報告までをクラウドで完結させ、現場の業務効率化を支援するサービスです。
スマホやタブレットからでも簡単に分析依頼ができ、進捗状況もログインするだけでリアルタイムに確認可能。
受け入れから分析結果までの流れが“見える化”されるので、現場・事務所・協力会社の間で常に最新情報を共有できます。
書類作成は必要な情報をシステムに入力するだけで自動で生成され、作業計画書、報告書、掲示用の看板PDFまで一括で出力可能。
記載ミスのリスクを減らし、工数も削減できます。
さらに、出力したCSVデータをアップロードするだけで、GビズID対応の電子報告がスムーズに完了。
これまで何度も工事情報を入力していた手間やヒューマンエラーを大幅に削減できます。
クラウド上で進捗管理や情報共有ができるため、確認作業や手戻りも最小限に抑えられ、スピーディーで無駄のない業務が実現します。
まずは無料の個別相談をご利用ください。現場の状況や業務フローをヒアリングし、最適な活用方法をご提案します。



_20250217_すず-1024x154.jpg)



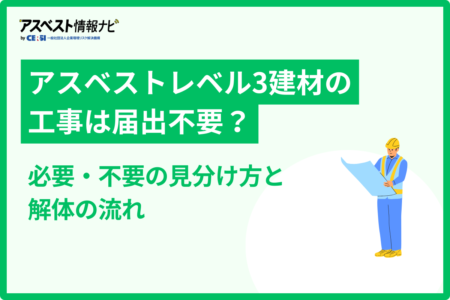











_20250214.png)
