アスベストはいつから禁止となった?元請業者・建物管理者が知るべき法改正の流れ
- 最終更新日:

かつて「奇跡の鉱物」とも呼ばれたアスベストは、その耐火性・断熱性の高さなどから建築材料として長年にわたり広く使用されてきました。
しかし、その微細な繊維を吸い込むことで発症する中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害が明らかになり、国内外で規制が進むこととなります。
日本でも1975年の吹付けアスベスト原則禁止を皮切りに、段階的な法改正を経て、2006年には実質的な全面使用禁止に至りました。
元請業者や建物管理者にとっては、これらの規制の歴史を正しく理解し、建築物の調査や管理に活かすことが法令遵守と安全管理の第一歩です。
本記事では、アスベスト規制の法改正の流れと、その実務上の意味について詳しく解説します。
・アスベスト使用禁止の法改正の流れ(1975年〜2006年)と段階的禁止
・アスベスト禁止時期を知るべき理由とは?建材判断と調査計画への影響
アスベスト使用禁止の法改正の流れ(1975年〜2006年)と段階的禁止
アスベストの使用に関する法的な規制は、1975年に労働安全衛生法に基づく省令改正によって始まりました。
この年、アスベストを 5 重量%超えて含有する吹付け作業が原則禁止されたことが、日本におけるアスベスト使用禁止の第一歩となりました。
その後、1995年には労働安全衛生法施行令が改正され、アスベストを含む吹付け材の使用が全面的に禁止されました。
続いて2004年には、アスベスト含有量が重量の1%を超える製品の製造、輸入、使用などが禁止されました。
さらに2006年には、アスベスト含有量が0.1%を超える製品の製造や使用が原則禁止となり、事実上の全面禁止が達成されました。
なお、化学工業施設におけるグランドパッキンなど、一部の製品は2006年9月1日以降も製造、使用が許されているものがあるため注意が必要です。
このようにアスベストは段階的に規制され、2006年9月1日をもって実質的な全面禁止に至りました。
なお、新築着工日が2006年9月1日より前の建物にはアスベストが使用されている可能性があるため、現在もその調査や対策が重要となっています。
アスベストの全面禁止が実現したとはいえ、それ以前に施工された多くの建築物には依然としてアスベスト含有建材が残存しており、そのリスクは現在も無視できません。
特に、老朽化した建物の解体や改修工事を行う際には、アスベストの飛散による健康被害を防ぐため、事前調査と適切な除去作業が不可欠です。
厚生労働省や環境省は、アスベストに関する規制やガイドラインを随時見直し、業界関係者への周知を進めています。
また、アスベストの事前調査結果は、2022年4月以降、原則として電子報告が義務付けられており、建設業界における情報管理の厳格化が進んでいます。
今後も法改正に対応しつつ、技術者や管理者は最新の知識を持って、安全な施工環境を確保することが求められています。
アスベスト問題は過去のものではなく、現在進行形の課題として認識することが重要です。
アスベスト禁止時期を知るべき理由とは?建材判断と調査計画への影響
元請業者や建物管理者にとって、アスベストの禁止時期を正確に把握しておくことは極めて重要です。
なぜなら、建物の築年数によってアスベストが含有されている可能性が大きく異なるためです。
たとえば1975年以前に建てられた耐火建築物では、吹付けアスベストの使用が広く行われていた可能性があります。
また、2006年9月1日より前に新築着工された建物でも、アスベスト含有建材が使用されているリスクを排除できません。
そのため、改修工事や解体工事を行う前には、建物の新築着工日を確認し、アスベストの使用有無を慎重に評価する必要があります。
禁止時期を把握しておらず、アスベスト含有建材の使用有無を調査せずに作業を進めた場合、
法令違反となるだけでなく、労働者の健康被害や近隣住民への悪影響といった重大なリスクを引き起こす可能性があります。
調査対象となる建材を正しく選定するためにも、アスベストの禁止時期を正確に知ることが求められます。
さらに、アスベストの禁止時期を把握することは、調査計画の効率化にも大きく寄与します。
築年数をもとにリスクの高い部位や建材を事前に絞り込むことで、無駄のない調査手順を組むことが可能となり、時間的・経済的コストの削減にもつながります。
とりわけ、複数棟を管理する大規模施設や再開発事業においては、こうしたリスク評価の初期段階での正確さが、後々の工程全体の安全性と効率性を左右します。
また、元請業者は下請業者や作業員に対してアスベストの有無や注意事項を正確に伝達する責任も負っているため、禁止時期の知識を持っていないことは管理者としてのリスクでもあります。
施工現場でのトラブルや健康被害の発生を未然に防ぐためにも、元請業者自身が率先してアスベスト関連の情報を把握し、計画に反映させる姿勢が求められます。
安全で適切な工事の実施には、こうした事前準備が欠かせません。
築年数・図面・仕様書などからアスベスト含有リスクを推定する方法
アスベスト含有のリスクを推定するには、まず建物の築年数を確認することが基本です。
前述のとおり、2006年9月1日より前に新築着工された建物ではアスベストが含まれている可能性があり、特に1970年代から1990年代にかけてはアスベストを含む建材の使用が一般的でした。
また、建築当時の設計図面や仕上表、建材仕様書などが残っている場合、それらを確認することでアスベスト含有の可能性がある建材を特定できます。
たとえば、ケイ酸カルシウム板、バーミキュライト吹付け材などは、かつてアスベストを含んでいた製品が存在します。
たとえ設計図書等から情報が得られる場合であっても、現地での目視調査やサンプリング調査を行い、アスベストの有無を確認する必要があります。
また、建材メーカーのカタログ、JIS番号、製品名などの情報からも、アスベストの含有リスクを推定できるケースがあります。
建物の履歴情報をできるだけ詳細に収集することが、正確なリスク評価と調査計画の策定につながります。
さらに、建物の過去の改修履歴も、アスベスト含有リスクを見極める上で重要な手がかりとなります。
たとえば、建設当初にアスベストが使われていなかったとしても、その後の改修や補修工事においてアスベスト含有建材が使用されていた可能性も否定できません。
したがって、設計段階から竣工後に至るまでの全体の履歴をできるだけ遡って確認することが求められます。
また、調査対象となる建材は、単に建築躯体にとどまらず、天井材、壁材、床材、配管の断熱材、ボイラーまわりの保温材など、幅広い部位にわたるため、
建築や設備に関する幅広い知識が調査には必要となります。
現場の状況や劣化の程度、使用されている建材の層構成なども含めて総合的に判断することが、より精度の高いアスベストリスク評価につながります。
アスベスト調査を専門業者に依頼する場合でも、元請業者や建物管理者自身が基礎的な知識を持っていることで、調査結果を適切に理解し、
今後の工事計画や管理方針に反映させることが可能となります。
そのためにも、築年数や設計資料の確認に加えて、現場の詳細な把握と過去の修繕履歴の収集をあわせて行うことが大切です。
アスベスト禁止時期を踏まえた適切な事前調査
事前調査を実施する際には、アスベストに関する法的な背景と禁止時期を踏まえた上で、どの建材にリスクがあるのかを評価し、効率的な調査計画を立てることが重要です。
厚生労働省のガイドラインでは、すべての解体・改修工事対象建築物について、事前調査の実施とその結果の報告が義務付けられています。
調査方法は、書類調査、目視調査、分析調査の三段階が基本となります。
まずは書類調査でリスクのある建材を洗い出し、目視調査で書類と現地の状況の整合性や建材の型番等の情報を収集し、必要に応じてサンプリングを行って分析します。
とくに2006年9月1日より前に新築着工された建物については、書類調査だけでなく有資格者による目視調査も行うことが必須とされており、より慎重な調査が求められます。
また、2022年4月からは、改修・解体等工事を行う元請業者に対して、アスベストの事前調査結果を電子システムで報告する義務が課されています。
これは法令遵守の観点から非常に重要であり、元請業者側の情報管理体制の強化が求められます。
アスベストONEで書類作成・進捗管理を効率化し、法令遵守も安心サポート
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)対応業務に必要な書類作成と進捗管理を、クラウド上でワンストップで支援するサービスです。
これまで手間と時間のかかっていた作業を効率化し、現場との情報共有までを一括でカバーします。
入力項目に沿って進めるだけで、事前調査報告書や作業計画書、現場掲示用の看板PDFなどを自動で生成。
法令に準拠したフォーマットで出力されるため、記載漏れやミスを防ぎます。
さらに、GビズIDに対応した電子報告にも対応しており、出力したCSVデータを一括アップロードするだけで行政への報告が完了するため、
手入力による負担やミスを軽減できます。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく下請け業者や協力会社とも最新情報を簡単に共有可能です。
進捗状況や全体工程も見える化され、手戻りの少ないスムーズな業務連携を実現します。
EMSでは、現場の状況や課題をヒアリングしたうえで、最適な運用方法を無料相談でご案内しています。
業務負担を軽減し、確実に法令対応できる体制をぜひアスベストONEで実現してください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)

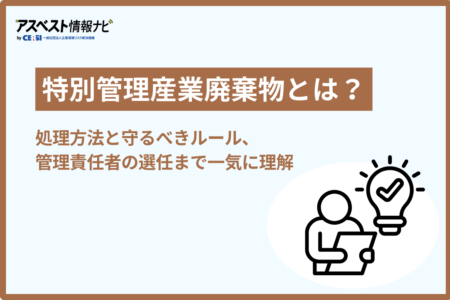

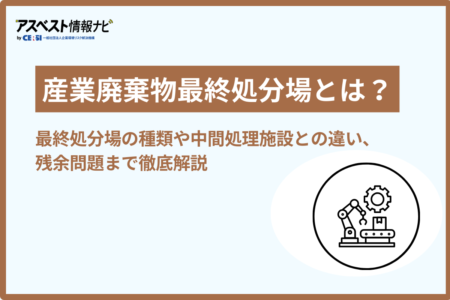











_20250214.png)
