アスベスト使用禁止の全体像|禁止時期・対象建材と現場の対応手順
- 最終更新日:

アスベストは、耐熱性や断熱性、耐久性に優れた素材として建材や工業製品に広く使用されてきましたが、
吸入による健康被害(中皮腫や肺がんなど)が明らかになるにつれ、日本では段階的に使用が規制・禁止されていきました。
以下に、1975年から2006年までの主な禁止の経緯と対象品目についてまとめます。
法令によるアスベスト禁止の経緯(1975~2006年)と対象品目
まず、1975年に最初の規制が導入され、アスベストの飛散リスクが高い吹付けアスベストの使用が原則禁止されました。
これにより、建築物でのアスベスト吹付け施工が大きく制限されましたが、アスベストを含む建材(成形品など)は引き続き使用されました。
次に、1995年の労働安全衛生法改正により、クロシドライト(青石綿)とアモサイト(茶石綿)の使用・製造・輸入が禁止されました。
これらはアスベストの中でも発がん性が特に高いとされ、早期に規制対象となったのです。
2004年にはさらに規制が強化され、石綿含有建材、石綿含有摩擦材、石綿含有接着剤の輸入、製造、使用等が禁止されました。
ただし、代替が難しい製品については「特定用途」として例外措置が認められていました。
そして、決定的な転換点となったのが2006年の改正です。
この年の法改正により、アスベスト含有率が重量比で0.1%を超えるすべての製品について、製造・輸入・譲渡・提供・使用が原則禁止されました。
対象品目は建材にとどまらず、パッキン、ガスケット、クラッチライニング、ブレーキパッド、シール材など、産業用部品にも及びます。
このように、日本では30年以上かけて段階的にアスベストの使用が規制され、2006年に事実上の全面禁止となりました。
これにより、現在では新規のアスベスト使用は認められていませんが、過去に建設された建物などには依然として残存しているケースが多く、
解体・改修時の注意と法令遵守が強く求められています。
使用禁止建材の一覧とアスベスト含有判断のポイント
アスベストは、2006年の法改正により、重量比で0.1%を超える含有製品の製造・輸入・譲渡・提供・使用が原則禁止されました。
以下は、過去に使用されており、現在は使用が禁止されている主な建材の一覧です。
代表的な使用禁止建材には、以下のものがあります。
- 吹付け石綿(耐火・断熱・吸音目的)
- 石綿含有保温材(ボイラー・配管等の断熱材)
- 石綿含有成形板(押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板等)
- 石綿スレート(屋根材・外壁材等)
- 石綿含有ビニル床タイル、接着剤(床仕上げ用等)
- 石綿含有石こうボード、パッキン・ガスケット
これらは主に1970年代から1990年代初頭に多用され、建物の屋根、壁、天井、配管周辺などに使われました。
アスベスト含有判断のポイントとしては、まず建物の建築年代が重要です。
特に1980年代以前の建築物は、含有の可能性が高いとされていますが、それ以降の建築物であっても使用されているケースがあるため、年代だけで判断することはできません。
また、建材の種類や形状、設置場所も判断材料になります。
たとえば、吹付け材や成形板であれば、リスクが高いとされます。
正確な判断には、設計図書や材料仕様書を確認することが第一ですが、
不明な場合は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による現地調査と、建材のサンプリング・分析(定性分析)を行う必要があります。
アスベストは見た目のみで含有有無を判別することはできないため、経験や知識だけに頼らず、
法令に沿った適切な調査と判断を行うことが、健康被害と法的リスクの回避につながります。
使用禁止以前の建築物に残されたアスベスト含有建材の管理と注意点
2006年の全面禁止以前に建築された建物には、現在もアスベストを含む建材が残存している可能性が高いと言われています。
比較的飛散性が低いとされるレベル3建材であったとしても、通常の状態では直ちに健康被害を及ぼすわけではありませんが、老朽化や改修・解体時に飛散のリスクが高まります。
そのためレベルに応じた適切な管理が必要です。
まず建物の竣工年や図面、過去の改修履歴をもとに、アスベスト含有の可能性がある箇所を把握することが重要になります。
目視だけでは判断できないため、必要に応じて専門機関による分析調査を実施します。
また、建物の解体時には原則としてアスベスト含有建材の除去が必要ですが、建物の改造・補修においては、
レベル1・2建材の封じ込めや囲い込みといった措置も選択肢として認められます。
石綿含有建材をむやみに取り扱ったり撤去したりすることは、粉じんの飛散や法令違反につながるおそれがあるため、必ず資格を持つ作業者による安全な対応が求められます。
建物の維持管理においてはリスクの正しい理解と計画的な対応が不可欠です。
アスベスト法令違反時の罰則・行政指導の事例と教訓
アスベスト関連の法令違反が発覚した場合、企業や個人には厳しい罰則や行政指導が科されます。
例えば、事前調査の未実施や無届けでの解体工事、飛散防止措置の不備などが典型的な違反例であり、労働安全衛生法や大気汚染防止法に基づき、最大で6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(法人両罰あり)といった刑罰が適用される可能性があります。
過去には、大手建設会社が飛散防止措置を怠ったことで行政処分を受け、社会的信頼を大きく損なった事例がありました。
こうした事例は、現場管理の甘さや教育不足が招いた結果であり、事業者には法令遵守と徹底したリスク管理が求められます。
違反が発覚すれば企業の信用失墜や損害賠償にもつながるため、アスベスト対応に関しては最新の法規制と手順を確実に理解・実行することが重要です。
アスベスト含有建材を扱う際のアスベスト調査・報告の手順
建築物の解体・改修工事を行う際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査し、所定の手続きに従って報告することが法令で義務付けられています。
まず、建物の設計図や仕様書を確認し、使用されている建材の種類や施工時期からアスベスト含有の可能性を推測します。
次に、必要に応じて建材のサンプルを採取し、専門機関で定性・定量分析を実施します。
調査の結果、アスベストが含まれていると判明した場合は、「石綿障害予防規則」および「大気汚染防止法」に基づき、必要に応じて労働基準監督署や自治体に届出を行い、適切な飛散防止措置の計画を立てます。
報告を怠ると法令違反となり、罰則の対象になるため注意が必要です。
調査・報告は、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行うことが求められており、正確な対応が安全確保の第一歩です。
アスベスト分析から書類作成・電子報告まで、クラウドで完結。現場の業務効率化を今すぐ実感
建設現場のアスベスト対応業務は、分析の手配、進捗確認、法令に沿った書類作成、行政への報告など、煩雑で時間のかかる業務が多く、担当者の大きな負担となっています。
こうした業務に追われて、「本来の作業に集中できない」「毎回の対応が手探りで大変」…そんなお悩みはありませんか?
アスベストONEは、分析依頼から書類作成、電子報告までをクラウド上で一元管理できるサービスです。
必要な情報をクラウド上のフォームに入力するだけで、分析依頼が完了し、進捗もリアルタイムで確認可能。
作業計画書や報告書、現場掲示用の看板PDFなども自動生成され、書類作成にかかる工数を大幅に削減できます。
出力される書類は法令に準拠したフォーマットなので、記載漏れや誤記のリスクも軽減。
さらに、GビズIDに対応した電子報告も可能で、手入力による煩雑な作業から解放されます。
また、クラウド上でのデータ共有により、現場・事務所・協力会社の間で常に最新の情報が確認できるので、手戻りや無駄な確認作業も減り、スピーディーで確実な業務連携が実現します。
アスベスト対応における事務負担の軽減、コスト削減、法令対応の徹底を、ぜひアスベストONEでご体感ください。
まずは無料の個別相談で、貴社の現場に合わせた最適な活用方法をご提案いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)

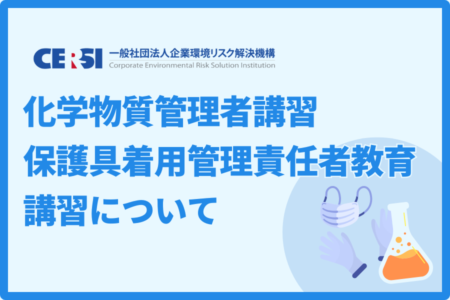













_20250214.png)
