マンションにアスベストがある?建物所有者・管理組合が知っておくべき対応ポイント
- 最終更新日:

本コラムでは、
マンションにおけるアスベスト使用の可能性と、管理者・所有者が直面する実務上のポイント
を整理します。
・築年数別に見たアスベスト使用リスクと、法令上の考え方
・管理者・管理組合に求められる住民への説明責任と対応リスク
・共用部・専有部それぞれにおける調査の進め方と判断の注意点
マンション特有の 「誰が・どこまで・どう対応すべきか」 という論点を中心に、
調査結果の扱い方から除去・維持管理まで、管理実務に直結する要点を解説します。
マンションにおけるアスベスト使用の可能性と築年数との関係
アスベストとは石綿のことで、耐熱性、耐摩耗性、絶縁性などに優れているため、過去には建材や工業製品に広く使用されていました。
しかし、アスベストは繊維状の鉱物であるため繊維を吸い込むと肺炎などの健康被害を引き起こす可能性があります。
そのため段階的な規制強化を経て2006年9月1日以降アスベストの使用が全面的に禁止されるようになりました。
マンションの築年数によっては、建築時にアスベストが使用されている可能性があります。
特に、1975年以前に建てられたマンションは、アスベスト含有建材が使用されている可能性が非常に高く対策が必要になりますが、
法的には新築着工日が2006年9月1日以降でなければ、アスベスト含有建材を使用している可能性を否定できないとされています。
アスベスト含有建材が使用されている場合、リフォーム・解体工事の際に大きなコストアップ要因となったり、
建材の種類によっては工事をしなくても劣化して繊維を飛散させ、住民にとって健康被害のリスクになる場合があります。
マンションの所有者、管理者はアスベストに関する危険性を十分に理解し、法令に則った対応を行う必要があります。
_20250217_すず-1024x154.jpg)
マンション住民へのアスベスト説明責任と管理者としての対応リスク
宅地建物取引業法(宅建業法)では、建物の取引に際しアスベストの調査が過去に行われた履歴があれば、
その内容を重要事項として説明しなければならないと規定しています。
アスベスト含有建材の使用が判明した場合、管理者や管理組合は住民に速やかに説明することが望まれます。
一般的に、アスベスト含有建材は切断や損傷を及ぼさなければ飛散せず、通常の生活において健康被害を及ぼすリスクは小さいです。
しかしながら、石綿含有吹付け材等の建材では、建材の劣化の進行等により工事等を行わなくとも粉じんが発生し、住民に健康被害を及ぼす可能性があります。
建築物石綿含有建材調査者など、適正な資格を持った調査者による調査結果をもとに、建築物における石綿のリスクを正しく把握し、透明性を持って住民に伝えることが重要です。
住民への説明が不十分だったり、必要なアスベストへの対応を行わなかったなどの場合には、最悪の場合、管理側の責任を問われ法令違反となったり、民事での損害賠償を求められることもあり得ます。
したがって、アスベストの調査結果や対応方針は、早期に文書や説明会等を通じて住民に伝えることが極めて重要です。
特に、アスベスト除去工事を行う場合は、施工方法や安全対策、工期などの作業計画を詳細に説明し、住民の理解と同意を得ることが必要不可欠です。
対応を怠った場合のリスクは、法的責任だけでなく、マンション全体の資産価値の低下や管理者への信用失墜にもつながります。
したがって、管理者は専門業者との連携を強化し、法令に基づいた調査・対応を適切に行い、住民と継続的かつ透明なコミュニケーションを取る体制を整えることが、最重要課題となります。
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
共用部と専有部でのアスベスト調査の進め方
マンションにおけるアスベスト調査は、「共用部」と「専有部」で進め方が異なります。
それぞれの部位に応じた調査手順と、法令に基づく適切な対応が求められます。
まず、共用部とは、エントランスホール、廊下、階段、外壁、屋上など、専有部以外の部分を指します。
共用部でのアスベスト調査は、管理組合が主体となって実施することが一般的です。
共有部の調査は原則として一般建築物石綿含有建材調査者や特定建築物石綿含有建材調査者の有資格者が行う必要があります。
一戸建て等石綿含有建材調査者の資格では調査ができませんので注意が必要です。
一方、専有部は各住戸内の居室や台所、浴室などを指します。
専有部のアスベスト調査は原則として各区分所有者の責任のもとに行われることが一般的です。
ただし、住戸のリフォームや設備更新などの工事を行う際にアスベストが使用されている可能性がある場合は、工事業者を通じて事前調査を実施し、その結果に応じた対応が必要です。
専有部の調査に関しては「一般」「特定」だけではなく「一戸建て」の調査者も行えますが、ベランダやバルコニーは共用部となりますので気を付けましょう。
なお、専有部の調査や除去作業が共用部に影響を与える場合(たとえば換気ダクトの共有など)、管理組合と連携して進める必要があります。
トラブル回避のためにも、管理規約でアスベスト対応に関するルールを明確化し、住民への周知徹底を図ることが重要です。
共用部・専有部を問わず、調査は専門知識と適切な手順を要するため、資格を有する業者に依頼し、報告書を文書で残すことがリスクマネジメントにつながります。
管理者・所有者としては設計図書等の提供や写真撮影の許諾、サンプル採取の許諾など、調査者が適正な調査を行えるよう、可能な限り協力することが求められます。
アスベスト調査結果の確認と対応方針の決定
アスベストの調査結果は、必ず書面にて工事の元請業者から発注者に説明することが義務付けられています。
アスベスト含有建材がある場合はもちろんのこと、ない場合であっても発注者への説明は必須となります。
リフォーム、解体等の工事に伴う事前調査であれば、この説明は必ず着工より前に行うこととされています。
マンションのリフォーム・解体工事期間中、施工業者は工事現場にはこの調査結果を掲示する必要があります。
住民・労働者の双方が見やすい場所に看板を掲示し、調査を実施した箇所と建材ごとにアスベスト含有状況を明確にすることが義務付けられていますので、管理側も掲示場所の提供等の協力が望まれます。
調査結果の確認後、アスベストの有無によって対応方針を決めていきます。
アスベスト含有建材がある場合、あるいはアスベストの有無が不明であり「みなし」で工事を行う場合には、養生、湿潤化、作業主任者の選任など法令で求められる対応を行います。
また、レベル1・レベル2の石綿含有建材の除去等の作業を行う場合は、工事着工の14日前までに管轄する労働基準監督署及び大気汚染防止法窓口に必要書類を提出する必要があります。
工事の施工業者だけではなく発注者にも提出の義務があるものもありますので、法令をよく確認して対応することが必要です。
アスベスト調査結果の確認と対応方針の決定は、周辺住民と作業従事者の双方の健康を守るために非常に重要です。
関係法令を遵守し、適切な対応を徹底しましょう。
アスベスト除去・封じ込めの対策実施とその後の維持管理
リフォーム等工事に伴い一部のアスベスト含有建材を除去したのちも、まだアスベスト含有建材が残っている場合や、アスベスト含有建材からの粉じんの飛散を抑えるため、封じ込め・囲い込み等の工事を行う場合があります。
これらの場合には、アスベスト含有建材を完全に除去したわけではありませんので、適切な維持管理が重要です。
封じ込めや囲い込みを行った場合、定期的な点検を行い、劣化や損傷がないか確認します。
また、解体時にはアスベストの除去が必要になります。
対策実施後に維持管理を行う方法として定期点検や劣化損傷の確認などが挙げられます。
特に封じ込め対策を行った後は劣化の状況に応じ半年~1年に1回程度定期的に建材の状況の確認を行うことが推奨されます。
アスベスト含有建材については、完全に除去を行うことが最も安心なのは言うまでもありません。
しかしながら、費用や工期、建物の構造などの問題からアスベスト含入建材を完全に除去することが難しい場合もあります。
そのような場合には十分な飛散防止対策と定期的な確認を含め、健康被害のリスクを最小限にすることが重要です。
アスベストONEで分析依頼から書類作成・電子報告までを効率化
「アスベストONE」は、クラウド上での分析依頼から進捗状況の確認、書類作成までをワンストップでサポートするクラウドサービスです。
システムに沿って入力するだけで、法令に準拠した作業計画書や報告書を自動で生成できるため、これまで手間のかかっていた書類作成業務を大幅に効率化できます。
さらに、CSV形式で一括出力したデータはGビズIDと連携して電子報告が可能なため、複雑な行政手続きもスムーズに対応できます。
また、書類の作成状況や進捗がクラウド上で“見える化”されており、現場・事務所・協力会社の間で常に最新情報を共有・確認できます。
これにより、手戻りや確認作業を最小限に抑えた、無駄のない連携が可能になります。
EMSでは、アスベスト対応に関する無料の個別相談も承っております。
専門スタッフが現場の状況を丁寧にヒアリングし、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内いたします。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)

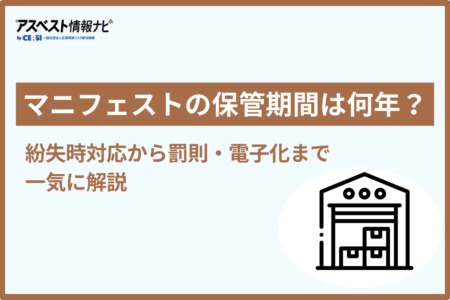
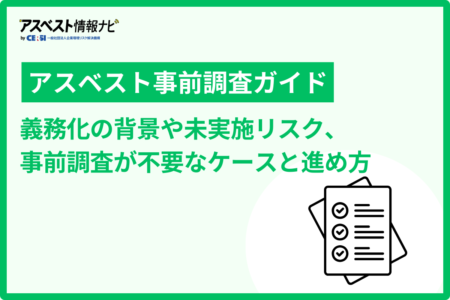











_20250214.png)
