アスベスト事前調査が必要な工事・不要な工事と実施から報告までの流れ
- 最終更新日:
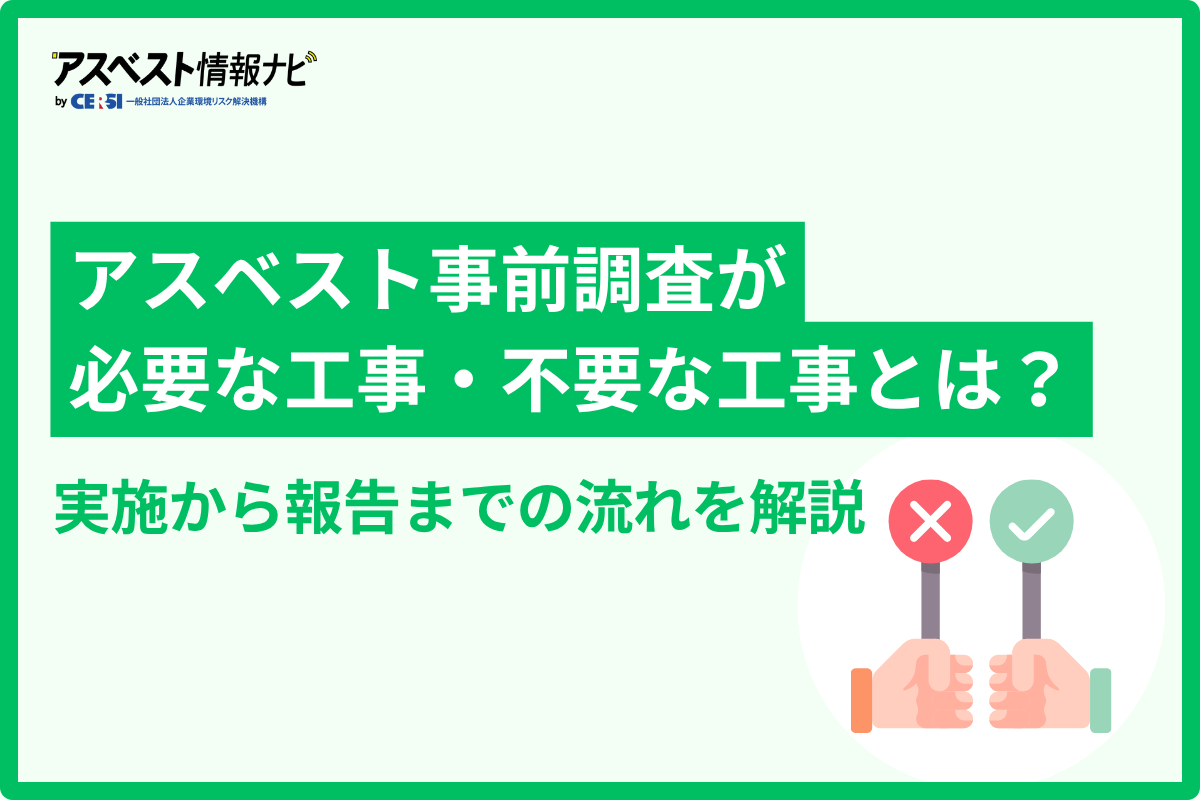
本コラムでは、アスベスト事前調査がどの工事で必要になり、
どこまで対応すべきかを実務ベースで整理します。 ・事前調査が義務となる工事内容と、対象となる建築物・工作物の考え方 ・調査が不要と判断できるケースと、その際に元請が注意すべきポイント ・事前調査から結果報告までの流れと、行政対応で求められる実務 「やらなくていいと思っていた」が通用しない理由を、元請目線で具体的に解説します。
アスベスト事前調査はどんな場合に必要?
元請業者が解体や改修工事を行う際、対象建築物や工作物にアスベスト含有建材が使用されている可能性がある場合は、着工前に「アスベスト事前調査」を実施する必要があります。
これは大気汚染防止法および労働安全衛生法で定められており、2022年4月1日の規制強化に伴い、一定規模以上の工事については事前調査結果を行政に報告することも義務付けられました。
具体的には、次のような工事が調査対象です。
- 建築物全体の解体工事
- 外壁や屋根、内装材の改修工事
- 設備配管やダクト、保温材の撤去工事
- 工作物(煙突、貯蔵タンク等)の解体や改修
特に2006年9月1日以前に着工された建築物は、アスベスト含有建材が使用されている可能性が否定できないため、慎重な調査が必要です。
事前調査は、原則として有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)が行い、現地での目視確認、設計図書の確認、必要に応じた試料採取・分析を通じて、含有の有無を判定します。
アスベスト事前調査が不要な場合とは
一方で、全ての工事が必ずしもアスベスト事前調査の対象になるわけではありません。
調査が不要とされるのは、アスベスト含有の可能性が明らかにない場合や、工事の内容においてアスベスト粉じんの飛散の恐れがない場合です。
厚生労働省の通知によれば、次のようなケースでは不要とされることがあります。
- 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
- 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。
- 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。
ただし、塗装工事であっても事前に高圧洗浄を行う場合には既存の塗装が除去される可能性があるため、事前調査が必要であると一般に判断されています。
一つの指標として、既存の建材の損傷、除去を伴う工事であれば、原則として上記の3つのパターン以外の工事では事前調査は必要である、といえます。
上記3パターンの工事に当てはまるため事前調査不要である、と判断した場合でも、元請業者は「不要」と判断した理由を記録に残し、監督官庁から求められた際に提示できる体制を整えることが望ましいでしょう。
2006年9月1日以降に着工された建築物は事前調査が不要?
2006年9月1日以降は、0.1重量%を超えるアスベストを含む製品の製造・輸入・使用が全面禁止されました。
そのため、この日以降に新築着工された建築物は、基本的にアスベスト含有建材が使用されていないと考えられます。
しかし、誤解されがちではありますが事前調査が不要になるわけではありません。
2006年9月1日以降に新築着工された建物でも先述の3パターンの工事以外は、原則としてすべての工事においてアスベスト事前調査が必要になります。
ただし、2006年9月1日以降の建物の事前調査については、書面調査の段階でその建物の新築着工日が2006年9月1日以降である、ということを確認できれば、
現地での目視調査を行わずにアスベスト含有建材は使用されていない、と判断して良いこととなっています。
この判断に関しては、必ずしも建築物石綿含有建材調査者等の有資格者でなくても行うことが可能です。
なお、上記の通り2006年9月1日以降に新築着工された建物においては、事前調査の中でも書面調査の段階まででアスベスト含有建材なしの判断を下すことができ、
現地での目視調査やサンプルを採取しての分析調査を省略することが可能ですが、あくまでも事前調査そのものは実施義務があることに注意が必要です。
このため、事前調査結果記録の作成や発注者への書面での調査結果説明は必要となり、解体面積80㎡以上の解体工事や請負金額100万円(税込)以上の改修工事であれば行政への事前調査結果報告の対象にもなります。
アスベスト事前調査の流れについて
アスベスト事前調査は、以下の流れで実施するのが一般的です。
事前情報の収集・書面調査
設計図書や仕様書、過去の改修履歴を確認し、使用建材や施工年代を把握します。
現地調査の実施
建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が現場に赴き、目視確認や建材の状態確認を行います。分析調査が必要である場合には、建材の一部を試料として採取します。
試料分析
採取した試料は分析機関に送り、偏光顕微鏡法やX線回折法などで含有の有無を確認します。
調査結果のまとめ
調査結果は、使用した分析手法や判定基準とともに報告書にまとめます。
工事計画への反映
結果を踏まえ、必要な飛散防止措置や届出の有無を判断し、工事計画を策定します。
この流れを確実に踏むことで、法令遵守と安全確保が可能になります。
また、この流れの中で特に重要なのは、各工程の記録を正確に残すことです。
事前情報の収集段階では、設計図書や仕様書の写し、過去の工事写真、材料証明書などを整理し、現場調査との整合性を確認します。
現地調査時には、採取位置や建材の状態を写真付きで記録し、後から第三者が見ても判断できるようにしておくことが望まれます。
試料分析では、分析機関の選定も重要です。
分析機関の選定には、分析料金はもちろんのこと、精度の信頼性、納期、対応できる分析手法、レスポンスの良さなど、様々な観点を踏まえて考えることが望ましいでしょう。
調査結果報告書の取りまとめでは、使用した分析方法、判定基準、採取試料の番号と位置などを明記し、飛散防止策の策定や届出の必要性を明確化します。
最後に、工事計画への反映では、調査結果を基に安全管理計画や工程表を修正し、発注者や下請業者と共有します。
こうした情報共有を徹底することで、現場での作業手順が統一され、不要な粉じん発生や法令違反のリスクを抑えることができます。
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
アスベスト事前調査結果の報告の流れ
前述の通り、建築物であれば解体面積80㎡以上の解体工事並びに請負金額100万円以上(税込)の改修工事においては、アスベスト含有建材の有無にかかわらず事前調査結果を行政に報告する必要があります。
報告は原則、インターネット上の石綿事前調査結果報告システムから行います。なお、この際にGビズIDが必要になります。
事前調査結果の報告は原則として工事の着工前に行うことが義務付けられており、石綿事前調査結果報告システムから報告を行えば管轄する労働基準監督署と自治体の大気汚染防止法窓口の双方に報告がなされる仕組みとなっています。
また、調査結果記録や作業記録写真等は工事完了後も一定期間(原則3年間)保存し、後日の問い合わせや行政の立入検査に対応できるようにします。
尚、労働者の作業記録は、40年間の保存が義務づけられています。
元請業者は、調査から報告までの一連のプロセスを正確かつ迅速に行うことが求められます。
これにより、工事の安全性と信頼性を高め、発注者や地域社会への説明責任を果たすことができます。
アスベスト対応を分析から書類作成・電子報告まで、クラウドで効率化
従来のアスベスト対応業務は、FAXやメールによる分析依頼、煩雑な書類作成、進捗の確認や管理、報告手続きと、手間もミスも起きやすい作業の連続でした。
「効率化を図りたいが、法令対応のために結局アナログ作業が多い」──そんな悩みを抱える現場担当者も少なくありません。
「アスベストONE」は、こうした業務をまとめてクラウド上で効率化するサービスです。
フォームに沿って情報を入力するだけで、分析依頼が完了し、受け入れ状況や進捗もリアルタイムで確認可能。
書類作成も自動化され、作業計画書・報告書・現場掲示用の看板までワンクリックで出力できます。
出力される書類はすべて法令に準拠したフォーマットのため、記載内容の整合性や記入漏れにも安心。
GビズIDを連携した電子報告にも対応しており、従来のような手入力作業を省くことで、時間と手間を大幅に削減できます。
スマホやタブレットからも利用できるので、現場や出張先からもスムーズに操作が可能。
現場・事務所・協力会社間で常に最新の情報を共有できるため、手戻りや重複作業を減らし、スピード感のある業務体制を実現します。





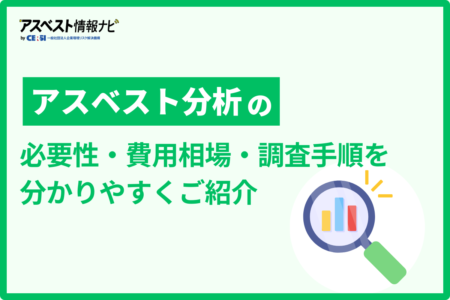
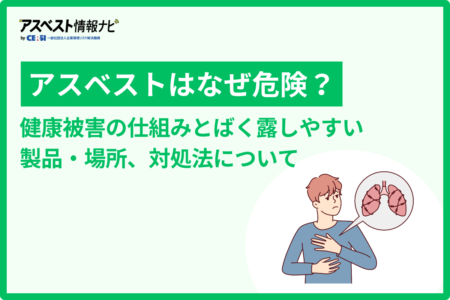











_20250214.png)
