アスベスト分析費用の相場はいくら?必要性・方法・補助金を一挙解説
- 最終更新日:

本コラムでは、解体・改修工事に欠かせないアスベスト分析の基本と実務上の判断ポイントを整理します。 ・アスベスト分析が必要となる背景と、事前調査だけでは判断できないケース ・分析方法の種類と選定時に押さえておくべき実務上の考え方 ・分析費用の相場感と、コストを抑えるための現実的な工夫 「みなし対応」と比較したときに、なぜ分析が結果的に合理的な選択になるのかを元請視点で解説します。
アスベスト分析とは
元請業者が解体・改修工事を行う際には、着工前に建材にアスベストが含まれているかどうかを確認する必要があります。
アスベスト分析とは、採取した建材試料を専門の分析機関に依頼し、その成分を科学的に調べる工程です。
日本では2006年9月1日以降、0.1重量%を超えるアスベストを含む製品の製造・輸入・使用が全面的に禁止されました。
しかし、2006年9月1日以前に着工された建物には、断熱材や保温材、吹付材、スレート板などにアスベストが含まれている可能性があります。
現場での事前調査では、目視や設計図書の確認だけでは判断が難しい場合が多く、その際にアスベスト分析が必要になります。
この分析結果は、工事計画の立案や適切な除去・封じ込め方法の選定に直結するため、元請業者にとって重要な判断材料となります。
アスベスト分析が必要な理由
元請業者がアスベスト分析を行う主な理由は、安全管理と工費削減の2つです。
第一に、安全管理の観点では、アスベストは吸入すると健康被害を引き起こす可能性があるため、工事従事者や周辺住民の安全を確保する必要があります。
分析により含有の有無を明らかにすることで、石綿有の場合、石綿の種類に応じて必要な保護具や作業方法を事前に準備できます。
第二に、工費削減の観点では、分析の結果「石綿なし」と判明することで、飛散防止にかかわる費用や、産業廃棄物処理にかかるコストを削減することができます。
石綿を含む産業廃棄物は通常、埋め立てが必要になりますが、埋め立て地の許容量の関係もあり、ほかの処理に比べてコストがかかります。
特に石膏ボードは石綿有とみなして進める場合、管理型の埋め立て許可のある処分業者が少なく、産廃処理費用が高くなりがちです。
しかし、石膏ボードは分析結果が石綿なしで出ることが多く、普通産廃で処理ができればリサイクルもできるため、分析調査を行うことが産廃処理費用の削減につながります。
石綿ありとみなして対応をとった場合は石綿対応・産廃処理費用が高額になる可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためにも、分析は不可欠です。
アスベスト分析の方法とは
元請業者が実施するアスベスト分析は、大きく分けて2つのステップで進みます。
試料採取
有資格者が現場で建材の一部を切り取り、密閉容器に入れて分析機関に送ります。採取の際には飛散防止措置を講じ、周囲への影響を最小限に抑えます。
分析機関による分析
分析機関による分析方法は「定性分析」と「定量分析」の二つがあります。
・定性分析……建材にアスベスト(石綿)が含まれているかどうかを調べる
・定量分析……アスベストの含有濃度を調べる
さらに、それぞれ次の手法が用いられます。
<定性分析>
①定性分析方法1(偏光顕微鏡法)「JIS A 1481-1」
偏光顕微鏡分析(PLM):光の偏光特性を利用してアスベスト繊維を確認する方法。比較的安価で迅速ですが、微細な繊維の判別が難しい場合があります。
②定性分析方法2(X 線回折分析法・位相差分散顕微鏡法)「JIS A 1481-2」
X線回折分析(XRD):結晶構造を調べることで種類を特定する方法。複数の手法と併用されることが多いです。
位相差顕微鏡分析(PCM):光学的手法で繊維の数をカウントしますが、種類までは特定できません。
③定性分析方法3(電子顕微鏡法)
透過型電子顕微鏡分析(TEM):高精度な分析が可能で、極細の繊維や種類まで特定できますが、費用と時間がかかります。
定性分析方法1(偏光顕微鏡法)あるいは定性分析方法2(X 線回折分析法・位相差分散顕微鏡法)によって分析した結果、アスベストの確認が難しいときは電子顕微鏡によるアスベスト繊維の同定等が推奨されています。
<定量分析>
①定量分析方法1(X 線回折分析法)「JIS A 1481-3」
②定量分析方法2(偏光顕微鏡法)「JIS A 1481-4」
工事規模や建材の種類、必要な精度によって、採用する分析方法が異なります。
アスベスト分析の方法を選定する際には、単に精度や費用だけでなく、分析目的や工期の制約も考慮することが重要です。
例えば、工期が迫っている現場では、結果が早く得られる定性分析方法1が有効な場合があります。
一方で、公共工事や大規模改修など、精度を最優先する場面では定性分析方法3が選ばれることが多く、複数手法を併用するケースもあります。
また、分析結果の信頼性を確保するためには、分析機関の選定も欠かせません。
厚生労働省や環境省が示すマニュアルに準拠しているか、有資格者が複数人所属しているかといった点を確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
結果報告書には、使用した分析手法や測定条件、判定基準が明記されるため、元請業者はこれらの内容を把握し、発注者や関係者に説明できる体制を整えておく必要があります。
さらに、試料採取時の管理も重要です。
採取した試料が混入や紛失を起こすと、再採取による工期遅延や費用増加のリスクが生じます。
採取箇所の写真記録やラベル管理、保管方法の徹底は、分析精度だけでなく現場管理全体の信頼性向上にもつながります。
加えて、分析結果がアスベスト含有「あり」と判定された場合、その後の工事計画や作業手順が大きく変わる可能性があります。
除去作業の実施や届出書類の追加作成など、元請業者の業務負担が増えるため、分析段階からこれらの変化を見越して準備しておくことが望ましいです。
このように、アスベスト分析の方法選定と運用は、単なる試験依頼ではなく、工事全体の安全性・法令遵守・工程管理に直結する重要なプロセスといえます。
元請業者としては、分析精度、納期、コストのバランスを見極めつつ、適切な方法と信頼できる分析機関を選定することが、円滑な工事進行の鍵になります。
アスベスト分析費用の相場
アスベスト分析費用は、試料数や分析方法によって変動します。元請業者が依頼する場合、一般的な相場は以下の通りです。
- 定性分析方法1 偏光顕微鏡分析(PLM):1試料あたり 15,000〜25,000円程度
- 定性分析方法2 X線回折分析(XRD):1試料あたり 20,000〜35,000円程度
- 定性分析方法3 透過型電子顕微鏡分析(TEM):1試料あたり 25,000〜40,000円程度
試料数が多い場合や、至急対応を依頼する場合には割増料金が発生することがあります。
また、試料採取費用や、報告書作成費用が別途必要な場合もあります。
全体として、1件の工事で必要な分析費用は数万円から十数万円になるケースが多く見られます。
アスベスト分析費用を見積もる際には、単純に分析単価だけで判断するのではなく、工事の規模や建材の種類、分析の目的を含めて総合的に検討することが重要です。
例えば、複数階建ての建物や広範囲に及ぶ改修工事では、採取箇所が増える傾向にあり、その分、分析費用が膨らみます。
また、現場によっては同じ種類の建材が複数箇所に使用されている場合もありますが、採取位置や劣化状況によって含有率が異なる可能性があるため、
同一建材の範囲の判断や採取場所の選定、採取検体数の判断には慎重さが求められます。
費用面で注意したいのは、至急対応の割増料金です。
工期が迫っている現場では、通常より短納期で分析結果を求めるケースがありますが、この場合は1試料あたり数千円〜1万円程度の追加料金が発生することがあります。
元請業者としては、工期に余裕を持ったスケジュールを組むことで、こうした割増コストを抑えることが可能です。
さらに、採取費用や報告書作成費用も見逃せません。
採取は有資格者による立ち入りや足場設置が必要になる場合があり、現場の条件によっては費用が上振れすることがあります。
報告書についても、法令で求められる記載事項や写真添付、自治体への届出用フォーマットへの対応など、内容が充実するほど作成コストが増える傾向があります。
長期的なコスト削減を考えるなら、信頼できる分析機関と継続的に取引することで、単価交渉やセット割引が受けられる場合があります。
また、一部の自治体ではアスベスト分析費用の補助制度を設けているため、発注者(施主)に補助金情報を事前に案内することで、工事全体の予算負担を軽減できます。
最終的に、分析費用は「安全確保」と「法令遵守」のための必要経費であると同時に、「みなし」での工事と比較してコスト削減できる一つの手段と捉えることが重要です。
元請業者が適切な費用感を理解し、発注者に透明性のある説明を行うことで、信頼性の高い工事運営につながります。
アスベスト分析関連の補助金について
自治体によっては、アスベスト分析費用の一部を助成する制度があります。
元請業者が発注者(施主)に説明する際、補助金制度の有無を事前に調べて案内することで、工事全体の予算計画が立てやすくなります。
補助対象とする石綿(アスベスト)は、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。また、以下のように概要が定められています。
- 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物
- 補助内容:吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用
- 国の補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)
補助金制度はすべての自治体にあるわけではなく、制度がない自治体もありますので事前に確認する事が望ましいといえます。
分析依頼から書類作成・電子報告までアスベスト対応を見える化
アスベスト対応業務では、いまだにFAXやメールでの分析依頼、手書きでの書類作成、煩雑な報告準備といったアナログ業務が根強く残っています。
こうした手作業が時間を奪い、本来の現場作業に支障をきたすことも珍しくありません。
「アスベストONE」は、分析から書類作成・報告までをクラウドで完結させ、現場の業務効率化を支援するサービスです。
スマホやタブレットからでも簡単に分析依頼ができ、進捗状況もログインするだけでリアルタイムに確認可能。
受け入れから分析結果までの流れが“見える化”されるので、現場・事務所・協力会社の間で常に最新情報を共有できます。
書類作成は必要な情報をシステムに入力するだけで自動で生成され、作業計画書、報告書、掲示用の看板PDFまで一括で出力可能。
記載ミスのリスクを減らし、工数も削減できます。
さらに、出力したCSVデータをアップロードするだけで、GビズID対応の電子報告がスムーズに完了。
これまで何度も工事情報を入力していた手間やヒューマンエラーを大幅に削減できます 。
クラウド上で進捗管理や情報共有ができるため、確認作業や手戻りも最小限に抑えられ、スピーディーで無駄のない業務が実現します。
まずは無料の個別相談をご利用ください。現場の状況や業務フローをヒアリングし、最適な活用方法をご提案します。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)

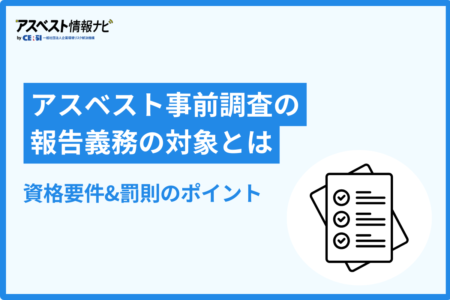

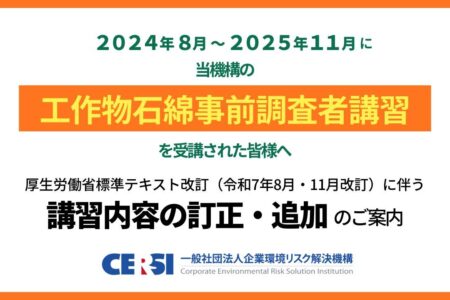











_20250214.png)
