アスベストの危険性と人体への影響とは?使用場所の見分け方から法的補償まで
- 最終更新日:

本コラムでは、アスベストの危険性と人体への影響を軸に、使用されてきた場所の見分け方から、
万一の際の法的補償制度までを整理します。 ・なぜアスベストが人体に深刻な健康被害をもたらすのか ・住宅や建築物のどの部位に使われていた可能性があるのか ・曝露被害が発生した場合に適用される補償制度と法的責任 現場対応だけでなく、元請として説明責任を果たすために押さえておくべき全体像を解説します。
アスベストはどのような場所に使われていた?
アスベストは20世紀を通じて世界各国で広く利用されていました。
その理由は、他の天然素材や人工素材では代替しにくい特徴を兼ね備えていたからです。
具体的には、燃えにくい耐火性、熱を通しにくい断熱性、長期間劣化しにくい耐久性、さらには摩擦や酸に強いという性質を持っています。
しかも天然に産出し、コストも低かったため、建築資材や工業製品の中に幅広く取り入れられていったのです。
特に建築分野においては、外壁や屋根、内装材などに大量に使用されました。
住宅の屋根に敷かれていたスレート板、外壁に張られた窯業系サイディング、学校や公共施設の天井や柱に吹き付けられた耐火材、オフィスビルや商業施設の床に使われたビニル床タイルなど、身近な建材の多くにアスベストが混入していました。
さらに配管やボイラーの周りに巻かれる保温材、煙突の断熱材、自動車のブレーキパッドなどにも含まれていたため、私たちの生活空間のあらゆる場所で利用されていたと言えます。
こうしてアスベストの使用が広がった背景には、国の建築基準や社会的な需要もありました。
高度経済成長期の日本では大量の住宅建設が求められ、安価で大量生産が可能な建材が必要とされていました。
その要望に応えたのがアスベスト含有建材であり、工務店や建設業者にとって使いやすく、発注者にとっても低コストで耐久性の高い選択肢となったのです。
結果として、1970年代から1990年代にかけて建築された住宅やビルの多くにアスベストが採用され、今なおその建物は各地に存在しています。
しかし、その有用性の裏で健康被害が次第に明らかとなり、2000年代には社会問題として強く認識されるようになりました。
これを受けて規制は段階的に強化され、1975年には特定の吹付け材の使用禁止が始まり、その後は使用範囲が段階的に制限され、最終的に2006年9月1日以降に着工された建物では、アスベストの使用が全面的に禁止されています。
とはいえ、それ以前に建てられた建物にはアスベスト含有建材が残っている可能性が高く、現在でも住宅地や市街地の解体工事でしばしば問題になります。
こうした背景を踏まえ、現在では解体や改修を行う際に事前調査が法律で義務付けられています。
事前調査の実施責任は元請業者等の施工業者にあり、そのため、解体・改修工事を計画する発注者(施主/工事の注文者)は、調査が適切に行われているかを確認することが求められます。
この調査によってアスベストの有無を確認し、含まれている場合には適切な飛散防止措置を講じなければなりません。
調査や分析は有資格者や分析機関が行うものであり、建築物に関わるすべての関係者が責任を持って対応することが求められます。
アスベストの危険性について
アスベストの危険性は、繊維が非常に細かく、吸入されやすい点にあります。
肉眼では見えない微細な繊維が空気中に浮遊し、呼吸によって肺に取り込まれると、長期間にわたり体内にとどまります。
この性質が健康被害の大きな要因とされています。
通常、アスベストは建材の内部に固められているため、使用されているだけでは直ちに危険ではないといわれています。
しかし解体や改修によって建材が破損すると繊維が飛散するおそれがあり、その際に作業従事者や周辺住民が曝露するリスクが高まります。
そのため法律では、工事の前に必ず有資格者による事前調査を行い、アスベストが含まれている場合には飛散防止措置を徹底することが求められています。
アスベストにおける人体への影響とは?
アスベストが人体に及ぼす影響は、主に呼吸器系に集中しています。
繊維は極めて細かいため肺の奥深くまで到達しやすく、一度吸入されると体外に排出されにくいのが特徴です。
時間の経過とともに肺組織に炎症や線維化を引き起こし、呼吸機能を低下させる原因となります。
曝露した人すべてが発症するわけではありませんが、喫煙との相乗効果などによってリスクが高まることが指摘されています。
しかも影響が現れるまでに20年から40年程度の長い潜伏期間を経ることも多く、曝露したことを忘れた頃に病気が発症するケースが少なくありません。
そのため「静かな時限爆弾」と表現されることもあり、人体への影響は非常に深刻とされています。
元請業者としては、工事現場における粉じん管理を徹底し、作業従事者や周辺住民を曝露リスクから守ることが社会的責任であるといえます。
アスベストが原因で発症する可能性のある病気
建物所有者や元請業者にとって、アスベストの健康影響を理解しておくことは重要です。
アスベスト曝露に関連して報告されている代表的な疾病には以下があります。
石綿肺
長期間にわたりアスベスト繊維を吸入すると、肺組織が硬く線維化していきます。
これにより呼吸がしづらくなり、進行すると慢性的な呼吸不全に至ることもあります。
悪性中皮腫
胸膜や腹膜など、臓器を覆う膜に腫瘍が発生する病気で、アスベスト曝露との因果関係が特に強く認められています。
発症後は進行が速く、治療が難しいのが特徴です。
肺がん
アスベストを吸入することで肺がんの発症リスクが高まるとされています。
特に喫煙と組み合わさることで、危険性がさらに増大することが指摘されています。
その他の疾患
胸膜肥厚斑やびまん性胸膜肥厚など、呼吸機能に影響を及ぼす疾患も報告されています。
これらは必ずしも重篤ではありませんが、進行すると呼吸に支障をきたす場合があります。
アスベスト被害の法律や補償について
建設現場や工場などでアスベストに長期間曝露し、病気を発症した作業従事者は労災補償保険の対象となります。
対象疾病は厚生労働省が定めており、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償などを受けられます。
比較的スムーズに補償につながるケースが多いのも特徴です。
一方で、作業服に付着した繊維を家庭に持ち込むことで起きる「家庭内曝露」や、周辺住民が工場や工事現場からの粉じんにさらされた「環境曝露」も問題となってきました。
こうした労災対象外の人々を救済するために創設されたのが、石綿健康被害救済制度 です。
環境再生保全機構が窓口となり、医療費の自己負担分の補償、療養手当、特別遺族弔慰金、特別葬祭料などが支給されます。
また、元請業者や下請業者が解体や改修工事を進める際には、事前調査と報告、飛散防止措置の徹底が法律で義務付けられています。
これを怠った場合や虚偽報告を行った場合には、安衛法・大防法に基づき 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 が科される可能性があり、社会的信用を失うリスクも伴います。
つまり、補償制度と法令による規制は、被害を受けた人々を守ると同時に、新たな曝露を未然に防ぐための両輪として機能しています。
すでに被害を受けた方を救済しつつ、社会全体でアスベストの危険を繰り返さない仕組みを築くことが重要です。
アスベストONEで書類作成・進捗管理を効率化し、法令遵守も安心サポート
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)対応業務に必要な書類作成と進捗管理を、クラウド上でワンストップで支援するサービスです。
これまで手間と時間のかかっていた作業を効率化し、現場との情報共有までを一括でカバーします。
入力項目に沿って進めるだけで、事前調査報告書や作業計画書、現場掲示用の看板PDFなどを自動で生成。
法令に準拠したフォーマットで出力されるため、記載漏れやミスを防ぎます。
さらに、GビズIDに対応した電子報告にも対応しており、出力したCSVデータを一括アップロードするだけで行政への報告が完了するため、手入力による負担やミスを軽減できます。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく下請け業者や協力会社とも最新情報を簡単に共有可能です。
進捗状況や全体工程も見える化され、手戻りの少ないスムーズな業務連携を実現します。
EMSでは、現場の状況や課題をヒアリングしたうえで、最適な運用方法を無料相談でご案内しています。
業務負担を軽減し、確実に法令対応できる体制をぜひアスベストONEで実現してください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)

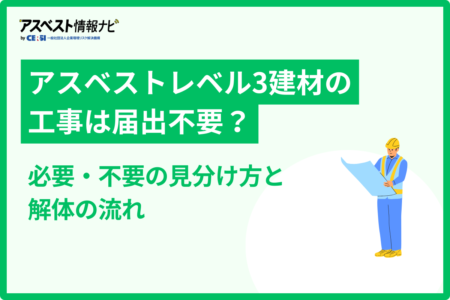
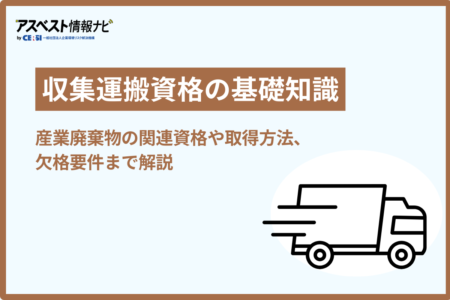
にアスベストは含まれる?-450x300.png)











_20250214.png)
