アスベストレベル3とは?レベル3の対象建材や必要な対策
- 最終更新日:

アスベスト含有建材は、その飛散性に応じてレベル1からレベル3に分類されています。
中でも「レベル3」は、通常の使用状態では比較的粉じんが飛散しにくい「非飛散性建材」とされています。
しかし、切断や穴開け、撤去といった建材に損傷を及ぼす作業を行う際には、やはり飛散リスクが伴うため、適切な知識と対策が不可欠です。
本記事では、レベル3に分類される建材の具体例や使用場所、作業時に必要な措置、そしてレベル1・2との違いをわかりやすく解説します。
施工業者として現場の安全性を確保し、法令を遵守するために、レベル3建材への正しい理解が求められています。
アスベストレベル3の定義と対象建材(Pタイル、ケイ酸カルシウム板第1種など)
アスベストレベル3とは、アスベストを含む建材のうち、通常の使用状態では比較的飛散性が低い建材を指します。
厚生労働省が定めるアスベスト作業における粉じん濃度の分類において、最も飛散性が低いレベルとされており、主に非飛散性建材が該当します。
具体的な対象建材としては、Pタイル(ビニル床タイル)、ケイ酸カルシウム板(第1種)、アスファルト防水材、スレート板、窯業系サイディングなどの
アスベスト含有成形板のほか、セメント円管、パッキン、接着剤などが挙げられます。
加えて、建築用仕上塗材や下地調整剤についても、レベル3相当として取り扱われます。
これらの建材は、切断・穿孔・研磨などの加工を行わない限り、空気中への飛散リスクは比較的低いとされています。
ただし、飛散性が低いとはいえ、解体・改修工事の際には粉じんの発生が避けられない場面もあるため、適切な事前調査と飛散防止措置が必要です。
さらに重要なのは、レベル3建材であっても、劣化や破損が進んでいる場合には、アスベスト繊維が表面に露出しやすくなり、飛散リスクが高まる点です。
特に、長期間使用されてきた古い建物では、表面の摩耗やひび割れなどが原因で、アスベストが意図せず露出していることがあります。
また、建材の加工や解体時には、工具による振動や衝撃によって、微細な繊維が飛散する可能性もあるため、飛散性が「低い」からといって油断してはなりません。
そのため、レベル3建材を含む建物で改修や除去作業を行う場合は、有資格者による事前調査が必須となります。
建材の種類や使用状況を適切に把握した上で、作業計画を立て、必要に応じた湿潤化や養生、防じんマスクの着用などの対策を講じることが求められます。
こうした事前準備の有無が、作業者の健康と周辺環境の安全を大きく左右することになります。
アスベストレベル3建材の使用場所と必要な対策
アスベストレベル3に分類される建材は、住宅や商業施設、工場、学校などあらゆる建物で広く使用されてきました。
特にPタイルは、床仕上げ材として公共施設やオフィスビル、病院などに数多く用いられており、耐久性とコスト面の理由から昭和後期に多用されました。
また、ケイ酸カルシウム板(第1種)は、耐火・断熱性能に優れていることから、天井材や壁材、ダクトの覆いなどとして幅広く使用されました。
これらの建材は表面の外観のみではアスベスト含有の有無を判断できないため、改修や撤去時には事前調査が欠かせません。
レベル3建材を扱う作業では、作業場所における粉じん飛散を最小限に抑える対策が求められます。
具体的には、湿潤化による粉じん抑制、低振動工具の使用、作業区域の隔離措置、作業員の保護具(防じんマスク、作業衣または保護衣)の着用などが必要です。
また、廃棄物の密閉梱包および飛散防止のための袋詰めも適切に行う必要があります。
さらに、作業区域の出入り口には明確な警告表示を設け、関係者以外の立ち入りを防止する措置も重要です。
作業中に飛散したアスベスト粉じんが周囲に拡散するのを防ぐため、局所排気装置の設置や簡易陰圧の導入も有効とされています。
特に、屋内での作業や換気の悪い場所では、これらの対策が作業者および建物利用者の健康リスク低減に直結します。
加えて、レベル3建材は非飛散性であることから、一般的には湿潤化や隔離などの簡易な措置で対応可能ですが、作業の内容や状態によっては、より厳格な管理が求められるケースもあります。
たとえば、石綿含有シール材(パッキン、ガスケット等)が劣化・固着している場合には、
除去作業に際して集じん・排気装置(負圧隔離)やグローブバック方式による隔離が必要になるケースがあります。
作業後には、区域内の清掃を徹底し、使用した保護具や廃棄物の処理についてもアスベスト関連法令に準拠した方法で行う必要があります。
これにより、現場の安全性を保ちつつ、周辺環境への影響も最小限に抑えることができます。
元請業者や現場監督者は、作業者への安全教育と適切な管理体制の構築を通じて、アスベスト対策の実効性を確保することが求められます。
アスベストレベル3の除去作業に必要な資格・講習要件とは
アスベストレベル3の建材を取り扱う作業においても、一定の法的資格要件が存在します。
厚生労働省が定める「石綿作業主任者技能講習」は、アスベスト含有建材の除去作業現場における主任者配置義務に対応するための講習であり、レベル1・2・3を問わず必要とされます。
また、2022年4月の石綿則改正により、アスベスト含有建材を取り扱う作業については、作業従事者全員に「特別教育」の受講が義務化されました。
この教育は、レベル3建材に対しても適用されており、作業前に適切な知識と手順を習得することが求められます。
さらに、作業の規模や内容によっては、労働基準監督署への届出が必要となるケースもあるため、施工前には法的要件の確認を徹底する必要があります。
アスベストレベル3における作業手順と安全管理策
レベル3建材の作業では、飛散のリスクが低いとはいえ、施工手順を誤るとアスベスト粉じんが飛散する恐れがあるため、作業手順と管理策が極めて重要です。
作業開始前には、対象建材の種類、施工位置などを調査し、作業計画書を作成します。
作業中は湿潤化処理を行い、可能な限り乾燥状態での切断や研磨を避けることが推奨されます。
電動工具を使用する場合は、集じん装置付きの低振動タイプを選ぶことで飛散を最小限に抑えることが可能です。
また、作業エリアは他の区域から隔離し、警告標識を設置することで第三者の立ち入りを防止します。
作業後は、作業区域内を清掃し、発生した廃材はアスベスト含有廃棄物として法令に基づいた方法で適切に処分します。
さらに、作業者の防護具はその場で脱着し、外部への持ち出しを防ぐための洗浄・廃棄手順を徹底します。
アスベストレベル1・2との違いと比較ポイントの整理
アスベスト建材は、飛散性の程度によってレベル1(高)、レベル2(中)、レベル3(低)に分類されています。
レベル1は吹付けアスベストなど、非常に飛散性が高い建材であり、作業にあたっては密閉空間での隔離、負圧除じん装置の設置、全面形防護具の着用など、極めて厳重な管理が求められます。
レベル2は、成形板や断熱材など飛散性は中程度で、隔離空間内での湿潤化処理や簡易陰圧措置などの対策が必要です。
これに対してレベル3は、前述のとおり非飛散性の建材が対象で、比較的簡易な管理措置で対応可能とされています。
ただし、あくまで「通常の使用状態で飛散しにくい」という分類であるため、切断や破砕といった作業時には他のレベルと同様、十分な注意と管理が求められます。
したがって、レベル3であっても過信せず、作業ごとに適切な対策を講じることが必要です。
アスベストONEで分析依頼から書類作成・電子報告までを効率化
「アスベストONE」は、クラウド上での分析依頼から進捗状況の確認、書類作成までをワンストップでサポートするクラウドサービスです。
システムに沿って入力するだけで、法令に準拠した作業計画書や報告書を自動で生成できるため、これまで手間のかかっていた書類作成業務を大幅に効率化できます。
さらに、CSV形式で一括出力したデータはGビズIDと連携して電子報告が可能なため、複雑な行政手続きもスムーズに対応できます。
また、書類の作成状況や進捗がクラウド上で“見える化”されており、現場・事務所・協力会社の間で常に最新情報を共有・確認できます。
これにより、手戻りや確認作業を最小限に抑えた、無駄のない連携が可能になります。
EMSでは、アスベスト対応に関する無料の個別相談も承っております。
専門スタッフが現場の状況を丁寧にヒアリングし、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内いたします。
まずは分析からはじめて、手間とコストを削減できる実感をぜひお確かめください。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
_20250217_すず-1024x154.jpg)

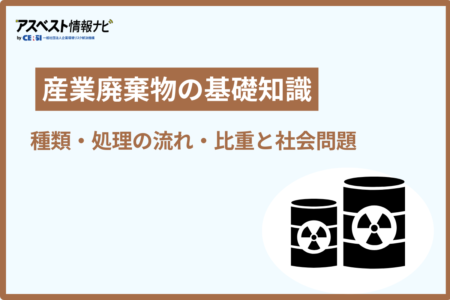













_20250214.png)
