アスベスト含有建材の見分け方|目視・資料・分析による建材判別の基本
- 最終更新日:
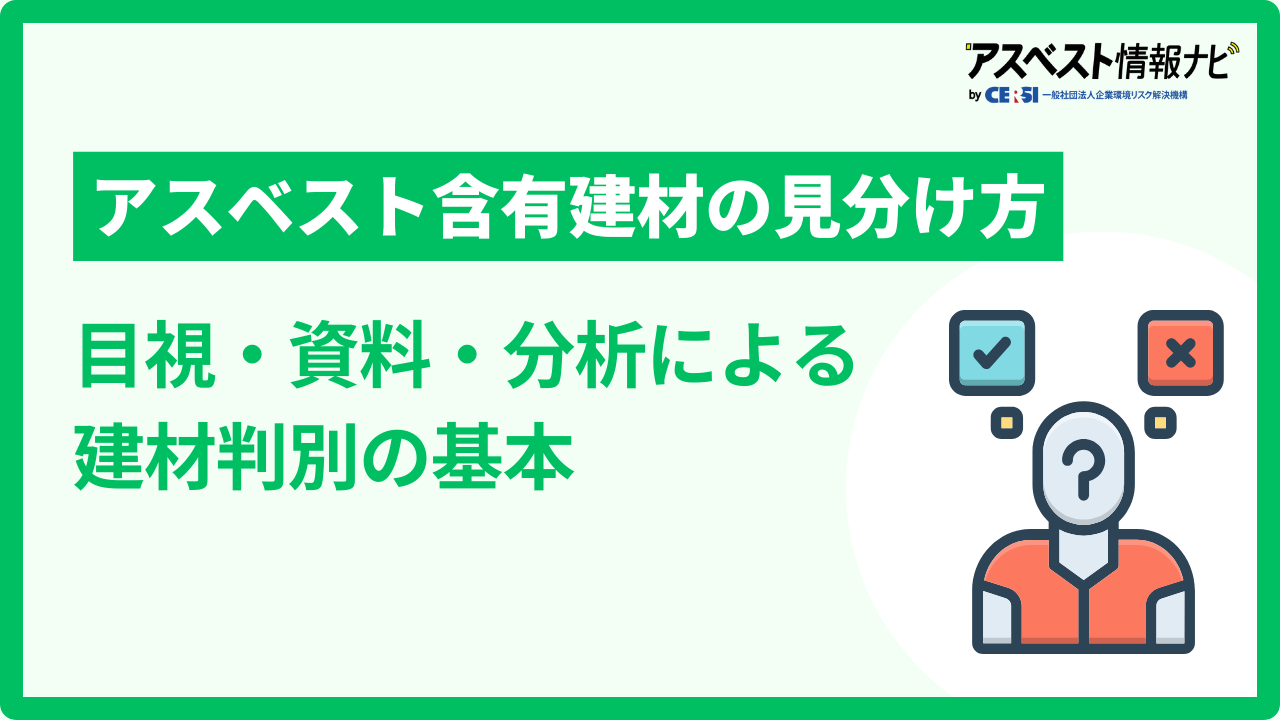
解体・改修工事において、アスベスト含有建材を正しく見分けられるかどうかは、
工事の安全性だけでなく、法令遵守やコスト管理にも直結する重要なポイントです。
しかし実務の現場では、「見た目」「築年数」「過去の経験」だけで判断してしまい、
結果として行政指導や工事中断につながるケースも少なくありません。
・外観や施工年代から、どこまでアスベスト含有の可能性を判断できるのか
・建材の用途ごとに注意すべき、アスベスト使用の典型パターン
・図面・メーカー情報・分析調査をどう使い分けるべきか
アスベスト含有の有無は、目視や経験則だけで確定できるものではありません。
本コラムでは、外観・施工年代・建材用途といった基本的な見分け方の考え方を整理したうえで、
自己判断の限界と、分析調査を含めた実務上の正しい判断プロセスを解説します。
アスベスト含有建材の見分け方の基本|外観・施工年代・建材用途の傾向
発注者(施主/工事の発注者)にとって、解体・改修等工事の際に重要となるのが、使用されている建材にアスベストが含まれているかどうかの判別です。
特に2006年9月1日以前に着工された建物は、アスベスト含有の可能性が高く、適切な事前調査が求められます。
見分けの基本としてまず注目すべきは、施工年代です。
前述のとおり、2006年以前の建物ではアスベスト含有リスクが高く、特に1970~1990年代に多く使用された建材(スレート、ケイ酸カルシウム板、Pタイル、吹付け材など)は要注意です。
これらの建材は、見た目のみで含有有無を判別することはできません。
また、建材の用途にも着目する必要があります。
断熱材、耐火材、防音材などの機能を持つ建材は、性能を高める目的でアスベストが使用されていたケースが多く、リスクが高いです。
外壁材や天井材のほか、配管周りの保温材なども該当します。
建材ごとの特徴とアスベスト調査の注意点
建物の解体や改修に伴うアスベスト対策は、元請業者にとって重要な法令遵守項目の一つです。
特にアスベスト含有建材は、建材の種類や施工年代によって見た目では判別がつかない場合も多く、誤った判断が事故や行政指導に直結するリスクをはらんでいます。
判断を誤れば、現場作業の中断や遅延、報告書の修正、周辺住民からのクレーム対応など、さまざまな影響が生じるため、正しい知識と慎重な対応が求められます。
石綿含有の有無は見た目で判断できない
建材にはさまざまな種類がありますが、同じ形状・用途でも石綿を含むものとそうでないものが存在します。
たとえば、スレート屋根材は1970年代から普及しましたが、2000年頃までは石綿含有品が流通していました。
見た目はどちらもほぼ同じであり、表面の凹凸や色、厚みによって判別することは困難です。
ケイ酸カルシウム板についても同様で、建物の内装や天井材として広く使われてきたものですが、含有品と非含有品を外見のみから見分けるのは不可能です。
Pタイルも1975年以前のものには高確率で石綿が含まれており、現場での目視だけでは含有有無を判定できません。
このように、アスベスト含有の有無は専門的な知識や資格があっても現場の目視だけで判断するのは極めて難しく、正確な調査には法令に基づいた手順と分析が必要です。
そのため、調査は必ず石綿調査の有資格者が担当し、必要に応じて分析機関との連携も含めた適切なプロセスを踏むことが求められます。
設計図書類やメーカー情報の活用方法
アスベスト含有の可能性を事前に把握するためには、現場確認だけでなく、建物に関する図面や記録、メーカー情報といった文書資料の活用が有効です。
調査の効率を高め、「みなし」判定による無駄な産廃処理コストを抑えるためにも、既存の情報からヒントを得る姿勢は欠かせません。
ただし、「発注者側で図面が保管されていない」「メーカー情報が公開されていない」等、すべての現場で資料が確実に残っている保証はありません。
こうした場合、分析調査によりアスベスト含有有無の判定を行うことも有効性の高い手段です。
図面や製品情報による確認のポイント
建物の設計図書や竣工図、仕様書などを確認することで、使用されている建材名やメーカー名を特定できる場合があります。
メーカーと建材名が分かれば、厚生労働省や環境省が公開している「アスベスト含有建材データベース」と照合することで、含有可能性の初期判定が可能となります。
また、建材自体に刻印されている型番やメーカー名を基に、製造元のカタログを参照することで、製造時期や成分構成を確認できるケースもあります。
過去の製品資料を参照することで、当該建材が含有品であるかの手がかりが得られる可能性があります。
ただし、こうした情報が現場に完全な形で残されていることは稀です。
改修歴のある建物であれば、図面と現場の仕様が異なるケースも多いため、書面情報の過信は危険です。
あくまで補助的な情報として捉え、現場での確認とあわせて活用するのが現実的な対応となります。
元請業者としては、建材の確定情報が得られない場合は、初めから分析を前提とした判断を行うことが、スムーズかつ安全な対処法といえます。
自己判断の限界と分析機関による確実なアスベスト分析
アスベストの有無を判断する際に、現場の経験則や建材の見た目、施工年代などに頼ることは少なくありません。
しかし、これらの方法には明確な限界があり、見落としや誤判定が発生する恐れがあります。
最終的な判断にあたっては、信頼性の高い分析結果に基づく対応こそが、安全性とコンプライアンスを両立する唯一確実な手段となります。
特に元請業者にとっては、適切な判断が自社の信頼を守る鍵でもあるのです。
目視判別と分析の精度の違い
外観や施工年代、用途情報などを基にした判断は、あくまで可能性に基づく予測に過ぎません。
建材の種類や劣化具合によっては判断が難しいだけでなく、誤判定による法令違反にもつながります。
成分分析では、建材から採取した試料を専門機関に持ち込み、偏光顕微鏡やX線回折装置などを使って精密に検出を行います。
定性分析によるアスベスト含有有無の判定に加えて、定量分析を併用することにより、0.1重量%以上のアスベストが含まれているかどうかを明確に判定できます。
元請業者としては、分析調査の活用により確実な根拠を得ることができ、行政報告や住民への説明責任においても大きな信頼を得られます。
2025年4月より、株式会社EMSが提供する「アスベストONE」でも分析依頼機能を実装しており、書類作成とあわせて分析依頼を一括で行える体制を整えています。
書類作成と分析調査の両方をアスベストONEのシステム内で完結できることで、二重のやり取りや情報伝達ミスを防ぎ、作業の効率化とリスク管理の向上を実現します。
見た目や資料情報に頼らず、分析調査結果という揺るぎない根拠に基づく判断が今後ますます重要となります。
判別ミスによって生じる行政指導リスクとその回避策
不適切な判別によってアスベスト含有建材を見逃した場合、改修・解体工事中に飛散事故が発生するリスクがあります。
これは労働安全衛生法違反に該当し、元請業者に対しては労働基準監督署からの指導や改善命令が出されることもあります。
さらに、行政報告の内容に誤りがあった場合には、発注者や周辺住民からの信頼を損ね、契約トラブルや損害賠償リスクにも発展しかねません。
現場作業の円滑化と法令順守のためにも、目視判断のみに頼るのではなく、確実な分析に基づいた調査結果の文書化が求められます。
アスベストONEで分析依頼から書類作成・電子報告までを効率化
「アスベストONE」は、クラウド上での分析依頼から進捗状況の確認、書類作成までをワンストップでサポートするクラウドサービスです。
システムに沿って入力するだけで、法令に準拠した作業計画書や報告書を自動で生成できるため、これまで手間のかかっていた書類作成業務を大幅に効率化できます。
さらに、CSV形式で一括出力したデータはGビズIDと連携して電子報告が可能なため、複雑な行政手続きもスムーズに対応できます。
また、書類の作成状況や進捗がクラウド上で“見える化”されており、現場・事務所・協力会社の間で常に最新情報を共有・確認できます。
これにより、手戻りや確認作業を最小限に抑えた、無駄のない連携が可能になります。
EMSでは、アスベスト対応に関する無料の個別相談も承っております。
専門スタッフが現場の状況を丁寧にヒアリングし、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内いたします。
まずは分析からはじめて、手間とコストを削減できる実感をぜひお確かめください。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)

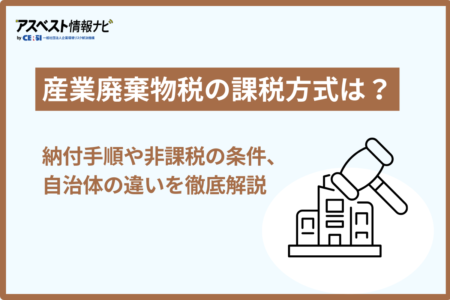













_20250214.png)
