木造一戸建て住宅の解体で知るべきアスベスト対応の費用と対策|アスベスト含有リスクや解体フローを解説
- 最終更新日:

発注者(施主/工事の注文者)が木造一戸建て住宅の解体を検討する際、見落としてはならないのがアスベスト(石綿)に関するリスクです。
かつてアスベストは耐火性・断熱性・防音性に優れた建材として、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物に限らず、木造住宅にも広く使用されていました。
特に昭和から平成初期にかけて建てられた住宅では、外壁材、天井材、屋根材、配管保温材などにアスベストを含む製品が使用されていた可能性があり、現在ではそれらの除去に関する法令対応が義務づけられています。
2006年にアスベストの使用が全面禁止されたとはいえ、それ以前に建てられた建物には含有建材が残っている可能性があり、
解体時には事前調査、分析、除去、適正処分といった手順を踏む必要があります。
その分、解体費用が増加することも珍しくなく、発注者としては正確な情報をもとに準備を進める必要があります。
本記事では、木造一戸建て住宅におけるアスベストの使用実態、健康リスク、費用相場、工事の流れ、対策までを詳しく解説します。
木造一戸建て住宅にはアスベストが含まれる?
木造一戸建て住宅においても、アスベストが使用されている可能性は十分にあります。
特に2006年9月1日以前に着工された住宅では、外壁のスレート材や屋根の波形スレート板、軒天や天井の化粧石膏ボード、内装材の一部に石綿を含む製品が使用されていた事例が多く報告されています。
また、給排水設備の保温材や床材の接着剤にもアスベストが使用されていたケースがあります。
鉄筋や鉄骨を使っていない構造だからといって、アスベストのリスクが低いと判断するのは誤りです。
アスベストは性質上、どのような構造の建物にも多様な用途で使用されていたため、単に木造一戸建て住宅であることを以ってアスベストが使用されていないと判断することはできません。
発注者は、解体、改修等の工事を行う場合には、原則として一般建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による調査により、アスベスト含有建材の有無を確認する事が法的義務となっています。
木造一戸建てのアスベストによる健康被害のリスク
木造住宅であっても、解体時にアスベストを含む建材が破砕・切断されることで、アスベスト繊維が飛散するおそれがあります。
これらの繊維は非常に微細で、目に見えない状態で空気中に浮遊するため、吸入した作業従事者や近隣住民に健康被害を及ぼす可能性があります。
代表的なアスベスト関連疾患には、中皮腫、肺がん、石綿肺があり、いずれも潜伏期間が数十年に及ぶという特徴を持っています。
石綿の健康被害は直ちに表れるものではないため、見落とされやすいリスクでもあります。
解体工事の際に適切な飛散防止措置を講じなければ、健康被害だけでなく、発注者が元請業者などとともに周辺住民等から損害賠償等の民事上の責任を問われる可能性もあります。
そのため、石綿障害予防規則および大気汚染防止法に基づき、アスベストが含まれている建材を扱う際は、
飛散防止措置、作業計画の策定、有資格者の配置、養生等の作業基準の順守、適切な廃棄物処理などが求められています。
発注者としては、調査段階からアスベスト含有建材がある場合には施工に際し様々な対応が必要であることを認識する必要があります。
木造一戸建てにおけるアスベスト解体の具体的な費用相場
木造一戸建て住宅の解体費用は、建物の規模や構造、立地条件などによって変動しますが、延床面積30坪前後(約100㎡)の住宅の場合、
アスベストが含まれていない通常の解体であればおおよそ80万〜120万円程度が相場です。
しかし、アスベスト含有が判明した場合、以下のような費用が追加で発生します。※あくまでも一例であり、諸条件により変動します。
事前調査・分析費用:1検体あたり約15,000〜30,000円(部位数により数万円〜十数万円程度)
届出・書類作成支援費用:約3万〜10万円
飛散防止養生・隔離費用:約10万〜50万円
除去作業(アスベスト種類・数量による):10㎡あたり約15万〜50万円
廃棄物の特別管理産業廃棄物処分費:重量・距離により加算
これらを合算すると、アスベスト除去込みの解体費用は100万〜300万円以上になるケースもあります。
とくに屋根材・外壁材に広範囲で使用されていた場合、仮設足場や解体手順の複雑化によってさらに費用が増加します。
発注者は、調査・見積もりの段階でこれらの項目を明確にしておくことが肝心です。
木造一戸建てにアスベストが含まれる場合の解体までの流れ
アスベストが含まれる木造住宅の解体は、通常の解体よりも多くの手順を踏む必要があります。
まず、建築物が2006年9月1日以前に着工されている場合、アスベスト含有建材が使用されている可能性があるため、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による書面及び目視での事前調査が必要となります。
建築物の新築着工日が2006年9月1日以降である場合には書面での調査のみでアスベスト含有建材が使用されていないと判断できますが、設計図書等での新築着工日の確認は必須であり、調査の記録も残す必要があります。
事前調査によりアスベストが含まれていないと断定できない建材については、アスベスト有とみなして取り扱う(みなし)か、サンプルを採取し、JIS規格に準拠した定性分析・定量分析を行います。
調査の結果、アスベスト含有建材が確認されたり、アスベスト有とみなして取り扱う建材が存在する場合には、
アスベスト含有建材のレベルに応じて法令で定められた対応を施工に際して順守する必要があります。
なお、アスベスト含有建材がない、との調査結果だった場合でも、解体時に調査結果を看板として掲示したり、解体面積が80㎡以上の場合には調査結果を行政に報告することが施工業者に義務付けられています。
アスベスト含有建材あり、またはみなしでの工事の場合、上記に加えて作業計画の策定を施工業者が行います。
また、木造一戸建て住宅の場合稀ですが、レベル1、2のアスベスト含有建材(吹付け材、保温材、耐火被覆材など)が使用されている場合には、
工事の14日前までに管轄する労働基準監督署、並びに自治体の大気汚染防止法窓口への届出が必要になります。
特に大気汚染防止法窓口への届出は発注者の名義で行うため注意しましょう。
次に、解体業者が飛散防止措置を施し、アスベスト含有建材の除去作業を行います。
作業中は有資格者(石綿作業主任者)の配置、ビニルシートでの養生等による隔離、粉じんの飛散を抑制するための湿潤化、必要な掲示物の掲示等が義務付けられており、作業記録の作成も必要になります。
除去後には発生したアスベスト含有の廃材を廃棄物処理法に基づいて処理しますが、
レベル1、2のアスベスト含有建材の場合には特別管理産業廃棄物である廃石綿等、
レベル3のアスベスト含有建材(石膏ボードやスレート、Pタイルなど)の場合には石綿含有産業廃棄物に該当し、
いずれの場合にも通常の建設産業廃棄物以上に厳しい管理を要し、処理の方法も限られるため処理費用が高くなります。
最後に、アスベスト含有建材の取り残しがないよう有資格者が現場を確認し、高性能真空掃除機等で清掃した上で作業報告書を発注者に提出して、アスベスト含有建材の除去作業は終了となります。
木造一戸建て住宅解体時のアスベスト対策
発注者が木造住宅解体時にアスベスト対策を講じるには、有資格者を配置しており、正確な調査を行える施工業者に工事を依頼することが最も重要といえます。
工費が安かったとしても必要なアスベストの事前調査や対策を行わない業者は法令違反のリスクがあり、発注者も責任を問われたり、最悪の場合飛散したアスベスト線維を吸引し健康被害をのリスクが生じかねません。
見積の中にアスベスト事前調査費用等が明確に示されている、信頼できる解体業者やアスベスト除去専門業者に依頼し、法令に則った計画・届出・養生・除去・報告の一連の流れを確実に実行してもらうことが必要です。
また、事前調査結果記録や届出書類の整備、作業看板の出力、報告書の作成といった各工程については、発注者としても状況を把握し、必要な準備を漏れなく進めることが重要です。
手続きの煩雑さを軽減するため、調査会社や施工会社と早期に相談し、役割分担と実施スケジュールを明確にしておくことが、法令違反のリスクを回避するポイントとなります。
さらに、自治体によってはアスベスト除去に関する補助金制度を設けている場合があり、費用の一部を助成してもらえる可能性があります。
制度は自治体により異なるため、解体前に必ず確認することが望ましいといえます。
アスベストONEで書類作成と進捗管理をワンストップで効率化
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)に関する書類作成と進捗管理をワンストップで支援するクラウドサービスです。
必要な情報を項目に沿って入力すれば、事前調査報告書・作業計画書・現場掲示用の看板PDFなどを自動生成。
同じ内容を何度も入力する必要がないため、書類作成の手間を大幅に削減できます。
また、GビズIDによる電子報告にも対応しており、CSV形式で出力したデータをアップロードするだけで、煩雑な手入力作業を省き、スムーズな報告が可能です。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく、下請け業者や協力会社との情報共有もスムーズに行えます。
全体の工程を明確に把握しながら、法令に沿った対応を効率的に進めることができます。
初めての方でも安心して運用いただけるよう、アスベスト対応に関するご相談も随時承っております。
EMSでは、現場に即した実務の視点から、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内し、皆さまの業務負担の軽減と、確実な法令対応をしっかりとサポートいたします。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
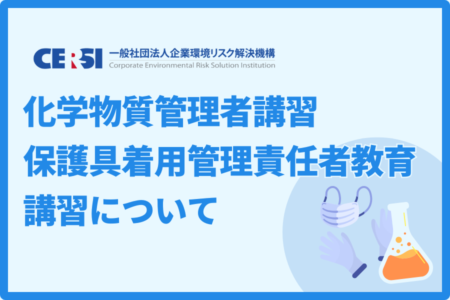

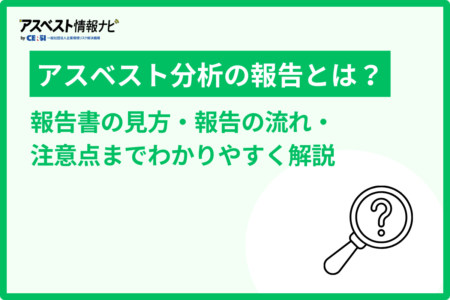











_20250214.png)
