外壁に使われるアスベストとは?見分けポイント&含有判定方法ガイド
- 最終更新日:

本コラムでは、外壁に使われてきたアスベストの実態と、見分け・対応の実務ポイントを整理します。 ・外壁材にアスベストが使用されていた背景と、含有リスクが高い建築年代・建材 ・外壁にアスベストが含まれているかを確認するための現実的な見分け方と調査方法 ・含有が判明した場合に求められる法的手続きと、改修・解体時の適切な対応フロー 外壁工事や建物管理に関わる立場として、知らなかったでは済まされない実務上の要点を解説します。
外壁にアスベストは使われている?
外壁材にはかつて多くの建築物でアスベストが使用されてきました。
特に2006年9月1日以前に着工された建物は使用されている可能性が高く、注意が必要です。
アスベストは耐火性、断熱性、耐久性に優れ、しかも安価に調達できたことから1970年代から1990年代にかけて幅広い外壁建材に混入されていました。
住宅だけでなく、工場や倉庫、公共施設などにも使われ、使用箇所も外壁材や屋根材、さらには内装材にまで広がっていたのです。
代表的なものとしてはスレート板や窯業系サイディング、押出成形セメント板が挙げられます。
外観は一般的なセメント板やサイディングと変わらないため、見た目だけでアスベスト含有の有無を判断することはほぼ不可能です。
築年数が30年以上経過している建物を所有する場合、あるいは改修や解体を検討している場合には、外壁にアスベストが含まれているかどうかを確認することが非常に重要になります。
外壁のアスベストを見分ける理由とその必要性
外壁にアスベストが含まれているかどうかを見分けることは、健康被害の防止・法令順守・資産価値の観点から非常に重要です。
アスベストは繊維が空気中に飛散すると吸入によって体内に蓄積し、長い年月を経て石綿肺や悪性中皮腫など深刻な疾病を引き起こすことが知られています。
そのため解体や改修を行う際に、外壁にアスベストが含まれているかどうかを把握し、飛散防止措置を講じることは欠かせません。
また、建築物の事前調査は建物所有者や発注者(施主/工事の注文者)、そして工事を請け負う元請業者に調査・報告の責任があります。
怠れば罰則の対象となり、工事関係者だけでなく周辺住民にまで健康リスクを及ぼすおそれがあります。
さらに、資産価値の面でも見分けは重要です。
アスベストを含む外壁材は撤去や処理に追加の費用が必要となるため、売買や相続の際に評価へ影響を与えます。
したがって、外壁にアスベストが含まれているかどうかを正しく見分けることは、健康・法令・経済の観点から欠かせないポイントなのです。
外壁として使用されるアスベストの種類
外壁に使われてきたアスベスト含有建材にはいくつかの特徴的なものがあります。
窯業系サイディングは2000年代まではアスベストが含まれているケースが多く、現在普及している非含有品と外観がほとんど変わらないため判別は極めて困難です。
スレート板は灰色のセメント板で、住宅や工場の外壁や屋根に広く使われてきました。
波型スレートや平板スレートなど形状はさまざまですが、いずれもアスベスト含有の可能性があります。
押出成形セメント板は重量感があり、表面に凹凸があるのが特徴で、耐火性が評価され外壁に採用されてきました。
こうした建材は現在も多くの建築物に残っており、外観からアスベスト含有の有無を見分けることは困難です。
製造年代やメーカーの仕様を確認しても、アスベストの有無が明確になるとは限りません。
最終的には専門的な分析が必要となるため、外壁材に関しては「種類を知る」ことが第一歩であり、その後の調査につなげることが重要になります。
外壁にアスベストが含まれているか見分ける方法
外壁にアスベストが含まれているかを確認するためにはいくつかの手順を踏む必要があります。
まず大前提として建築年の確認が有効です。
2006年9月1日以前に着工された建物はアスベスト含有建材の使用可能性があり、特に1980年代から1990年代にかけて建築された住宅や工場では注意が必要です。
そのうえで建築当時の設計図や施工仕様書を確認することにより、記載された建材名やメーカー名から含有の有無を推測できる場合があります。
ただし、実際には外観や図面だけでの判定は不十分であり、最終的には有資格者による調査が欠かせません。
発注者や建物所有者が解体や改修を予定している場合、事前調査を行うことが義務づけられています。
この事前調査では、まず設計図書や現地確認を行い、それでも判定が難しい場合には外壁材からサンプルを採取し、分析機関で顕微鏡を用いた分析などを実施します。
こうして分析を経て初めて、外壁にアスベストが含まれているかどうかが確定されます。
外壁にアスベストが含まれていた場合の対処法と流れ
外壁にアスベストが含まれていることが判明した場合には、法令に沿った手続きを踏む必要があります。
特に、一定規模以上の改修・解体工事の場合には、調査結果を行政に報告する義務があります。
この際、GビズIDを利用した電子報告が必要となり、入力作業が煩雑になることもあります。
こうした手続きは建物所有者や元請業者が責任を持って実施しなければならず、怠れば罰則の対象となる可能性があります。
その後は作業計画を策定し、飛散防止措置を徹底しながら工事を進めます。
養生や湿潤化などによって繊維の拡散を防ぎ、作業従事者と周辺住民の安全を守ることが不可欠です。
続いて重要になるのは、実際の作業現場での管理体制です。
外壁材を撤去する際には、作業区域を明確に区切り、関係者以外の立入制限を行うことが求められます。
工事の規模や対象建材の種類によっても必要な措置が異なります。
また、作業従事者は防じんマスクや保護衣を着用し、作業後には濡れ雑巾や高性能真空掃除機等を用いて粉じんを取り除いたうえで退場することが必要です。
廃棄物についても石綿含有産業廃棄物として厳格に管理され、耐水性のプラスチック袋等で梱包したうえで許可業者に引き渡されなければなりません。
さらに、工事の進行に合わせて作業記録を残し、完了後には報告書としてまとめ、発注者に説明することが義務付けられています。
これらの手順を踏むことで、建物所有者や元請業者は法令順守を果たし、周囲に対する安全を確保できます。
外壁にアスベストが含まれている場合の対処は時間も費用もかかりますが、手続きを適切に進めることで、将来的なトラブルやリスクを最小限に抑えることにつながります。
アスベスト分析から書類作成・電子報告まで、クラウドで完結。現場の業務効率化を今すぐ実感
建設現場のアスベスト対応業務は、分析の手配、進捗確認、法令に沿った書類作成、行政への報告など、煩雑で時間のかかる業務が多く、担当者の大きな負担となっています。
こうした業務に追われて、「本来の作業に集中できない」「毎回の対応が手探りで大変」…そんなお悩みはありませんか?
アスベストONEは、分析依頼から書類作成、電子報告までをクラウド上で一元管理できるサービスです。
必要な情報をクラウド上のフォームに入力するだけで、分析依頼が完了し、進捗もリアルタイムで確認可能。
作業計画書や報告書、現場掲示用の看板PDFなども自動生成され、書類作成にかかる工数を大幅に削減できます。
出力される書類は法令に準拠したフォーマットなので、記載漏れや誤記のリスクも軽減。
さらに、GビズIDに対応した電子報告も可能で、手入力による煩雑な作業から解放されます。
また、クラウド上でのデータ共有により、現場・事務所・協力会社の間で常に最新の情報が確認できるので、手戻りや無駄な確認作業も減り、スピーディーで確実な業務連携が実現します。
アスベスト対応における事務負担の軽減、コスト削減、法令対応の徹底を、ぜひアスベストONEでご体感ください。
まずは無料の個別相談で、貴社の現場に合わせた最適な活用方法をご提案いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)



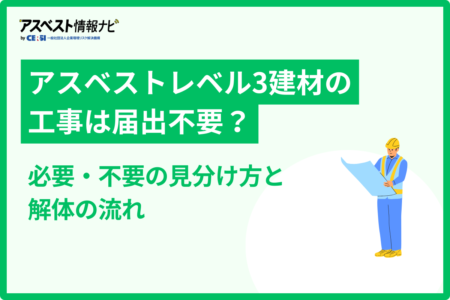











_20250214.png)
