アスベスト規制の歴史と法改正のポイント
- 最終更新日:

「この建物、大丈夫かな?」「昔に建てた物件にアスベストが使われていたら…」と、不安を感じたことはありませんか?
建物所有者にとって、アスベストの存在は単なる過去の問題ではなく、いまなお法的・社会的責任を伴う重要な課題です。
かつて「奇跡の鉱物」と呼ばれたアスベストは、その後、深刻な健康被害とともに社会問題へと発展し、国内では段階的に規制が強化されてきました。
本記事では、アスベスト規制の歴史を体系的に振り返り、建築物に関する規制の流れや、現行法で求められる対応までをわかりやすく整理します。
アスベストが使用されてきた背景と社会的影響
かつて「奇跡の鉱物」と呼ばれたアスベストは、日本の高度経済成長を支えました。
しかし、その裏には深刻な健康被害と長期にわたる社会的課題が隠されていました。
今なお私たちの身近に残るリスクと、その対応の必要性について解説します。
高度経済成長期に広がったアスベスト利用
アスベストはその優れた耐火性・断熱性、そして安価で加工しやすい特性から、1950〜90年代の日本で建材として広く使用されました。
ビルや学校、住宅など多くの建築物に使われ、経済発展を支える資材として重宝されてきました。
健康被害の深刻さと社会的な反響
しかし後に、アスベストの繊維を吸い込むことで肺がんや中皮腫といった重大な健康被害を引き起こすことが判明しました。
中皮腫は発症までに数十年かかることもあり、現在でも年間1,500人以上の死者が出ているとされます。
2005年の「クボタショック」は社会に大きな衝撃を与えました。
石綿の使用が全面的に禁止された2006年9月より前に建てられた建物には、アスベストが使用されている可能性があります。
過去の教訓をもとに、今後の安全対策を講じることが求められています。
日本国内のアスベスト規制の始まりと主要な改正点
アスベストの健康被害が明るみに出たことで、日本では1960年代から段階的に規制が始まりました。
その後も法改正が繰り返され、現在では解体や改修時の厳格な調査義務も設けられています。
本章では、アスベスト規制の流れと社会的意義を解説します。
1960年から始まったアスベスト使用の規制
日本におけるアスベスト規制は、1960年にアスベスト製造工場等における労働者の健康障害予防のためにじん肺法が制定されたことが始まりとされています。
さらに、1971年には特定化学物質等障害予防規則(特化則)が制定され、アスベストの製造や取り扱いを行う作業場において、
局所排気装置の設置や呼吸用保護具の備え付けが必要になるなど、今日のアスベスト規制の大本となるような規制がかたち作られました。
特化則は1975年に改正され、5重量%を超えるアスベストの吹き付け作業が原則として禁止される等の措置がなされることとなります。
当時、肺がんや中皮腫との因果関係が注目され、労働者の健康被害防止や住環境の見直しが急務となっていたのです。
リスクの高まりを背景に、使用制限が段階的に進められました。
1996年には大気汚染防止法(大防法)が改正され、特定建築材料(吹付け石綿)を使用する一定要件をみたす建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、
発注者による事前届出、作業基準の遵守義務が規定されました。
2006年の全面禁止と既存建物への対応
労働安全衛生法施行令(安衛令)の改正により、2004年には一部製品、2006年にはアスベストを0.1重量%を超えて含む全製品(一部代替困難なものを除く)の製造・輸入・譲渡・提供・新規使用が禁止され、アスベスト製品は全面禁止されるに至りました。
しかし、すでに使用された建物のアスベストは依然として存在し、その管理や安全対策が必要とされ続けています。
規制は「使わない」だけでなく「残されたものへの対応」も必要となります。
また、2006年の全面禁止に先立ち、2005年には特化則からアスベスト関連の規制を分離した石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、
作業時の届け出や石綿作業主任者、特別教育などの規制が盛り込まれました。
近年の実務面での法整備と所有者の責任
2020年に大防法並びに石綿則が改正され、2021年より順次施行されています。
この改正により、有資格者による事前調査の原則義務化、一定規模以上の工事における石綿事前調査結果の行政への報告の義務化、写真等による作業記録の作成・保管、比較的飛散性の小さいとされるレベル3のアスベスト(石綿含有成形板)も大防法の対象になること、など、アスベストに関する規制は大幅に強化されました。
アスベストに関する法規制では、建設業者だけでなく建築物の所有者や管理者にも責任を求めています。
建築物の所有者や管理者は、建築物の利用者がアスベストにばく露しないようにすることが最優先事項となります。
このため、不動産取引に際して過去の石綿調査の記録を説明したり、劣化して飛散しやすくなったアスベストの除去・封じ込め・囲い込みなどの対応を行う必要があります。
現に、2023年には建物に劣化して飛散しやすい状態になってしまったアスベストがあるのに放置し、
従業員を建物内で働かせていた事業者が送検される、という事例も発生しています。
また、建築物の解体・改修工事を発注する際には、設計図書類の提供や写真撮影の許可、期間や費用に関して無理な条件をつけないようにするなど、
施工業者が適切なアスベスト対策が行えるよう配慮することが必要となります。
建築物におけるアスベスト規制の変遷(施工・使用禁止の年表)
アスベストが使用された可能性のある建物かどうかを見極めるには、施工年代と規制の進展を把握しておくことが重要です。
ここでは、日本におけるアスベスト規制の主な流れと、それが建物所有者に求める姿勢について解説します。
時系列で見るアスベスト規制の主な流れ
これまでに見てきた通り、日本では1975年に「石綿を 5 重量%超えて含有する吹付けアスベスト」が禁止されて以降、段階的に規制が強化されてきました。
1995年にはアスベスト含有量1%超の製品が原則禁止、2004年には一部建材の使用も禁止されました。
2006年にはすべてのアスベスト含有製品が全面的に禁止され、新規使用は不可能となりました。
建物の施工年代とリスク判断の重要性
規制の強化により、施工年代がアスベストリスクの大きな指標となります。
2006年9月1日より前に新築着工された建物では、屋根材や断熱材、外壁材などにアスベストが使われている可能性があるため、
改修・解体時には有資格者による石綿事前調査と適切な対応が求められます。法令遵守はまず現状把握から始まります。
なお、2006年9月1日以降に新築着工された建物についても、設計図書等により新築着工時期を確認する事前調査(書面調査)を行うことは施工業者の義務となっており、
記録の作成や一定規模以上の工事の場合は行政への報告についても適用されます。
法改正が求める社会的責任と意識改革
アスベスト(石綿)は、ばく露から健康被害発生までの潜伏期間の長さ、そして引き起こす健康被害の重篤さから「静かな時限爆弾」とも呼ばれています。
ここまで見てきたようにアスベストに関する規制は段階的に強化され続けており、2006年以降はアスベスト含有製品の新規使用は全面的に禁止されていますが、
過去にアスベストを使用して建設された建物の解体工事は2028年頃をピークに増加し続け、2050年頃までは続くものと推定されています。
インフラ更新などが社会問題化していることも重なり、今後も当面の間はアスベストへの対策は社会全体の大きな課題であり続けると考えられます。
直近の法改正はこのような状況下において、新たなアスベストによる健康被害を防ぐために建設業者への規制を強化するとともに、
建物所有者を含むステークホルダーに対し、責任を持ってアスベストの飛散を防止し、周辺住民や作業従事者の安全を確保することを強く求めるものであるといえるでしょう。
アスベスト問題が今後与える影響と最新の動向
アスベストの使用は禁止されているものの、過去に建てられた建物には今も多くが残っています。
法改正や人手不足といった最新の社会動向を踏まえると、今後ますます計画的な対応が求められます。現状と今後のリスクについて見ていきましょう。
2006年9月以前に建てられた建物に潜むアスベストと解体時のリスク
アスベストは健康被害のリスクが高いため全面禁止されていますが、既存の建物にはいまだに含まれているケースが少なくありません。
特に2006年9月以前に建てられた建物の解体では石綿の飛散リスクがあるため、有資格者による事前調査と適切な除去が義務付けられています。
法改正の進展と所有者への影響
2022年には施工業者(元請事業者)による石綿の有無の事前調査結果の報告が義務化されました。
建物所有者や管理者は、こうした法制度の変化に即応できる体制が求められています。
対応を怠れば、施工業者(元請事業者)が行政指導や罰則の対象となるだけにとどまらず、工事が中断したり、民事訴訟が発生するなど、発注者にとってもリスクとなる可能性があります。
最新の法規制を正しく把握し、アスベスト対応を施工業者任せにせず建物所有者も関心を持って取り組むことで、建物の維持管理、解体・改修におけるアスベストのリスクを最小化していくことが重要といえるでしょう。
法人向けのアスベスト対応チェックリスト・コンサル案内
アスベストに関する対応は、単なる法令順守にとどまらず、現場での安全確保や社会的信頼にも直結する重要な管理業務です。
特に2006年9月1日以前に着工された建物では、アスベスト含有建材が使われている可能性があるため、元請業者は工程開始前の確認と準備を慎重に進める必要があります。
専門支援を活用して全体工程を可視化
アスベストに関する対応は、調査の記録、作業方法の説明、作業計画の提出、現場掲示物の作成、作業結果の報告といった一連の書類業務を含みます。
これらの作成と管理は煩雑になりがちですが、それらをクラウド上で一元化できる「アスベストONE」という支援ツールもあります。
例えば、必要な書類を画面に沿って入力するだけで自動作成でき、現場掲示用のPDF看板も即時出力が可能です。
GビズIDとの連携によって電子報告の手間も軽減されるため、全体の業務効率を大幅に向上させることが期待されます。
建物情報のチェックと初期相談がカギ
まずは、解体・改修予定の建物がアスベスト(石綿)に関する法令の対象となるか、着工日や用途から確認を行ってください。
そのうえで、石綿含有建材の有無が不明な場合や、書類対応に不安がある場合は、早い段階で専門機関への相談を検討する必要があります。
「アスベストONE」では、クラウドを通じて建材分析の依頼・進捗管理・過去データの検索も可能なため、現場や出張先でも的確な判断を下す支援となります。
書類作成の手間を省き、対応の見える化を進めたい元請業者の方は、アスベストONEの導入をぜひご検討ください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)


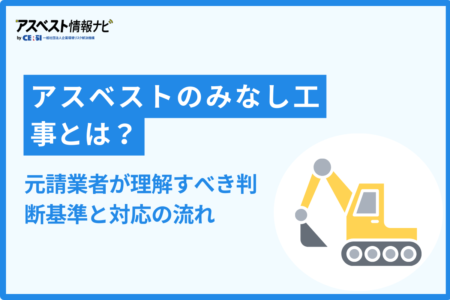











_20250214.png)
