アスベスト含有建材の年代別リスクと対策
- 最終更新日:
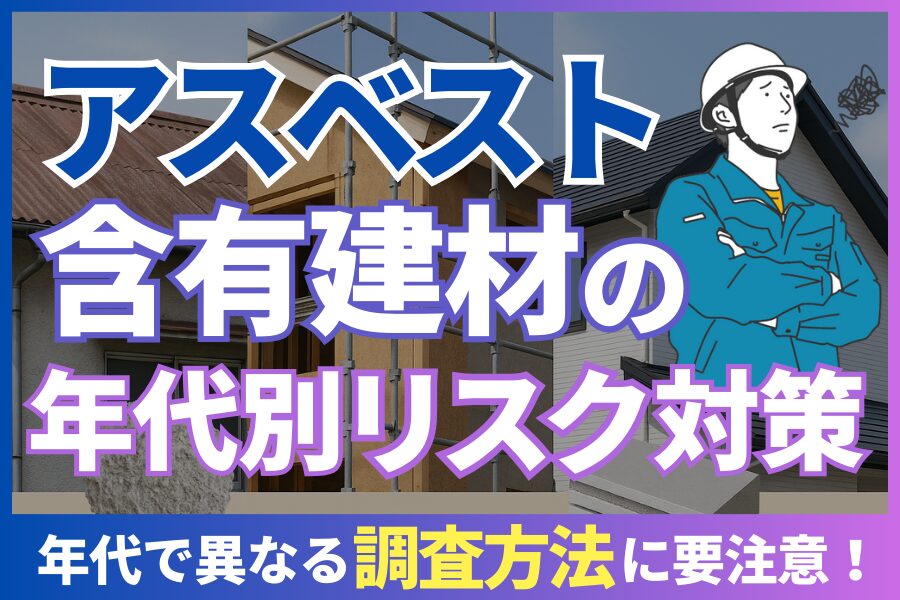
「この建物って、アスベスト(石綿)が含まれてるかもしれない…でも、どうやって判断すればいいの?」と不安に感じたことはありませんか?
特に、古い建物の管理やリノベーション予定の物件に関わっている方にとって、
アスベストの有無を把握することは健康リスクの回避や法令遵守における適切な対応の第一歩です。
この記事では、建物におけるアスベスト含有可能性の推定の手がかりや、含有建材の特徴・調査検査方法・対応策までをわかりやすく解説します。
アスベスト含有建材が使われていた年代と種類
アスベストはかつて「万能素材」として多くの建築物に使われていましたが、現在ではその健康リスクから使用が全面禁止されています。
リスクの正確な把握には、どのような建材が使用され、その建材の製造時期はいつなのかを調べる事が重要です。
1975年以前:吹付けアスベストの全盛期
1975年以前は、天井や配管周辺などに吹付けアスベストが多く使われていました。
このタイプは繊維が空中に飛散しやすく、深刻な健康障害の原因として問題視されました。
そのため、1975年に特定化学物質等障害予防規則により、石綿を 5 重量%を超えて含有する吹付けアスベストの使用が禁止されました。
1980年代:成形建材の注意点
1980年代には、スレート屋根材やケイ酸カルシウム板などの成形建材が主流になりました。
これらは通常、吹付け材と比べて繊維が飛散しにくいとされていますが、切断、穿孔や撤去などの作業時には飛散のリスクが残るため、
適切な作業方法と専門的な安全管理の対応が求められました。
1990年代以降:規制強化と残されたリスク
1990年代には、アスベスト含有率が1%未満に抑えられた製品が普及しましたが、それでもなお使用が続けられていました。
1995年には、アスベストを1重量%を超えて含有する建材の吹付け作業が禁止となり、さらに2004年10月1日には1重量%を超えるアスベスト含有建材や摩擦材、接着剤などの製造・輸入・使用等が禁止されました。
その後、2006年9月1日にはアスベスト含有量が0.1重量%を超える製品の輸入・製造等が全面禁止となり、アスベストの使用は一部を除き全面的に禁止されました。
しかし、素材の代替化が困難であったガスケットやグランドパッキン等の一部資材は2012年まで猶予期間が設けられたほか、当時の在庫建材が使用されたケースもあり、完全な排除には時間を要しました。
建物の着工年月日や使用されている建材の確認は、現在でもリスク管理において重要な要素となっています。
年代別に見たアスベスト含有建材の特徴・リスクレベル
アスベストの危険性を正しく判断するには、建物の建築年代と使用された建材の種類・状態を見極めることが欠かせません。
年代によって含有量も違い、使用状況や飛散リスクは異なるため、各年代の特徴を把握することが安全対策の第一歩です。
1975年以前:飛散性が高い吹付け材のリスク
1975年以前に建てられた建物では、天井や配管周辺に吹付けアスベストが多く使用されていました。
このタイプは非常に飛散性が高く、健康障害のリスクも大きいため、最も厳重な対応が求められます。
管理や除去には専門知識が不可欠です。
1980〜90年代:代替建材にも残る注意点
1990年代以降は、石綿を1重量%を超えて含有する建材の吹付け作業は禁止されましたが、スレート板やケイ酸カルシウム板といった成形建材が主流になりました。
これらは通常は飛散しにくいものの、劣化や改修・解体時にはアスベストが飛散する可能性があります。取り扱いには慎重な対応が必要です。
2000年代まで:規制強化前のグレーゾーン
1990年代には含有率を1%未満に抑えた製品が出回りましたが、規制は段階的だったため使用状況にはばらつきがあります。
建物の新築着工年月日からアスベスト含有の可能性を推定する方法
建物にアスベストが使われているかどうかは、新築着工年月日をもとに一定の目安を立てることができます。
特定の年代には使用頻度が高く、リスクも増すため、建物所有者や管理者はこの点をしっかり把握することが重要です。
竣工年月日では、アスベスト含有の判断根拠にはなりませんので、注意が必要です。
1960〜1980年代半ばは高リスク時期
アスベストは1960年代から1980年代半ばにかけて、断熱性や耐火性に優れた建材として広く使用されました。
この時期に建てられた建物は、天井や壁、配管の保温材などにアスベストが使われていた可能性が高く、特にリスクの高い年代とされています。
2006年以前の建物にも要注意
アスベストの使用は2004年に大幅に制限され、2006年に全面禁止となりましたが、それ以前の建物には在庫建材が使われていたケースもあり注意が必要です。
1970年代の集合住宅などでは、吹付け材の使用が確認されており、飛散リスクを伴うことがあります。
判断には公的資料の活用や専門調査の徹底を
より正確に判断するには、設計図や施工記録の確認、国土交通省が公開している*「アスベスト含有建材データベース」の参照が有効です。
建材メーカーや業界団体等のホームページにおいても、製品や製造年ごとの含有有無が公開されているケースがあります。
適法な資格を受持している調査者による現地調査を行うことが、法令遵守、作業従事者や周辺環境への安全の確保に重要となります。
*※建材・資材がデータベースに登録されていないことをもって「石綿なし」と判断する根拠とはなりません。
アスベスト含有建材の調査・分析方法と費用相場
建物の改修や解体を安全に進めるには、アスベスト含有の有無を事前に把握することが欠かせません。
外観だけでは判断できない場合が多いため、調査者または分析業者による正確な調査と分析が必要です。
調査の流れと費用の目安について解説します。
分析はサンプル採取と専門分析が基本
アスベストの有無を確認するには、まず石綿含有建材調査者が書面調査を行ったうえで、現地でも建材の種類や状態を目視確認します。
その後、必要に応じてサンプルを採取し、専門機関で分析を行います。
分析では、偏光顕微鏡やX線回折装置を用いて、アスベストの含有の有無と種類を特定します。
高い信頼性と公的機関の推奨
分析調査は、厚生労働省や環境省も推奨する信頼性の高い手法です。
とくに着工年・竣工年が古い建物や使用建材が不明な場合は、分析を実施することでリスク回避につながります。
現場での判断に頼らず、科学的な分析に基づく手法も調査の選択肢として有効です。
費用相場と検査の重要性
分析費用は1検体あたり3万〜6万円が一般的で、建物全体の調査では数十万円にのぼることもあります。
しかしながら、分析調査の結果「石綿なし」と判断されれば、飛散防止対策の費用のみならず、建材の廃棄時にかかる処理費用も大きく削減されます。
結果として、分析を行わず「石綿ありとみなす」場合と比較して、全体費用が安く抑えられるケースも少なくありません。
1980年代のマンション改修時に分析を実施し、天井材のアスベスト建材を事前に除去することで、安心・安全な工事を実現した事例もあります。
アスベスト含有建材への対応策(除去・封じ込め・囲い込み)
アスベストが含まれる建材に対しては、健康障害を防ぐための「除去」 「封じ込め」 「囲い込み」といった対応策があります。
建物の状態や用途、築年数によって最適な手段は異なります。ここではそれぞれの方法の特徴と選定のポイントを解説します。
除去:最も確実な対応方法
アスベストへの対応で最も安全性が高いのは「除去」です。
アスベストを含む建材を完全に撤去することで、長期的なリスクを排除できます。
ただし、分析調査業者による調査や適切な施工、廃棄物処理が求められ、費用や作業期間がかかる点は考慮が必要です。
封じ込めと囲い込み:一時的なリスク低減策
「封じ込め」はアスベストが露出・劣化していない場合に表面をコーティング材で覆う方法で、短期間の飛散防止に有効です。
一方「囲い込み」は、アスベストを板やシートで密閉する対策で、比較的コストが抑えられますが、いずれも根本的な解決には至らず、将来的な再対応が必要です。
専門家による判断と長期的な計画が重要
対応策の選定には、建物の築年数、使用状況、劣化度合いなどを踏まえた判断が不可欠です。
国土交通省や環境省も、改修や解体の際には「除去」を基本方針としています。
封じ込めや囲い込みはあくまで一時的措置であり、最終的には除去を見据えた長期的な管理が求められます。
法人建物の築年数に応じたアスベスト管理サポートのご案内
建物所有者や元請業者にとって、アスベスト(石綿)リスクへの適切な対応は、安全確保とコンプライアンス遵守の両面から重要な責務です。
特に1970年代から1990年代に建設されたオフィスビル、商業施設、工場、倉庫等では、アスベスト含有建材が使用されている可能性が高く、事前調査や管理計画が不可欠となります。
建築年代に応じたリスクの内容を正しく把握し、適切な手順を踏むことが、従業員・テナント利用者の安全と企業の社会的信用を守る第一歩となります。
最新法令に準拠したリスク対応支援
2022年4月の大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、
工事の規模に関わらず建築物の改修・解体工事に際しては、事前のアスベスト調査と結果の保管が義務化されました。
調査を怠った場合、30万円以下の罰金や工事停止命令が課される可能性もあり、元請業者や建物所有者には一層の注意が求められています。
EMSは、こうした最新法令への対応を見据えたリスク管理を支援しています。
調査結果に基づく行政報告書や作業計画書の作成支援も行い、法令違反リスクを低減できるようサポートを行っています。
サポートサービス・個別相談のご案内
アスベスト対応に着手する際、元請業者や建物所有者がまず行うべきことは、現状把握と適切な対策の方向性を早期に確認することです。
EMSでは、建物の築年数・用途・工事計画に応じた無料の個別相談を受け付けており、専門スタッフが現地状況を丁寧にヒアリングのうえ、法令遵守に則った対応を案内しています。
また、クラウド型システム「アスベストONE」を活用することで、事前調査結果報告書・作業計画書・作業報告書などの作成を効率化し、
行政対応に必要なデータの一元管理が可能であるほか、システム内で分析調査を依頼することも可能です。
法令違反リスクの低減と業務負担軽減を同時に実現するため、まずはお気軽にご相談ください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
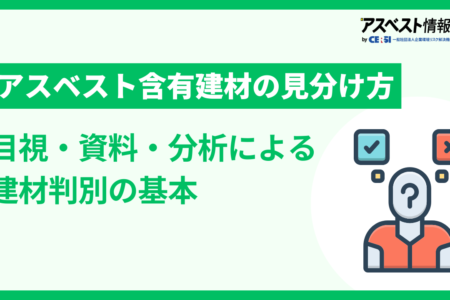













_20250214.png)
