アスベスト工事の対策ガイド|元請業者が知っておくべき法令遵守事項とコスト管理
- 最終更新日:

アスベスト工事では、通常の解体・改修工事とは異なる厳格な安全対策や法令対応が求められます。
しかし実務の現場では、「どこまで対策が必要なのか」「なぜそこまで厳しいのか」が
十分に理解されないまま工事が進められてしまうケースも少なくありません。
・アスベスト工事で対策が必要とされる理由と、健康リスクの基本的な考え方
・作業内容に応じたアスベスト工事の分類(レベル1〜3)と、それぞれのリスクの違い
・元請業者として押さえておくべき、届出・安全対策・体制整備のポイント
アスベスト工事における対策は、「念のため」ではなく、
法令とリスク評価に基づいて必須とされているものです。
本コラムでは、アスベスト工事に対策が必要とされる背景を整理したうえで、
作業分類ごとのリスクと、元請業者が実務で注意すべきポイントを解説します。
なぜアスベスト工事に対策が必要か?作業分類とリスク概要
アスベスト(石綿)は、吸入による発がん性が確認されている鉱物繊維であり、かつては建築資材として重宝されました。
吹付け材、保温材、断熱材のほかスレート、ケイ酸カルシウム板、Pタイルといった建材にも、石綿は広く使用されていましたが、
その健康リスクが明らかになった現在では使用が禁止されています。
アスベストの繊維は極めて微細であり、空気中に浮遊しやすく、吸入することで中皮腫や肺がん、石綿肺といった重篤な疾病を引き起こす可能性があります。
特に老朽化した建物の解体や改修工事の際には、アスベストが飛散するリスクが高まります。
このため、事前にしっかりとした対策を講じることが求められます。
アスベスト含有建材はその飛散性に応じて3つのレベルに分類されており、
レベル1は吹き付けアスベストのように著しく飛散しやすいもの、
レベル2は保温材や断熱材など飛散しやすいもの、
レベル3はスレートやPタイルなど比較的飛散性が低いとされる建材がそれぞれ該当します。
これらの分類に基づいて必要な措置や届出、保護具の基準が異なるため、元請業者としては事前の調査と正確な分類が非常に重要です。
必要な届出や法的義務を正しく理解する
アスベスト工事を行う際には、労働安全衛生法、石綿障害予防規則(石綿則)、大気汚染防止法といった関連法規に基づく複数の法的義務を遵守する必要があります。
特に、2022年4月以降はすべての建築物の解体・改修工事において、アスベストの有無を事前に調査し、その結果を労働基準監督署や自治体に報告することが義務付けられています。
さらに、レベル1およびレベル2作業を行う場合、工事の元請業者又は自主施工者は、建設工事計画届または建築物解体等作業届を労働基準監督署に、
工事の発注者は、特定粉じん排出等作業実施届出書を自治体窓口に、それぞれ届け出る必要があります。
また、大気汚染防止法に基づき、2023年10月からは「石綿事前調査結果の電子報告制度」が導入され、
アスベスト除去などの作業を伴う場合、着工前日までにGビズIDを用いて専用システムから調査結果を報告することが求められています。
これらの届出を怠った場合、労働安全衛生法違反として6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金といった罰則が科されるおそれがあります。
元請業者としては、関係法令を正確に理解し、適切な手続きを確実に実行する責任があります。
保護具・隔離措置・除塵など現場で求められるアスベストの安全対応
アスベストによる健康被害を防ぐためには、現場での安全対策が極めて重要です。
作業時の粉じん飛散性に応じて求められる対応は異なりますが、共通して言えるのは、作業員や周辺住民へのばく露を最小限に抑えるための設備と管理が必要という点です。
たとえば、レベル1およびレベル2建材を取り扱う作業では、電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR)や全身を覆う防護服、ニトリル手袋、安全靴などの保護具を装着することが義務付けられています。
レベル3建材を取り扱う作業であっても、防じんマスクや作業衣の着用が必要です。
また、レベル1およびレベル2建材の取り扱い作業時においては、作業エリアをポリシートなどで完全に隔離し、室内に負圧環境を作る必要があります。
出入り口には前室やシャワー室を設け、作業者が現場を離れる際にアスベストを外部に持ち出さないようにする措置が求められます。
作業そのものも、乾燥した状態で行うのではなく、事前に水や石綿飛散防止剤等を使用して十分に湿潤化させたうえで行う必要があります。
作業後はHEPAフィルター付きの掃除機を使い、残留したアスベストを徹底的に除去する必要があります。
アスベスト工事コストの内訳と補助制度の活用
アスベスト関連工事は通常の解体や改修と比べて高額になりがちです。
これは、事前調査、届出、隔離措置、専門的な除去作業、廃棄処分など、工程が多岐にわたるためです。
一般的に、事前調査費用だけでも3万円から15万円程度かかり、届出や書類作成に2万円から5万円程度が必要とされています。
隔離養生措置として負圧隔離を行うには10万円から50万円以上が必要な場合もあり、除去作業の費用は作業レベルや面積により数十万円から数百万円に達することもあります。
さらに、アスベスト含有廃棄物は通常の産業廃棄物とは異なり処分方法が限定されているため、処理費用も高額です。
これらの費用負担を軽減するため、多くの自治体では補助制度を設けています。
たとえば東京都内では、建築物石綿含有建材除去等助成として、中小企業や個人を対象に最大100万円までの助成が提供されている自治体もあります。
他の自治体でも補助率が2分の1~3分の2程度の補助制度が設けられていることが多く、元請業者にとってはこうした制度を活用することで、
産業廃棄物処理にかかる自社負担を軽減し、工事全体のコスト調整や円滑な実施につなげることができます。
協力会社を含めた体制整備のポイント
アスベスト工事を安全かつ円滑に実施するには、元請業者と協力会社が連携して作業体制を整えることが不可欠です。
まず、アスベストに関わる作業に従事する者は、所定の特別教育を修了している必要があります。
作業現場ごとに必ず1名以上の石綿作業主任者を選任することも義務付けられています。
現場ごとに作業手順書や緊急時対応マニュアルを整備し、作業に先立って全作業員へ周知(KY活動)を行うことが重要です。
元請業者と協力会社の間では、進捗確認や安全面のチェックを定期的に実施し、問題点を早期に共有・解決する体制が求められます。
また、作業の過程では写真や動画による記録、報告書の作成を通じて、実施内容を明確に記録し、3年間保管する必要があります。
これらの記録が不十分な場合、監督署からの指導対象となることがあるため、記録の一元管理体制の構築は極めて重要です。
さらに、アスベスト工事は複数の業者が関与する複雑な作業工程を伴うため、情報の伝達ミスや指示の行き違いが事故や法令違反につながるリスクをはらんでいます。
そのため、現場責任者を明確に定め、指揮系統を一本化することが現場の混乱防止に効果的です。
特に、協力会社が複数入る大規模な現場では、元請業者が中心となって統一的な安全ルールを定め、定期的な安全パトロールや是正措置を講じる仕組みを構築することが求められます。
加えて、アスベストに関する最新の法令改正や行政指導内容についても共有し、全体のコンプライアンス意識を高めていくことが、安全性と信頼性を保つうえで欠かせません。
人材不足や熟練作業者の減少といった課題もあるなかで、元請業者が率先して教育や技術継承を支援する姿勢が、業界全体の品質向上に寄与します。
書類作成のミス防止・業務負担の軽減に。アスベストONEがワンストップでサポート
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)対応業務をクラウドでワンストップで支援するサービスです。
煩雑な書類作成や進捗管理を効率化し、法令遵守の負担も軽減します。
項目に沿って情報を入力するだけで、事前調査報告書や作業計画書、現場掲示用看板PDF、作業方法説明書、作業記録、作業報告書まで、自動で作成できます。
法令準拠のフォーマットで出力されるため、記載漏れや誤記のリスクを抑え、書類作成にかかる時間も削減できます。
また、GビズIDに対応しており、CSV形式でデータを出力してアップロードするだけで電子報告が可能。
従来のように工事情報を手入力する必要がなく、負担やミスを防げます。
工事情報はクラウド上で一元管理され、社内・下請け業者・協力会社とスムーズに情報を共有します。
進捗状況もリアルタイムで見える化されるので、手戻りの少ないスピーディーな業務が可能です。
EMSでは、初めての方にもわかりやすく、現場の実情にあった運用方法を無料相談でご提案しています。
業務の正確性と効率化を両立したい方に、アスベストONEは最適です。ぜひご活用ください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
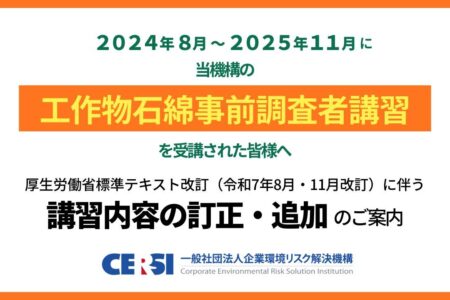
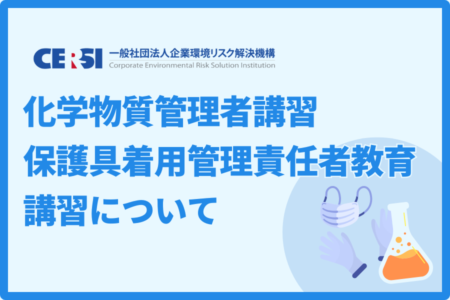
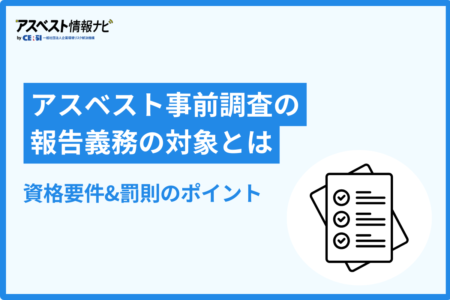











_20250214.png)
