アスベスト規制の全体像|法改正の流れと建設関係者が守るべき対応とは
- 最終更新日:

本コラムでは、アスベスト規制がどのように強化されてきたのかと、
現在の実務に直結する注意点を整理します。
・アスベスト規制の歴史と、段階的に使用禁止へ至った背景
・規制強化によって追加された事前調査・報告義務のポイント
・近年の法改正内容と、違反した場合に生じるリスク
過去の経緯を踏まえ、なぜ今、元請業者の法令対応が厳しく問われているのかを実務視点で解説します。
アスベスト規制の歴史と段階的な禁止の流れ
アスベスト(石綿)は、かつて断熱性・耐火性・耐久性に優れた素材として、建築や製造の現場で幅広く使用されてきました。
しかし、その一方で吸い込むことで肺がんや中皮腫といった重篤な健康被害を引き起こすことが次第に明らかとなり、国は段階的に使用を制限・禁止する方向へと舵を切っていきました。
規制の流れとしては、まず飛散性が高く特に危険とされる吹付けアスベストの使用が制限され、次に一部のアスベストを含む製品が禁止対象になりました。
その後も段階的に、含有率に基づく使用制限が厳格化され、現在では0.1重量%を超えて石綿を含有する建材の製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されています。
しかし過去に建てられた建物には、いまだ多くのアスベスト建材が残されており、建築年代によって使われている材料の傾向も異なります。
そのため、解体や改修工事を行う際には、建物が建てられた時期を参考にどのようなアスベスト建材が使われている可能性があるかを事前に把握しなければなりません。
特に古い建物では屋根材、外壁材などに吹付けアスベストが使用されているケースが多く見られます。
経年劣化等により、意図的に損傷を及ぼさずともアスベスト繊維が飛散する可能性があるため、建物所有者等は除去や封じ込めといった飛散防止対策が求められます。
アスベスト規制が強化された背景と社会的影響
1972年にILO(国際労働機構)やWHO(世界保健機関)がアスベストの発がん性を公的に認めたことを受け、日本政府は労働安全衛生法令に基づき、アスベストの使用禁止措置を段階的に進めていきました。
その後、2005年6月にアスベスト建材メーカーの工場において従業員やその家族、さらには近隣住民が中皮腫を発症・死亡していたことが公表されました。
これをきっかけに、アスベストによる健康問題は、単にアスベストを取り扱う労働者だけでなく、広く国民全体に関わる重大な社会問題として認識されるようになりました。
社会問題化する以前、アスベストは不燃性や耐熱性に優れていることから建材として広く利用され、私たちの生活のあらゆる場面で使用されてきました。
特に高度経済成長期には大量に輸入され、多くのアスベスト含有製品が製造されています。
しかし、アスベストによる中皮腫は発症までに20〜50年と非常に長い潜伏期間を要します。
アスベストが大量に使用されてからおよそ35年が経過した現在、潜伏期間のピークと重なる時期を迎えており、今後さらに健康被害の増加が懸念されています。
アスベスト規制に基づく調査・報告義務の概要と注意点
アスベストを含む可能性がある建物を解体・改修する際には、事前調査を行うことが法律で義務付けられています。
これは作業中にアスベストが飛散し、作業者や近隣住民に健康被害が及ぶのを防ぐために必要です。
事前調査は、まず設計図書などの書類を確認し、次に現地で目視確認を行います。
それでも判断が難しい場合には、建材の一部を採取し、専門機関による分析を行います。
ただし、この事前調査は誰でも実施できるものではなく、国が認定する講習を修了した資格者が行わなければなりません。
調査結果は、一定規模以上の場合は行政へ報告することが義務付けられており、未報告や虚偽の内容が含まれていた場合には、行政指導や罰則の対象になることもあります。
また報告した内容は3年間、書面として保管しておく必要があり、後日の確認にも、適切に対応できる体制を整えておくことが求められます。
さらに注意すべき点としては、元請業者が法的責任を負う立場にあるということです。
調査を外部に委託していたとしても、事前調査の結果の報告は元請業者が行わなければならず、適切に実施・報告されていなければ、責任を問われる可能性があります。
このようにアスベストに関する調査と報告は、単なる工事前の準備ではなく、建設工事における安全管理の根幹をなす重要なプロセスです。
したがって、関係者全員が法令の内容を正しく理解し、漏れのない対応を行うことが求められます。
最新のアスベスト規制動向と2020年以降の改正内容
アスベストによる健康被害から事業者や作業者を守るため、関連する法律は段階的に改正されてきました。
2020年以降の法改正では、制度の信頼性向上と現場での安全確保を両立させる仕組みへと進化しています。
事前調査・記録の保管の徹底
工事前には必ずアスベストを含むかどうかを調査し、その結果を記録・保存することが義務付けられました。
事前調査は図面などの書類確認と現場での目視確認を行い、その記録は3年間保管する必要があります。
さらに事前調査は国が定める講習を修了した資格者のみが実施するように限定され、より信頼性の高い対応が求められるようになりました。
アスベスト除去工事の改正内容
アスベスト除去工事については、工事後に資格者が粉じんなどが残っていないかを確認・記録することが義務化されました。
これは、見落としを防ぎ、確かな安全を担保するためです。
またアスベストを含む建材の切断や破砕を避けた施工方法や、工事現場を隔離するなどの飛散防止対策にも改善が加えられ、現場で不要な飛散が起きないような工夫が求められています。
アスベスト規制違反による罰則と行政指導の事例
アスベストによる健康被害を防ぐため、規制違反に対しては、罰則や行政指導等による非常に厳格な取り締まりが行われています。
アスベストを取り扱う際には、規定に従って適切な調査・報告や作業環境の管理が求められ、違反した場合には重い罰則が科される可能性があります。
例えば、建物の解体や改修工事前にアスベストの調査を怠った場合、アスベストが飛散し健康被害を引き起こすリスクが高まります。
このような場合、「調査義務違反」として最大で6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、さらには工事の差し止め命令が科されることがあります。
また、アスベストを取り扱う際に適切な防護措置を講じなかった場合、作業員や周囲の住民に健康被害を及ぼす恐れがあります。
これに対しては、労働安全衛生法などに基づき、行政から改善命令や是正指導が行われ、作業環境の改善や防護服の着用徹底が求められます。
さらに、行政指導では、違反した事業者に対し、違反内容の是正や改善を求める勧告が行われます。
これに従わなかった場合、さらに厳しい罰則が科されることになります。
実際の事例では、管理を怠ったまま行った建物の改修工事や、アスベストを含んだ廃材の不法投棄が問題となり、事業者に対して行政指導が行われたケースもあります。
建設業者、特に解体・改修工事の元請業者は、関係する法令規制を把握・理解し、適切な体制を構築することが法令違反リスクの第一歩となります。
書類作成のミス防止・業務負担の軽減に。アスベストONEがワンストップでサポート
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)対応業務をクラウドでワンストップで支援するサービスです。
煩雑な書類作成や進捗管理を効率化し、法令遵守の負担も軽減します。
項目に沿って情報を入力するだけで、事前調査報告書や作業計画書、現場掲示用看板PDF、作業方法説明書、作業記録、作業報告書まで、自動で作成できます。
法令準拠のフォーマットで出力されるため、記載漏れや誤記のリスクを抑え、書類作成にかかる時間も削減できます。
また、GビズIDに対応しており、CSV形式でデータを出力してアップロードするだけで電子報告が可能。
従来のように工事情報を手入力する必要がなく、負担やミスを防げます。
工事情報はクラウド上で一元管理され、社内・下請け業者・協力会社とスムーズに情報を共有します。
進捗状況もリアルタイムで見える化されるので、手戻りの少ないスピーディーな業務が可能です。
EMSでは、初めての方にもわかりやすく、現場の実情にあった運用方法を無料相談でご提案しています。
業務の正確性と効率化を両立したい方に、アスベストONEは最適です。ぜひご活用ください。



_20250217_すず-1024x154.jpg)

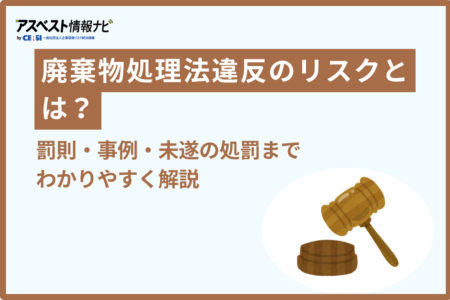













_20250214.png)
