アスベスト除去にかかる費用はいくら?相場から補助金まで徹底解説
- 最終更新日:

アスベストはかつて、建築資材として非常に重宝されていた鉱物繊維です。
耐熱性・断熱性・耐摩耗性に優れていたため、多くの建物の天井材や壁材、外壁、配管の断熱材などに広く使用されてきました。
しかし、その繊維を吸い込むことによって肺がんや中皮腫などの重篤な疾患を引き起こすことが明らかとなり、現在では原則として製造・使用が全面禁止されています。
建物の老朽化や解体に際して、アスベストの除去作業は避けて通れない工程となっています。
除去作業には高度な安全対策と専門的な知識が求められ、費用も決して安くはありません。
また、誤った知識をもとに不適正な業者に調査や施工を依頼してしまうと、健康被害だけでなく法的なトラブルにも発展する可能性があります。
一方で、国や自治体による補助金制度も整備されつつあり、正しい知識をもって適切に対応すれば、経済的な負担を軽減することも可能です。
本記事では、アスベスト除去の方法や費用相場、費用が高くなる背景、業者選定の重要性、さらには補助金制度の仕組みについて、詳しく解説していきます。
アスベストの除去方法とは
アスベストの処理方法には、除去、封じ込め、囲い込みの三つの方法があります。
もっとも根本的な解決策とされるのが除去です。
これはアスベストを物理的に完全に撤去する方法で、作業中はアスベスト繊維が空気中に飛散しないよう湿潤化や密閉空間の確保、負圧集じん装置の使用(レベル1・2建材)など厳格な安全管理が求められます。
作業後は廃棄物を石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)、もしくは廃石綿等(特別管理産業廃棄物)として適正に処理する必要があります。
次に、封じ込めはアスベスト含有部分を完全に撤去せず、そのまま表面を専用の封じ込め材で被膜・固定し、飛散を防ぐ方法です。
使用される材料には樹脂やシーラント剤があり、アスベストが損傷・劣化していない場合に適用されます。
最後に囲い込みは、アスベスト部分をボードや金属板などの板状材料等で覆い、物理的に隔離して飛散を防ぐ方法です。
これも長期的な維持管理が必要であり、将来的には除去が必要になるケースもあります。
どの方法を採用するかは建物の用途、アスベストの状態、施工予算などを考慮し、専門家によって判断されるべきです。
アスベスト除去にかかる費用相場
アスベストの除去費用は、使用されている建材の種類、面積、施工方法、作業環境などによって大きく変動します。
最も費用がかかるのは除去工法で、1平方メートルあたり1万5千円から5万円程度が相場とされています。
封じ込めや囲い込み工法であれば、1平方メートルあたり1万円から3万円程度とされ、比較的コストは抑えられます。
例えば、オフィスビルの天井材に吹付けアスベストが含まれており、100平方メートルを除去する場合、最低でも150万円、条件によっては500万円近くに達することもあります。
この金額には作業員の人件費、養生費用、飛散防止装置の設置費、廃棄物の運搬・処分費用などが含まれます。
さらに、施工前後のアスベスト濃度測定や分析費用が別途発生する場合もあります。
アスベストの除去費用が跳ね上がる理由
アスベスト除去の費用が高額になりやすい理由は、何よりも作業の高い専門性と法令遵守の徹底が求められる点にあります。
レベル1・2にあたる吹付け材や断熱材の除去等は、大気汚染防止法に定められる「特定粉じん排出等作業」に該当するため、発注者等に対して、作業開始14日前までに都道府県知事への作業実施届出が義務付けられています。
加えて、石綿障害予防規則に基づき、工事の元請業者に対して、着工14日前までに労働基準監督署への工事計画届出が義務付けられています。
これらには書類作成や行政対応のコストが伴います。
また、作業を実施するには「石綿作業主任者」などの有資格者が必要であり、通常の解体業務よりも人件費が高くなります。
作業時には全面養生による密閉空間の形成や負圧集じん装置の導入、保護具の着用など、極めて高い安全対策が求められ、それらにかかる資機材費用がコストに反映されます。
さらに、除去されたアスベストはその危険度に応じて処理区分が異なります。
レベル1・2にあたる吹付け材や断熱材などは「廃石綿等」とされ、「特別管理産業廃棄物」として厳重に扱う必要があります。
専門業者による収集・運搬・埋立処分が必要となり、受け入れ可能な最終処分場も限られているため、距離が遠い場合や処分量が多い場合には処理費用が高額になりがちです。
一方、レベル3に分類される成形板やスレート材などは通常の産業廃棄物区分の「石綿含有産業廃棄物」として処理されます。
ただしこちらも飛散防止のために適切な分別や袋詰めが必要であり、処理費用の負担は避けられません。
また、建物の立地条件や構造によっては足場の設置や重機の使用も必要になり、こうした付帯作業が費用高騰の一因にもなります。
アスベストの除去費用を専門業者に依頼するべき理由
アスベスト除去は、一般の解体業者ではなく、石綿に関する資格と豊富な実績を持つ専門業者に依頼すべき作業です。
理由としてまず第一に、アスベストの除去作業は労働安全衛生法や石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃棄物処理法など、複数の法令に基づいた届出と対応が求められるため、法的に適切な対応を行える知識と経験が必要です。
次に、飛散リスクを確実に抑える技術と設備を持っている点も重要です。
除去作業中は、微細なアスベスト繊維が空気中に飛散する可能性が高く、適切な養生や(負圧)隔離措置、作業区域のゾーニングが不可欠です。
専門業者はこれらの対策を熟知しており、近隣住民や作業員への健康リスクを最小限に抑えることができます。
さらに、廃棄物の処理に関しても、許可を得た業者でなければ取り扱いができません。
無許可業者に依頼した結果、不法投棄や環境汚染が発覚すれば、排出事業者である工事の元請業者自身も処罰の対象となる恐れがあります。
アスベストの除去に関連した補助金・助成制度とは
アスベスト除去にかかる費用は高額であることから、国や地方自治体は補助金や助成制度を設けています。
制度の有無や内容は地域によって異なるため、まずは各自治体の環境課や建築課に問い合わせることが大切です。
たとえば東京都では、一定の条件を満たしたうえで、住宅のアスベスト除去に関して最大で数百万円規模の補助が認められるケースもあります。
補助対象には除去工事費のほか、事前調査費や分析費、報告書作成費なども含まれる場合があります。
また、補助率は工事費の半額程度であることが多く、上限額も設定されています。
注意点として、補助を受けるためには事前の申請が必要であり、工事着工後の申請では対象外になることがほとんどです。
補助金を活用したい場合は、必ず工事前に自治体の窓口に確認を行い、書類提出のスケジュールや条件を把握しておきましょう。
アスベストONEで書類作成と進捗管理をワンストップで効率化
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)に関する書類作成と進捗管理をワンストップで支援するクラウドサービスです。
必要な情報を項目に沿って入力すれば、事前調査報告書・作業計画書・現場掲示用の看板PDFなどを自動生成。
同じ内容を何度も入力する必要がないため、書類作成の手間を大幅に削減できます。
また、GビズIDによる電子報告にも対応しており、CSV形式で出力したデータをアップロードするだけで、煩雑な手入力作業を省き、スムーズな報告が可能です。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく、下請け業者や協力会社との情報共有もスムーズに行えます。
全体の工程を明確に把握しながら、法令に沿った対応を効率的に進めることができます。
初めての方でも安心して運用いただけるよう、アスベスト対応に関するご相談も随時承っております。
EMSでは、現場に即した実務の視点から、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内し、皆さまの業務負担の軽減と、確実な法令対応をしっかりとサポートいたします。



_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
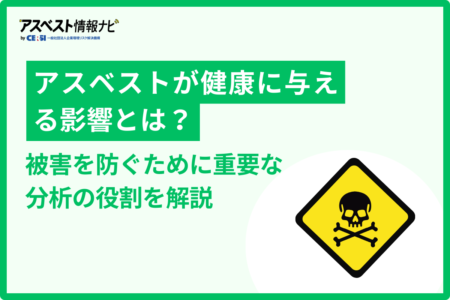

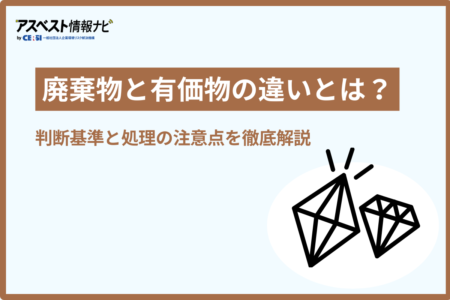











_20250214.png)
