アスベスト除去の全手順と費用相場|元請業者向けの安全・法令対応ガイド
- 最終更新日:

アスベスト含有建材への対応では、「除去・封じ込め・囲い込み」という複数の選択肢があり、
建材の種類や状態によって適切な対応が異なります。
一方で、費用や工期だけを理由に対応方法を選んでしまうと、
後々の法令違反や安全リスクにつながるケースも少なくありません。
・除去・封じ込め・囲い込みの違いと、それぞれが選択される判断基準
・建材レベルや使用状況によって対応方法が変わる理由
・実務で判断を誤りやすいポイントと注意点
対応方法の選択は、工事の安全性だけでなく、将来の維持管理や解体時のリスクにも直結します。
本コラムでは、アスベスト含有建材に対して、
どのような条件でどの対応が求められるのかを整理し、実務で迷いやすい判断ポイントを解説します。
アスベスト含有建材における除去・封じ込め・囲い込み基準
アスベスト含有建材への対応は、建材の種類や劣化状況、使用場所に応じて「除去」「封じ込め」「囲い込み」の3つの基本的な対処法が国の指針として定められています。
厚生労働省が定める石綿障害予防規則や環境省の指針に基づき、作業の適否を判断することが必要です。
「除去」は、アスベスト含有建材を完全に取り除く方法であり、以降のアスベストの飛散を完全に防止することができるため最も安全な工法といえます。
一方で、工期や費用などが大きくなりやすい工法でもあります。
「封じ込め」は、アスベストの繊維が空気中に飛散しないように薬剤などを用いて固化させる方法です。
劣化が進んでいない建材や、除去が建物の構造上困難な場合に選ばれることがあります。
ただし、施工後も定期的な点検が求められるため、長期的な維持管理が前提となります。
「囲い込み」は、アスベスト含有建材をボードやパネルなどで密閉する方法で、飛散防止が主な目的です。
この方法も、封じ込めと同様に原状の維持が可能な場合に限り、限定的に用いられます。
いずれの方法を採用する場合でも、建材の種類と使用場所の確認、専門家による適切な判断が不可欠です。
「封じ込め」「囲い込み」は「除去」と比べて作業時の石綿の飛散リスクは低く、また、工期や費用も抑えられますが、
将来的なアスベスト飛散のリスクを完全に取り除けるわけではなく、解体時には必ず除去作業が必要となります。
また、建築基準法では原則として増改築時にはアスベスト含有建材を除去することを求めており、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築時のみ、封じ込めや囲い込みを許容しています。
なお、レベル3の建材では封じ込め、囲い込みの工事は想定されておらず、除去が原則となります。
アスベスト除去工事の全体の流れと段取り
アスベスト除去工事は、法令に基づいた厳格な手順に沿って進められます。
まず最初に実施するのが事前調査です。
調査では、建物内の建材についてアスベストの有無を判定するため、資格を有する調査者が現地確認を行い、必要に応じて建材サンプルを採取し、分析機関で分析調査を実施します。
調査結果は、必ず発注者に説明するとともに、記録として作成し、3年間保管する必要があります。
アスベストが含まれていると判明した場合、次に行うのが作業計画の作成と届出です。
全レベル共通して作業計画の作成が義務付けられている他、レベル1またはレベル2の除去工事を実施する際には、労働基準監督署への作業届の提出が義務付けられています。
また、都道府県への大気汚染防止法に基づく届出も必要です。
届出後、現場の準備段階に入ります。
レベル1またはレベル2の除去工事を実施する場合は、養生と隔離区域の設置、負圧集じん装置の設置、エアシャワーや作業員動線の設計などを含めた養生作業を行います。
この工程は、アスベストの飛散を防止するうえで最も重要であり、基準を満たさない施工は行政指導の対象となります。
レベル3の場合も、一部の建材*では隔離が義務となります。(負圧までは不要) *仕上塗材の電動工具での除去やけい酸カルシウム板第1種の切断を含む除去の場合
実際の除去作業では、アスベスト繊維が空中に飛散しないよう、湿潤化処理を徹底してから作業を進めます。
除去後は、アスベストの取り残しがないことを確認する必要があります。
その後、廃棄物処理工程へと進みます。
除去されたアスベストは二重梱包するなど飛散防止の措置をとり、アスベストのレベルに応じて石綿含有産業廃棄物や廃石綿等の産業廃棄物処理業の許可を受けた収集運搬業者や処分業者と契約して適切に処理する必要があります。
最後に、アスベストの除去にかかわる作業の状況、作業従事者や、アスベストの取り残しがないことを記録した作業完了報告書を作成し、発注者に完了の報告をします。
アスベスト除去にかかる費用相場と費用増加の要因
アスベスト除去工事にかかる費用は、対象となる建材の面積、建物の構造、作業レベル、必要な飛散防止措置、廃棄処理の距離や量など、さまざまな要因によって異なります。
国土交通省が実施した調査では、レベル1の除去工事の場合、1平方メートルあたり2万円から5万円程度が相場とされています。
吹付けアスベストのように飛散性が高く、厳重な負圧隔離措置や気中濃度測定が必要なケースでは費用が大きく上昇します。
また、作業区域の設定が複雑であったり、養生に時間を要する構造である場合には、その分だけ人件費や施工期間が増加します。
一方、成形板など比較的飛散性の低いレベル3の建材であっても、撤去物の数量が多かったり、搬出経路に制約がある場合などにはコストがかさみます。
さらに、廃棄物処理場までの距離や、処分単価の地域差も費用に影響を及ぼします。
加えて、届出書類の作成や石綿作業主任者・特別教育受講者の配置といった法令対応のための人件費、各種測定や監督者による管理費用も加算されるため、工事全体の見積もりには慎重な精査が求められます。
現場で守るべき作業手順とアスベスト安全対策
アスベスト除去作業では、石綿障害予防規則および労働安全衛生法に基づいた安全対策の実施が義務付けられています。
まず石綿の作業に係る、作業員に対して特別教育を実施します。
アスベスト作業従事者は、アスベストによる健康被害のリスクや、作業に関する基礎知識と飛散防止技術、呼吸用保護具の使用方法などについて正確に理解している必要があります。現場では、アスベスト含有建材のレベルに応じた作業基準を遵守します。
事前調査の結果や、立ち入りを禁止する標識を設置します。
また、作業従事者は国家検定に合格した高性能な防じんマスクと専用の作業衣または保護衣を石綿の作業中着用し、石綿作業主任者はそれらが正しく着用されているかを監督する必要があります。
作業中は常に湿潤化処理を行い、乾燥した粉じんが飛散しないように配慮します。
使用する工具も、粉じんの飛散を抑える集じん機付きの電動工具や手工具が推奨されています。
作業終了後には、床面・壁面を清掃し、アスベストの取り残しがないことを確認しなければなりません。
これらの手順を遵守しない場合、作業停止命令や行政処分の対象となるため、元請業者としても現場管理の徹底が求められます。
作業が完了した後も、報告書の作成と記録の保存が必要です。
特に、作業工程ごとの写真や測定データ、使用した防護具や清掃方法などを正確に記録しておくことで、後日の行政指導やトラブル発生時にも証拠として活用できます。
また、住民や近隣への説明責任も重要です。
作業の概要や安全対策の内容、作業期間中の対応方法などを適切に周知することで、無用な不安や誤解を防ぐことができます。
アスベスト工事は、法律を守るだけでなく、信頼を得る姿勢も求められます。
現場ごとの特性をふまえ、作業の質を担保するためには、計画段階から完了後の管理まで一貫した対応が不可欠です。
アスベスト工事業者の選定時に確認すべき項目と契約内容
元請業者が協力業者にアスベスト除去作業を請け負わせる際には、業者の資格、実績、遵法体制を厳密に確認する必要があります。
石綿作業主任者の配置義務や、労働安全衛生法に基づく特別教育修了者の確保ができているかは最低限の確認事項です。
加えて、過去の行政指導歴や施工実績の内容、施工中の記録体制が明確であるかなども評価基準となります。
施工前には、除去対象建材の範囲、作業方法、隔離措置、飛散防止処理、廃棄物の搬出・処理方法までを含んだ詳細な工程表と見積書を取り交わすことが重要です。
アスベストONEで書類作成と進捗管理をワンストップで効率化
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)に関する書類作成と進捗管理をワンストップで支援するクラウドサービスです。
必要な情報を項目に沿って入力すれば、事前調査報告書・作業計画書・現場掲示用の看板PDFなどを自動生成。
同じ内容を何度も入力する必要がないため、書類作成の手間を大幅に削減できます。
また、GビズIDによる電子報告にも対応しており、CSV形式で出力したデータをアップロードするだけで、煩雑な手入力作業を省き、スムーズな報告が可能です。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく、下請け業者や協力会社との情報共有もスムーズに行えます。
全体の工程を明確に把握しながら、法令に沿った対応を効率的に進めることができます。
初めての方でも安心して運用いただけるよう、アスベスト対応に関するご相談も随時承っております。
EMSでは、現場に即した実務の視点から、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内し、皆さまの業務負担の軽減と、確実な法令対応をしっかりとサポートいたします。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
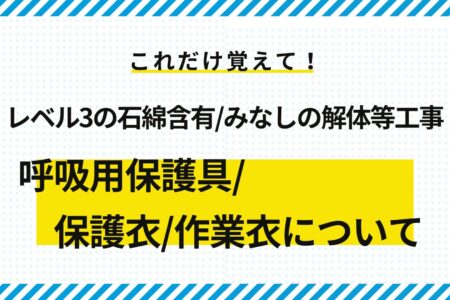

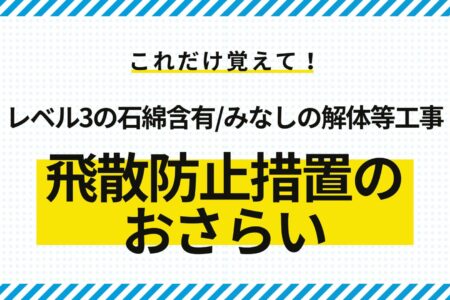











_20250214.png)
