木造住宅におけるアスベスト使用とリスク対策の全知識|見分け方から除去費用まで解説
- 最終更新日:

本コラムでは、木造住宅におけるアスベスト使用の実態と、調査・対応の実務ポイントを整理します。
・木造住宅でもアスベストが使用されてきた代表的な部位と、築年数による注意点
・健康被害リスクを踏まえた、見分け方と事前調査・分析の考え方
・アスベストが確認された場合の除去対策と、費用相場の目安
「木造だから大丈夫」という思い込みがなぜ危険なのかを、実例と制度の両面から解説します。
木造住宅におけるアスベスト使用箇所とは?
かつて日本では、アスベスト(石綿)が耐火性・断熱性・防音性などに優れた建材として幅広く利用されていました。
多くの方が「木造住宅ならアスベストは使われていない」と思いがちですが、それは大きな誤解です。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造に比べれば使用頻度は少ないものの、昭和30年代から平成初期にかけて建てられた木造住宅にも、下地材や断熱材、外壁、内装仕上げ材などにアスベストが含まれていることがあります。
例えば、屋根用化粧スレート、キッチン・浴室の壁材、ビニル床タイル、石膏ボード、そしてリシンやスタッコ、じゅらくなどの仕上塗材など、広く木造一戸建て住宅に使用されている材料でも過去に石綿が使用された建築材料は少なくありません。
特に、築年数が40年以上経過している木造住宅で、1970〜1980年代に建てられた物件では、設計図面や材料証明書が残っていないことも多く、実際にアスベストが使われているかどうかを判断するのが通常以上に困難になる場合もあります。
そのため、木造住宅だからといって安心せず、築年数やリフォーム歴を踏まえて、使用の有無を疑う姿勢が必要です。
木造住宅のアスベストがもたらすリスクと健康被害
アスベストによる健康被害は、アスベスト繊維を吸い込むことによって発症する肺線維症(じん肺)や中皮腫、肺がんなどが代表的です。
特に問題となるのは、建材が劣化して破損したり、リフォームや解体工事などで粉じんが発生する場合です。
通常の生活の中で建材の中にアスベスト繊維が封じ込められている状態ではリスクは低いですが、破砕や削り作業が行われると、空気中に微細なアスベスト繊維が浮遊し、吸入による健康被害が懸念されます。
木造住宅に使用されるアスベスト含有建材は、レベル3と呼ばれる飛散性の低いものがほとんどですが、それでも解体・リフォーム等の際に建材を損傷させると粉じんが発生し、これらの健康被害につながる可能性があります。
また、アスベストのリスクは即時に発症するわけではなく、曝露から数十年経過してから発症する「潜伏期間が長い」という特徴があります。
このため、過去にアスベストが使われた住宅での生活が将来的な健康リスクにつながる可能性も否定できません。
特に、家族を守るという観点からは、築年数の古い木造住宅について、専門家による調査を受けることが強く推奨されます。
木造住宅のアスベストを見分ける方法
木造住宅におけるアスベスト使用の有無は、見た目だけでは判別できません。
たとえば、スレート屋根やビニル床タイルは外観が似た製品も多く、アスベスト含有の有無を肉眼で判断することは不可能です。
したがって、まずは住宅の築年や改修歴、建材メーカー名などから対象製品の特定を試みる必要があります。
解体・リフォーム工事の前には有資格者である「建築物石綿含有建材調査者」により、アスベスト含有建材の有無を調べる事前調査を行うことが義務付けられています。
事前調査では、建築物の新築着工日や型番等からアスベスト含有の有無が判断できない場合、アスベスト含有ありとみなして工事を行うか、サンプルを採取して分析機関での分析調査を行います。
木造住宅のアスベスト事前調査と分析手法
2020年(令和2年)の大気汚染防止法および労働安全衛生法の一部改正により、すべての解体・リフォーム工事に先立ち、
建築物内にアスベスト(石綿)含有建材が使用されているかどうかを確認する「事前調査」の義務がこれまで以上に強化されました。
これは鉄筋コンクリート造のビルやマンションに限らず、木造住宅も例外ではありません。
したがって、木造住宅の小規模な改修工事や部分的な解体であっても、従来の事前調査の実施義務に加えて、事前調査は原則として有資格者(建築物石綿含有建材調査者)が行うこと、
一定規模以上の工事の場合には事前調査結果の行政への報告が必須となります。
調査の流れは一般に次のような手順で進められます。
まず初めに行うのは、設計図面、仕様書、過去の改修履歴などの既存資料の確認です。
これによって、当該建物にアスベストを含む可能性がある建材が使われている可能性が高い部位を書面上で推定し、現地調査の計画を立てます。
しかしながら、木造住宅の場合は築年数が古く、図面や資料が残っていないケースもあることに注意が必要です。
現地での目視調査は、厚生労働大臣の登録講習を修了した「建築物石綿含有建材調査者(特定または一般)」という有資格者が担当します。
現地にて目視調査や建物所有者への聞き取りを行い、必要に応じて建材の一部をサンプリングし、JIS A 1481に準拠した分析(主に偏光顕微鏡またはX線回折法)を専門の分析機関へ依頼します。
採取されるのは、吹付け材、壁材、床材、断熱材などで、アスベストの含有有無および種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト)が明確に判断されます。
事前調査の結果は、調査者によって「石綿事前調査結果報告書」にまとめられます。
この報告書は、大気汚染防止法および労働安全衛生法石綿障害予防規則に基づいて、解体等工事の元請業者が、地方自治体や労働基準監督署に電子システム(石綿事前調査結果報告システム)を通じて報告することが義務付けられています。
さらに、これらの書類は3年間保存することが求められ、監査や行政調査時に提示できるように整備しておく必要があります。
なお、建材の分析にかかる費用は、1検体あたり2万円程度が相場であり、住宅全体で複数の検体を採取・分析する場合、費用は数万円から十数万円になることもあります。
したがって、木造住宅の改修・解体を検討している場合は、あらかじめアスベストの有無を想定し、専門家に相談のうえ、余裕をもった準備と予算計画を立てておくことが重要です。
調査・分析の適切な実施は、作業従事者の安全確保だけでなく、近隣住民や居住者への健康被害リスクを防ぐうえでも欠かせない取り組みです。
木造住宅のアスベスト除去対策と費用相場
アスベストが含有されていることが確認された場合、撤去にあたっては「アスベストレベル」に応じた管理が必要です。
木造住宅で多く見られるのは「レベル3」と分類される成形品(スレート、ビニル床タイルなど)で、この場合でも「作業計画の作成」「看板設置」「作業記録の保管」「特別教育の実施」などが義務付けられています。
除去作業は、専門業者による湿潤化処理、飛散防止シートの設置、HEPAフィルター付き掃除機による清掃などの工程を経て、安全に実施されます。
木造住宅一軒分のアスベスト除去費用は、部位や量にもよりますが、30万〜150万円程度が一般的です。
さらに、分析・報告・届出などの事前費用を加えると、ある程度まとまった費用が必要である場合が少なくありません。
各自治体によっては補助金制度を設けている場合もあるため、事前に地元の市区町村に相談するのも一つの一つの選択肢といえるでしょう。
アスベストONEで書類作成と進捗管理をワンストップで効率化
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)に関する書類作成と進捗管理をワンストップで支援するクラウドサービスです。
必要な情報を項目に沿って入力すれば、事前調査報告書・作業計画書・現場掲示用の看板PDFなどを自動生成。
同じ内容を何度も入力する必要がないため、書類作成の手間を大幅に削減できます。
また、GビズIDによる電子報告にも対応しており、CSV形式で出力したデータをアップロードするだけで、煩雑な手入力作業を省き、スムーズな報告が可能です。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく、下請け業者や協力会社との情報共有もスムーズに行えます。
全体の工程を明確に把握しながら、法令に沿った対応を効率的に進めることができます。
初めての方でも安心して運用いただけるよう、アスベスト対応に関するご相談も随時承っております。
EMSでは、現場に即した実務の視点から、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内し、皆さまの業務負担の軽減と、確実な法令対応をしっかりとサポートいたします。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)

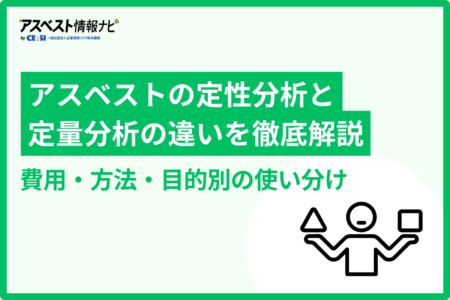
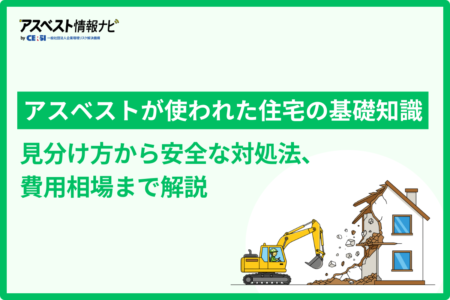
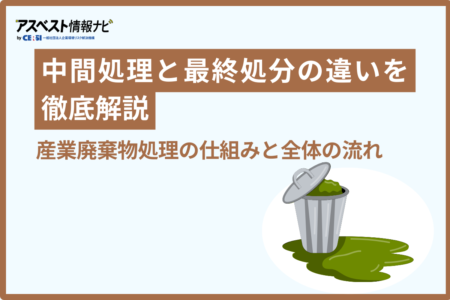











_20250214.png)
