アスベスト法改正ガイド|過去の規制から最新動向、適法工事の進め方を解説
- 最終更新日:

本コラムでは、アスベスト規制がどのような経緯で強化されてきたのか、その歴史と背景を整理します。
・高度経済成長期にアスベストが広く使われた理由
・健康被害の顕在化を受けて進められた規制強化の流れ
・現在の法改正で元請・発注者に求められる対応
過去から現在までの規制の流れを踏まえ、今なぜ厳格な対応が求められているのかを解説します。
アスベスト規制の歴史
アスベストは高度経済成長期を中心に、住宅やビル、工場、学校といった建築物に多く使われてきました。
耐火性や断熱性、耐久性に優れていたため、外壁材や屋根材、天井材、床材、さらにはボイラーや配管の保温材、ブレーキ部品など、建築から自動車部品まで多岐にわたる分野で利用されました。
安価に大量供給できたこともあり、当時の建設需要に応える理想的な素材と考えられていました。
しかし、1970年代以降、アスベストを長期にわたり吸入した労働者が石綿肺や悪性中皮腫といった重篤な病気を発症していることが次第に明らかになりました。
アスベスト繊維は肉眼では確認できないほど微細で、一度吸い込むと肺の奥深くに沈着しやすく、体外に排出されにくい性質を持っています。
このことが慢性的な炎症や線維化を引き起こし、数十年の潜伏期間を経て健康被害が現れるという特性を持つため、規制の必要性が社会的に強く認識されるようになりました。
日本で最初に大きな規制が導入されたのは1975年でした。
この年、特定化学物質等障害予防規則に基づき、重量比5%を超えるアスベストを含む吹付け材の使用が原則禁止されました。
当時の吹付け工法は火災対策として多用されていたものの、施工時や老朽化に伴う飛散リスクが非常に高いことが問題視され、最初に規制対象となりました。
その後1995年には基準がさらに厳格化され、重量比1%を超えるアスベストを含む吹付け材が全面的に禁止されました。
併せて、労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト(茶石綿)やクロシドライト(青石綿)といった危険性の高い種類のアスベストについては、輸入や製造そのものが禁止されました。
2004年には労働安全衛生法が改正され、規制は吹付け材にとどまらず、アスベストを含む建材全般や摩擦材、接着剤などに拡大されました。
さらに決定的な規制が施行されたのが2006年9月1日です。
この改正により、重量比0.1%を超えるアスベストを含むすべての製品について、製造・輸入・使用が全面的に禁止されました。
これにより、日本国内で新規にアスベストを含む建材や製品を扱うことはできなくなりました。
アスベスト法改正の背景や目的
飛散したアスベスト繊維を吸入することで、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫などの疾病を引き起こす可能性が指摘されており、被害は長い潜伏期間を経て表面化しました。
特に、建材製造や建設工事等の労働現場でばく露した人々が高齢期に病気を発症する事例が増加し、国際的にもアスベストの危険性が問題視されました。
法改正の目的は、新たなばく露を防止し、これ以上アスベストによる健康被害を増やさないことにあります。
解体や改修を担う作業従事者だけでなく、周辺住民の安全も守るために、事前調査の実施義務化や行政への報告制度が導入されました。
建物所有者や発注者(施主/工事の発注者)、元請業者などの責任を明確にし、法令を守ることが社会的責務として強調されるようになったのです。
このような背景のもと、規制は「使用禁止」から「適正な除去と管理」へと移行し、今なお建物に残存するアスベストに対処するための仕組みが整備されています。
アスベストに関係する最新の法規制
近年の改正では、解体や改修工事の際に事前調査を行う義務が強化されました。
2023年10月以降、アスベストを含有する可能性がある既存の建材に損傷を及ぼす作業を行う際には、事前に「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による調査が義務づけられています。
2022年4月以降、一定規模以上の工事においては、調査結果を所轄自治体・労働基準監督署に報告する義務も追加され、虚偽報告や未報告には罰則も設けられています。
また、GビズIDを利用した電子報告制度も導入され、事前調査結果をオンラインで提出できる仕組みが整いました。
これにより、従来の紙媒体での届出に比べて効率的かつ一元的な管理が可能となり、行政による監督も強化されています。
さらに、アスベスト分析の重要性も増しています。
書面調査(新築着工日の確認)やメーカーへの問い合わせ等によってアスベストの有無を判定できない場合に、アスベスト含有の有無の根拠となる唯一の手段です。
現場で採取された建材サンプルは分析機関で検査され、その結果をもとに工事計画が策定されます。
アスベスト飛散による危険性
アスベストが危険とされるのは、繊維が極めて細かく、肉眼では確認できないほど微小なためです。
これらの繊維は空気中に飛散すると容易に肺の奥まで到達し、一度吸入されると体外に排出されにくい性質を持っています。
その結果、長い年月を経て石綿肺や悪性中皮腫、肺がんなどを発症する可能性があるとされています。
建材に固められている状態では飛散のリスクは低いとされますが、老朽化や解体によって破砕されると一気に飛散し、ばく露の危険性が高まります。
特に事前調査を行わずに(=アスベストの有無を確認せずに)工事を実施した場合、適切な飛散防止対策が講じられず、作業従事者だけでなく、周辺住民まで被害が及ぶ恐れがあります。
アスベスト法改正に対応した工事の進め方
アスベスト法改正に対応するためには、建物所有者や発注者(施主/工事の注文者)、そして元請業者がそれぞれの責任を理解し、法律に沿った手続きを確実に踏むことが欠かせません。
アスベストは新規使用こそ禁止されていますが、既存建物には依然として数多く残されているため、解体や改修の際には必ず事前調査を行い、含有の有無を把握した上で適切な工事を計画する必要があります。
調査の結果、アスベストの含有が確認された場合には、作業計画を策定することになります。
作業計画では、工事の手順や使用する機材、飛散防止措置の方法、作業従事者の人数や役割分担などを詳細に記載します。
養生や湿潤化を徹底し、負圧集じん装置の設置(レベル1・2建材の場合)といった対策に加えて、作業区域を区切って関係者以外の立入を制限することも不可欠です。
区域を明確に分けることで、不要な人員の出入りを防ぎ、アスベスト繊維が現場外へ拡散することも防ぎます。
工事中には、作業従事者への安全配慮も徹底しなければなりません。
防じんマスクや保護衣の着用はもちろん、退場時には粉じんを洗い流すための設備を設けることも求められます。
これは作業者自身の健康を守ると同時に、家庭や周辺環境への二次的なばく露を防ぐためにも重要です。
また、工事の各段階で測定や点検を行い、計画通りに飛散防止が実施されているかを確認する体制も必要となります。
工事終了後には、作業記録を報告書にまとめ、保管しておく義務があります。
どのような手順で工事が進められ、適切に飛散防止措置が講じられたかを明確に記録することで、行政の監督を受ける際にも透明性を確保できます。
このように、アスベスト法改正に対応した工事の進め方は、単に現場で安全に作業を進めるための手順というだけでなく、社会的責任や法的義務を果たすための包括的なプロセスです。
建物所有者、発注者、元請業者のそれぞれが役割を理解し、協力して正しいフローを実践することが、将来的な健康被害を防ぎ、社会全体の安心を守る基盤となります。
アスベストONEで書類作成と進捗管理をワンストップで効率化
「アスベストONE」は、アスベスト(石綿)に関する書類作成と進捗管理をワンストップで支援するクラウドサービスです。
必要な情報を項目に沿って入力すれば、事前調査報告書・作業計画書・現場掲示用の看板PDFなどを自動生成。
同じ内容を何度も入力する必要がないため、書類作成の手間を大幅に削減できます。
また、GビズIDによる電子報告にも対応しており、CSV形式で出力したデータをアップロードするだけで、煩雑な手入力作業を省き、スムーズな報告が可能です。
工事情報はクラウド上で一元管理できるため、社内だけでなく、下請け業者や協力会社との情報共有もスムーズに行えます。
全体の工程を明確に把握しながら、法令に沿った対応を効率的に進めることができます。
初めての方でも安心して運用いただけるよう、アスベスト対応に関するご相談も随時承っております。
EMSでは、現場に即した実務の視点から、法令に沿った対応方法をわかりやすくご案内し、皆さまの業務負担の軽減と、確実な法令対応をしっかりとサポートいたします。



_20250217_すず-1024x154.jpg)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1024x160.png)
_20250303_すず-1280-x-200-px-1-1024x160.png)
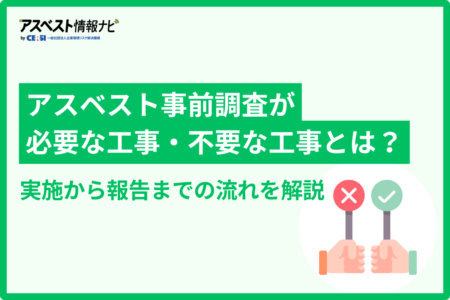













_20250214.png)
